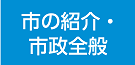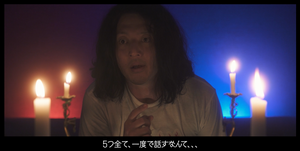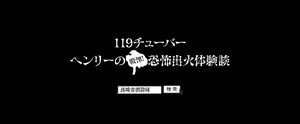ここから本文です。
戦慄!119チューバーヘンリーの恐怖出火体験談
更新日:2021年8月23日 ページID:037316
戦慄!119チューバーヘンリーの恐怖出火体験談
「119チューバー」称するヘンリーが長崎市消防局管内で実際に発生した火災の原因を再現し、恐怖体験として語ります。
ぜひ、動画を見ていただき、火災の予防について学んでください。
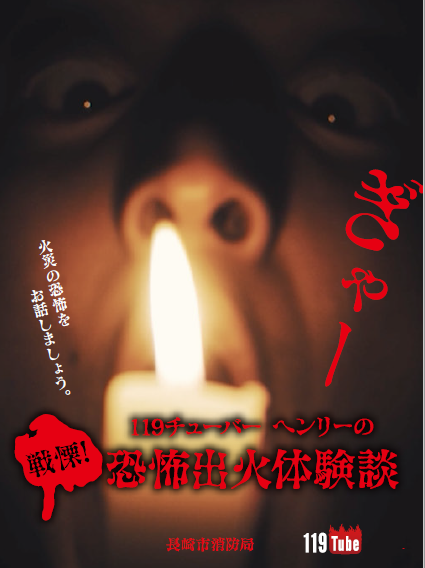
第壱部 生き霊?『無人の灰皿出火』編
1 火災原因
まだ火がついているたばこを灰皿に入れたため、他の吸殻に燃え移ったり、付近の燃えやすいものに着火し、火災になった。
2 予防対策
○ たばこは火を消してから灰皿に捨てる。
○ 吸殻を灰皿にためない。
○ 消火を確認せずにたばこをゴミ箱に捨てない。
○ 寝たばこはしない。
第弐部 妖怪?『火を噴くヘビ!配線短絡』編
『火を噴くヘビ!配線短絡』編 (新しいウィンドウで開きます)
1 火災原因
家具等により電気コードが挟まれたり、下敷きになったり、極端に折り曲げられていたため、ショートし、火災になった。
2 予防対策
○ コードは折れ曲がったままで使用しない。
○ 家具などでコードを踏まない。
○ コンセント付近はホコリをためずこまめに掃除する。
○ タコ足配線はしない。
第参部 怪奇現象?『黒鍋着火』編
1 火災原因
こんろで調理中に、来客や電話等によりその場を離れ、フライパンや鍋の中の食品や食油等が過熱発火し、火災になった。
2 予防対策
○ 調理中は火をつけたまま離れない。
○ コンロの周りには燃えやすいものを置かない。
○ 油火災には水をかけて消火はしない。
第四部 『怨霊?燃えるストーブ』編
1 火災原因
ストーブで、洗濯した衣類を乾燥させていたところ、衣類がストーブに落下し、着火し、火災になった。
2 予防対策
○ ストーブの近くに燃えやすい物を置いて使用しない。
○ ストーブの洗濯物を干さない。
○ 外出、寝る前にストーブは必ず消す。
第伍部 呪怨?『燃え上がる炎のローソク』編
『燃え上がる炎のローソク』編 (新しいウィンドウで開きます)
1 火災原因
仏壇にお供えをしようとした際に、ローソク火が着衣に着火し、火災になった。
2 予防対策
○ 仏壇でローソクに火をつけるのはお供え物を供えたり、掃除や片付けの後に行う。
○ ローソクに火をつけたまま離れない。
総集編
TVCM編
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く