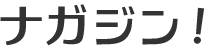「中島川沿いの遊歩道」
『シャッターチャンス@長崎』では、「長崎の観光名所はこの角度で撮るのがベスト!」という「ベストポジション」をご紹介しています。
また、長崎の街は数々の映画の舞台にもなっています。「あの映画のあのシーンはここで撮影された」という場所を見つけ、時にはその現場の「ベストポジション」もご紹介。 長崎の旅の記念になる最高の一枚を撮るためにぜひぜひお役立てください。

第14回目は、「中島川沿いの遊歩道」です。
前回紹介した「東古川通り」と、ちょうど直角に交わる中島川。元々多くの人々が集う憩いの場所でしたが、近年、周囲に遊歩道が設けられ、散歩を楽しむ人やベンチでくつろぐ人が増えました。長崎きっての観光名所「眼鏡橋」が架かるこの川は、訪れた観光客を驚かせるほどにとても小さな川……でも、この川には町の繁栄に大きく関わってきた歴史があります。
長崎の町を繁栄へと導いたのは、元亀2年(1571)の長崎開港後の南蛮貿易にはじまる海外との貿易。慶長2年(1597)に中島川沿いの田畑の地に〈材木町〉、〈本紺屋(もとこうや)町〉、〈袋町〉、〈酒屋町〉といった町が次々に造成され、以降、出島が置かれた鎖国時代を通し、この川は水運利用され長崎の町の中心となっていきました。慶長5年(1600)に長崎港内の中島側下流付近(出島周辺)が築かれ〈築町〉が誕生。寛永9年(1632)には、中島川西岸一帯が埋め立てられ、護岸が構築されました。長崎港内に停泊した外国船に積まれた貿易品を小分けして小舟に荷揚げ。その小舟が中島川をさかのぼり、町ごとに陸揚げされて商いが行われていたのです。中島川上流の堂門(どうもん)川に架かる「桃渓(ももたに)橋」をはさんだ2ヶ所には、唐船の安全を祈願した〈唐船安全祈願塔〉が現存し、小舟が上り下りしていた時代を今に伝えています。

中島川遊歩道

桃渓橋
それにしても、こんなに小さな川だというのに、「眼鏡橋」以外にも少し歩けば橋!また橋!の連続。こんなふうに、いくつもの橋が架けられた理由には諸説ありますが、この川に平行する風頭山麓に1600年代に建立された寺院が林立する寺町への参道として、寺院ごとに架けられたという説があります。「眼鏡橋」を架けたのは、日本初の唐寺、興福寺の二代目住持である唐僧 黙子如定(もくすにょじょう)。つまり「眼鏡橋」は興福寺への参道であったことを意味しているのです。また、中島川と平行する全長400mの長崎一古い「中通り商店街」も、元々はそれぞれの寺院へ参拝する道筋にあった門前町だったと伝わり、人々は、中島川に架かる橋を渡り、門前町を通り寺院へ参詣していたそうです。
上流から下流まで、わずか5kmほどの短い川に18橋もの石橋が架けられた場所は全国探してもほかに例はありません。寺院への参道として築かれて以降も長崎町民の生活道路として親しまれ、発展。今に至る歴史と、長きに渡りかつての風情を放っている空間が町中に存在し続けている……中島川沿いの風景は、長崎人の原風景であり誇り。そして、そんな風景に華を沿えるのが、まさしく四季折々の花々です。近年、春には市民団体の方々によって植樹された桜が花開き、梅雨の頃には長崎の市花である雨に濡れた紫陽花が楚々と咲く。夏には中島川の定番風景である柳と石橋、秋には、?原橋(市民会館横)から続く銀杏並木が黄金色に染まり、中島川周辺を彩ります。

紫陽花

銀杏並木
きれいに整備され、周囲に配された街路樹が四季を伝えてくれる中島川沿いの遊歩道。実は、この遊歩道の下は、川の流れを調整するバイパス水路が通っています。中島川は長い歴史のなかで度々氾濫。石橋は押し流され、人々は修復、架け替えを繰り返してきました。記憶に新しいところでは、昭和57年(1982)の「長崎大水害」でしょう。以降、多くが人工的な護岸となり、コンクリートの橋に架け替えられたりもして、かつての野趣溢れる風情は失われてしまいましたが、その分、人々が集うにふさわしい美しい空間が誕生しました。そして、新たな名所も生まれています。「ハートストーン」が護岸の石組みに埋もれているのです。グラバー園内のハートストーンが持つ「カップルでこの石に手を重ねると幸せになれる」「この石に触れて願いごとをすれば恋がかなう!」といった恋愛伝説同様、人気スポット! 歩いてみなければ、探せません!
そして、長崎といえば祭り! 以前、春に行われていた「中島川まつり」に代わり、夏に舞台を移し、2005年よりスタートした「中島川夏風情~長崎夜市」では、ライトアップされた眼鏡橋とその周辺が200個の提灯に照らされ、夜店はもちろん、様々な催しで賑わいます。浴衣姿の人も多く、昔ながらの夜市といった風情です。冬は、恒例の「長崎ランタンフェスティバル」。赤のランタンの灯りに包まれる中華街や他の会場とは違い、中島川を彩るのは黄色のランタン。水面に映る神秘的な灯りと石橋群も特筆すべき風景です。

長崎ランタンフェスティバル

ハートストーン
観光客の方々には、「眼鏡橋」を背景にパチり! というだけではなく、ぜひ、中島川の歴史の一端や周囲の風情に触れ、お気に入りの場所でのベストショットを狙ってもらいたいものです。
【中島川沿いの遊歩道】