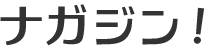「恵美須町界隈」
『シャッターチャンス@長崎』では、「長崎の観光名所はこの角度で撮るのがベスト!」という「ベストポジション」をご紹介しています。
また、長崎の街は数々の映画の舞台にもなっています。「あの映画のあのシーンはここで撮影された」という場所を見つけ、時にはその現場の「ベストポジション」もご紹介。 長崎の旅の記念になる最高の一枚を撮るためにぜひぜひお役立てください。

第15回目は、昔々は海だった!?「恵美須町界隈」です。
長崎の玄関口、長崎駅からほど近い場所に、おめでたい名称の町があります。〈恵美須町〉と〈大黒町〉、七福神の恵比寿様と大黒様、2神の名が付いた2町です。恵美須町の起源については、天正7年(?)(1579)と、寛永年間(1624?1644)だという2つの説がありますが、町名としては、かつて地内に祀られていた恵美須神社に由来しています。ポルトガル貿易により長崎港が開かれた当時、現在、長崎県庁が建つ地が海に突き出た岬の突端であったというように、その麓にあたるこの辺りは、もともと海であり、海の守り神である「恵美須神社」が祀られたのは納得のいく話です。一方、大黒町の誕生は、この恵美須町が大きくなりすぎたため、寛文12年(1672)、2町に分割した際、恵美須町にちなんで名付けられた町だといわれています。
恵美須町の大半は、瓊の浦(たまのうら)公園が占めています。瓊ノ浦(公園名は「瓊の浦」)とは長崎の古い呼名で、「瓊」は美しい玉(宝石)という意で、「美しい玉(宝石)のように光り輝く海、港」という意味。また、かつて存在した付近の町名には、天正13年?文禄元年(1585?92)に開かれた内町のひとつ、〈船津町〉があります。ここは、長崎で最も古い港で、付近一帯が船舶の発着場であり、金屋町にあった魚市場の船着き場でもありました。これらの町名からも、江戸時代から明治時代まで、この近辺を流れる岩原川の河口を埋め立てながら、長崎のまちは発展していったことが理解できますよね。長年、この付近には、市民に愛された〈恵美須、大黒市場〉がありましたが、平成24年度に老朽化のため取り壊しとなり、これまで暗渠となっていたかつての岩原郷、立山付近を水源とする岩原川の水路が出現。長崎のまちの遠い記憶が甦ってくる風景を目にすることができます。

瓊の浦公園

中町公園
江戸時代、大黒町辺りには、長崎港の警備にあたっていた諸藩の蔵屋敷(年貢米・特産物の保管・売却などを行っていた倉庫兼邸宅)がありました。現在、その山手付近には、中町教会、その隣に中町公園がありますが、中町教会は大村藩蔵屋敷跡に建てられています。殉教の歴史を持つこの地に日本人信徒のための教会を建てようと志した島内要助神父によって創立され、明治30年(1897)、献堂式が行われました。境内には日本二十六聖人のなかの3少年殉教者、ルドビコ茨木、アントニオ、トマス小崎の像があり、数々の殉教者を偲ぶとともに信仰の歴史を今に伝えています。中町教会が今の姿になったのは戦後のこと。戦前の建物は、原爆により焼失。残された小塔と外壁を生かし再建されました。長崎駅や市街地一の繁華街、浜町からも徒歩圏内にある、まちなかの教会のため、正午と18時には、町角で鐘の音を耳にすることができる中町教会。夕方の鐘が鳴る頃に瞬きはじめるイルミネーションも美しいですよ。

中町教会

岩原川の水路
一方、車道をはさんだ場所にある、中町公園は緑にあふれた清々しい公園です。遊具施設も整っているので家族連れも多く、周辺のビジネスマンの休息風景、お年寄りの散歩風景などにも多く出会う、様々な人々が集まる空間となっています。桜のシーズンには、まるで傘を広げたような姿の枝垂れ桜の満開風景に人々が集まります。中町公園は、長崎県復興事務所の跡地にできたため、園内には「戦災復興の建設碑」が建てられています。近隣の山のおかげで、原爆が落とされた山向うの浦上地区より被害が少ないものの、原爆の爪痕はまちのあちらこちらに残っているんです。
この近辺には、かつて〈小川町(こがわまち)〉という名の町もありました。旧町ごとに奉納する諏訪神社の秋の大祭「長崎くんち」ではお馴染みの町名です。もちろんこれも岩原川に由来する町名。家と家の間を縫うように巡る川の流れは、〈こがわ〉という名にふさわしい小さな川。しかし、周囲の立派な石積みといい、なかなか風情のある風景に出会えます。
長崎駅、日本二十六聖人殉教地から閑静な裏路地を通って恵美須町界隈へ。あまりなじみのない観光ルートかもしれませんが、教会、殉教、原爆、復興、古い地形……まちの歴史が散りばめられた場所でもあります。ぜひ、素敵な場所を見つけだして、バシッとシャッターを切ってください。
【恵美須町界隈】