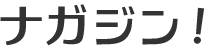「日本二十六聖人殉教地」
『シャッターチャンス@長崎』では、「長崎の観光名所はこの角度で撮るのがベスト!」という「ベストポジション」をご紹介しています。
また、長崎の街は数々の映画の舞台にもなっています。「あの映画のあのシーンはここで撮影された」という場所を見つけ、時にはその現場の「ベストポジション」もご紹介。 長崎の旅の記念になる最高の一枚を撮るためにぜひぜひお役立てください。

第17回目は、日本最初の殉教者の聖地「日本二十六聖人殉教地」です。
「明治日本の産業革命遺産」に続き、世界遺産登録の期待が高まっている「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」。その構成資産である、海に山に、大自然に溶け込むように現存する長崎県内の教会群は、ある出来事を機に建てられていったものでした。それは、献堂式(新築の会堂を神にささげる儀式)を終えたばかりの国宝 大浦天主堂で起きた「信徒発見」です。今年3月17日、奇跡と呼ばれるその出来事から150年を迎え、大浦天主堂での計7回の連続ミサのほか、各地で記念行事が行われました。この大浦天主堂は、1597年に殉教した日本二十六聖人に捧げられたもので、正式名称も「日本二十六聖殉教者聖堂」といいます。世界各国のカトリック信者たちが崇敬する二十六聖人の殉教地に向け、祈りを捧げるかのように建てられたのが国宝 大浦天主堂なのです。
さて、この日本二十六聖人とは、慶長元年12月19日(1597年2月5日)、豊臣秀吉の命令により処刑されたフランシスコ会宣教師6名と日本人信徒20名、日本で信仰を理由に処刑された初めての殉教者たちのことです。それは、日本人の心をとらえ、全国各地に広まりつつあるキリスト教に脅威を感じた秀吉が、戒めとして行った悲劇でした。


聖フィリッポ教会
昭和37年(1962)、日本二十六聖人列聖100年を記念して、殉教地である西坂公園に記念館と記念聖堂(聖フィリッポ教会)、レリーフが建立されました。設計は建築家 今井兼次氏、レリーフに嵌め込む日本二十六聖人等身大ブロンズ像は、彫刻家 舟越保武氏という、いずれも日本を代表する作家に依頼されました。実はお二人とも敬虔なカトリック信者。記念館と記念聖堂、レリーフ3点で、殉教者の精神を表現することに努めたのだといいます。
バルセロナのサグラダ・ファミリアで知られる建築家アントニオ・ガウディをいち早く日本に紹介した今井氏は、信仰と建築が一体となった中世カトリックの世界を実践し続けたガウディの創作方法に共鳴し、随所にガウディのエッセンスを盛り込みました。記念館の壁面と聖堂の象徴的な双塔部分には、聖人たちの故郷など、縁の地の陶片をモザイク状に敷き詰め、命無き陶片に永遠の命を与える歓びを表現しているのだといいます。それにしても、昭和37年当時、天に伸びた斬新なデザインのこの双塔は、観る人を驚かせたことでしょうね。

今井兼次氏制作レリーフ 26個のぶどうは26聖人を表している

記念館の壁面

レリーフの裏側にある記念館の入口
中ではキリスト教に関する貴重な資料を見ることができます。

また、レリーフに嵌め込まれた日本二十六聖人の昇天の様子が描かれた等身大像にも様々な意図が盛り込まれています。2体を除き、あとは合掌して天を仰ぐという全く同じ姿勢となっているのは、下に立って見上げる人に最も美しく見えるように、また、見る人と視線が合うことによって、その人の心を上の方に引き上げてくれる役割をするように考慮してのことだとか。
「パライソ(天国)、イエス、マリア」といって喜びを表したという最年少12歳のルドビコ茨木(右から9番目)。涙を流す両親に、微笑みながら「泣かないで、自分は天国に行くのだから」と慰め、隣のペトロ・バプチスタ神父に「神父様、歌いましょう」と言って賛美歌を歌った聖アントニオ13歳(10番目)。母への手紙に「心配しないように、弟たちをお願いします」と書いたトマス小崎14歳(20番目)。3人の少年がいることにも心動かされます。

聖アントニオ13歳、トマス小崎14歳
憩いの地として多くの人に親しまれている西坂公園、日本二十六聖人殉教地。今は高層ビルなどでめっきり見えづらくなりましたが、元来ここは、宣教師たちが乗り組んだポルトガル船来航のために開かれた長崎港が一望できる絶景地でした。長崎県が持つ、類い稀な宗教史に触れるには、まず、この地を訪れることをおすすめします。そして、語り継がれる歴史のシンボルを背景にぜひ素敵な一枚をパチりとどうぞ。
【日本二十六聖人殉教地】