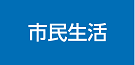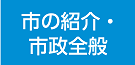ここから本文です。
国民年金
更新日:2024年7月27日 ページID:000435
国民年金の加入や免除申請
電子申請をぜひご利用ください
将来の年金額を簡単に試算
スマートフォンやパソコンで簡単にできます。
年金を納付しているかた
郵送先
〒812-8579 福岡市博多区榎田 1-2-55 AP榎田ビル
日本年金機構 福岡広域事務センター
各種手続きの詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。
- 転職・退職したとき ⇒国民年金への加入(新しいウィンドウで開きます)
- 学生以外の方で保険料を納めるのが困難なとき ⇒国民年金保険の免除制度・納付猶予制度(新しいウィンドウで開きます)
- 学生の方で保険料を納めるのが困難なとき ⇒ 国民年金保険料の学生納付特例制度(新しいウィンドウで開きます)
|
こんなとき |
必要なもの(郵送) |
|
|---|---|---|
|
加入 |
60歳未満で会社等を退職した(厚生年金等に加入していた) |
|
|
配偶者(厚生年金に加入していた)の退職・離婚・死亡・届出本人の収入増により、配偶者に扶養されなくなった |
|
|
|
納 付 ・ 免除 |
保険料を納めるのが困難なとき |
|
|
学生で保険料を納めるのが困難なとき |
|
|
※ マイナンバー(個人番号)記入による申請の場合、マイナンバーカード(両面)の写し、または(ア)と(イ)の両方の写しを添付
(ア)マイナンバーが確認できる書類 : 個人番号表示のある住民票の写し
(イ)本人確認書類 : 運転免許証、パスポート、在留カードなど
公的年金制度
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべてのかたは、必ず国民年金または厚生年金に加入することになっています。
ただし、60歳未満で老齢(退職)年金を受給しているかたは除かれます。
- 第1号被保険者:自営業のかた、学生のかた、無職のかたなど
- 第2号被保険者:厚生年金や共済組合に加入しているかた
- 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者として扶養されているかた
- 国民年金の資格取得・種別変更
- 次のかたは希望すれば加入できます(任意加入)
- 保険料と納め方
- 保険料を納めるのが困難なとき
- 次のかたは保険料が全額免除になります
- 産前産後の免除制度について
- 公的年金シミュレーターの開設
国民年金の資格取得・種別変更
上の1.に該当するかたや2.3.に該当しなくなったかたは、国民年金の資格取得または種別変更の手続きをしてください。
窓口
各地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、
日本年金機構 長崎南年金事務所(新しいウィンドウで開きます)
必要なもの
下表
※代理人の場合は委任状が必要  委任状(PDF形式 247キロバイト)
委任状(PDF形式 247キロバイト)
(ただしご本人と同世帯の世帯主が手続きをされる場合、委任状は不要です。)
お問い合わせ1
住民情報課総務係(電話番号095-829-1137)
日本年金機構 長崎南年金事務所(新しいウィンドウで開きます)(電話番号095-825-8705)
上の1.や3.に該当していた人が就職などにより2.に該当するようになった場合、手続きは新しい勤務先が行いますので、ご本人の市役所での手続きは原則不要です。
ただし、2.に該当する前に国民年金の保険料を口座振替にてお支払いをされていた場合は、変更後に誤って引き落とされてしまうことがありますので、お早めに口座振替停止の手続きを金融機関または年金事務所にて行ってください。
お問い合わせ2
日本年金機構 長崎南年金事務所(新しいウィンドウで開きます)(電話番号095-825-8705)
次のかたは希望すれば加入できます(任意加入)
- 60歳以上65歳未満(70歳までの特例あり)で年金受給のための資格期間が不足しているかた、
または過去に保険料の未納などがあり満額の老齢基礎年金を受給できないかた
※納付方法は口座振替のみ - 海外に住む日本国籍のかたで20歳以上65歳未満のかた
※納付方法は国内の協力者による納付書か口座振替 - 60歳未満で被用者年金制度(厚生年金や共済年金など)老齢(退職)年金を受給しているかた
※納付方法は口座振替のみ
窓口
各地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、
日本年金機構 長崎南年金事務所(新しいウィンドウで開きます)
必要なもの
本人確認書類、基礎年金番号通知書または年金手帳、口座振替の場合は通帳と銀行届出印
※代理人の場合は委任状が必要  委任状(PDF形式 247キロバイト)
委任状(PDF形式 247キロバイト)
(同世帯の世帯主が手続きをされる場合でも、委任状は必要です。)
お問い合わせ
住民情報課総務係(電話番号095-829-1137)
日本年金機構 長崎南年金事務所(新しいウィンドウで開きます)(電話番号095-825-8705)
保険料と納め方
国民年金の保険料は月額16,980円(令和6年度)です。
付加保険料400円を加算すれば、年金受給額が増えます。
2年分、1年分、6ヶ月分などを前納すると割引されます。
保険料や納付方法についての詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
※納付書の紛失や再発行、納付方法についてのお問い合わせは、日本年金機構 長崎南年金事務所(新しいウィンドウで開きます)へ(電話番号095-825-8705)
保険料を納めるのが困難なとき
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合、納付が免除される制度があります。
申請して、世帯構成員(被保険者、配偶者、世帯主)それぞれの所得額(収入)が
基準額内であれば、保険料の全額または一部(半額・4分の3・4分の1)が免除されます。
また、納付猶予制度(50歳未満が対象)や学生の納付特例制度もあります。
免除等の期間は年金受給の資格期間に入るので、未納のままにするより有利です。
災害により財産の約2分の1以上が損害を受けた場合も免除が受けられます(新しいウィンドウで開きます)
窓口
各地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、
日本年金機構 長崎南年金事務所
必要なもの
本人確認書類、基礎年金番号通知書または年金手帳
※代理人の場合は委任状が必要  委任状(PDF形式 247キロバイト)
委任状(PDF形式 247キロバイト)
(ただしご本人と同世帯の世帯主が手続きをされる場合、委任状は不要です。)
※失業による申請の場合は離職年月日がわかる書類
過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、
失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
雇用保険の被保険者であった方は公共職業安定所が発行する、次のいずれかの書類
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格通知
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
雇用保険の被保険者でなかった方は離職証明書
 離職証明書(PDF形式 120キロバイト)(様式を事業所に渡し、作成してもらう)
離職証明書(PDF形式 120キロバイト)(様式を事業所に渡し、作成してもらう)
雇用保険の適用対象外であった方は雇用先の国等が証明した書類(辞令書)など
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方】は次の書類
(1)総合支援資金の貸付決定通知書の写し及び申請したときの添付書類の写し
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書の写し
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(受付印のあるもの)
(4)保健所への廃止届出書(控)または廃止届証明書(受付印のあるもの)の写し
(5)その他、公的機関が交付する証明書等あって失業の事実が確認できる書類の写し
※(2)~(5)については、書類と併せて失業の状態にあることの申し立てが必要
お問い合わせ
住民情報課総務係(電話番号095-829-1137)
日本年金機構 長崎南年金事務所(電話番号095-825-8705)
次のかたは保険料が全額免除になります
次のかたは国民年金保険料が全額免除になります(法定免除)。
また、これに該当しなくなった場合も手続きが必要です。
なお、全額免除に該当した期間についての老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。
- 生活保護の生活扶助を受給されているかた
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受給されているかた
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養中のかた
窓口
各地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、
日本年金機構 長崎南年金事務所
必要なもの
本人確認書類、基礎年金番号通知書または年金手帳
生活保護:保護開始(廃止)決定通知書、長崎市福祉事務所公費負担診療依頼証(世帯主以外の届出をする場合のみ)
障害年金:年金証書
ハンセン病:日本年金機構 長崎南年金事務所へお問い合わせください。
※代理人の場合は委任状が必要  委任状(PDF形式 247キロバイト)
委任状(PDF形式 247キロバイト)
(同世帯の世帯主が手続きをされる場合でも、委任状は必要です。)
お問い合わせ
住民情報課総務係(電話番号095-829-1137)
日本年金機構 長崎南年金事務所(電話番号095-825-8705)
産前産後の免除制度
第1号被保険者が出産を行った際、その出産前後の一定期間の保険料については
納付することを要せず、当該期間は保険料納付済期間となる制度です。
※「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人口妊娠中絶を含みます。
対象者
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方。
※出産日が平成31年2月1日以降のかたが対象になります。
※任意加入しているかたは該当しません。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出可能です。
免除期間
単胎の場合は出産予定日(出生後に届出の場合は出産日)の属する月の前月から翌々月までの4か月間。
多胎の場合は出産予定日(出生後に届出の場合は出産日)の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間。
※産前産後免除期間は、保険料納付済期間とみなされます。
※産前産後免除期間中は、付加保険料を納付することができます。
※産前産後免除制度の日本年金機構HP
窓口
各地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、
日本年金機構 長崎南年金事務所
必要なもの
本人確認書類、基礎年金番号通知書または年金手帳、母子健康手帳(出産前に届出を行うかた)
※代理人の場合は委任状が必要  委任状(PDF形式 247キロバイト)
委任状(PDF形式 247キロバイト)
(同世帯の世帯主が手続きされる場合でも、委任状は必要です。)
お問い合わせ
住民情報課総務係(電話番号095-829-1137)
日本年金機構 長崎南年金事務所(電話番号095-825-8705)
公的年金シミュレータ―の開設
厚生労働省では、パソコンやスマートフォンで自分の将来の年金額を簡単に試算できるツールである「公的年金シミュレーター」を開発し、令和4年4月25日より試験運用を開始しました。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
公的年金シミュレータ―使い方ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
なお、個人の過去の加入記録に基づく、より詳細な年金の見込額の試算を希望する方は、「ねんきんネット」(新しいウィンドウで開きます)をご活用ください。試算に加え、これまでの年金記録などご自身の年金に関する情報をパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも確認できます。
年金を受給されているかた
年金は原則として、受給権を得た翌月分から受給権が消滅した月分まで支給されます。
年6回、偶数月に振り込まれます。
※下記の「市役所でお手続きできる年金の種類」以外の年金についてや年金額、
振込などについてのお問い合わせは日本年金機構長崎南年金事務所(電話番号095-825-8707)へ。
市役所でお手続きできる年金の種類
手続きに必要なものは、年金の種類ごとに異なりますのでお問い合わせください。
住民情報課総務係(電話番号095-829-1137)
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(最大40年)あるかたが、原則として65歳から受ける年金です。
障害基礎年金
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当し、
病気やけがなどで重い障害があるときに受ける年金です。
遺族基礎年金
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当するかたが亡くなったときに、
残された18才以下の子を持つ配偶者または子が受ける年金です。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格のある夫が年金を受給せず(障害年金含む)に亡くなったときに、
死亡時まで引き続き10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳までの間に受ける年金です。
死亡一時金
保険料を3年以上納めたかたが、年金を受けずに亡くなったときに遺族が受ける一時金です。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金などを受け取ることができないかたに支給される給付金です。
リンク
- 日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
- 全国国民年金基金(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
- 年金ポータル(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く