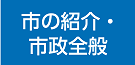ここから本文です。
平成22年度第1回 長崎市環境審議会
更新日:2013年3月1日 ページID:006557
長崎市の附属機関等について(会議録のページ)
担当所属名
環境部環境保全課
会議名
平成22年度第1回 長崎市環境審議会
- 日時:平成22年6月26日(土曜日)午前10時10分~正午
- 場所:長崎市立図書館 新興善メモリアルホール
催名
環境に関する市民意見交換会
審議結果
意見交換会内容
事務局
長崎市の環境の現状と目指す環境像について説明。(省略)
会長
質問もあるかと思うが、市民5人による意見発表がすべて終了した後に討論に入りたい。
つづいて、市民の発表に移らせていただく。
市民代表:宿町自治会長
宿町自治会と総合科学大学シーサイドキャンパスによる共同環境保全活動を通して互いの親睦並びに環境保全への共通認識を深めると共に地域活性化を目的としている。
活動内容
- 古紙回収に関する活動(・個人宅への訪問古紙回収・古紙保管書庫での分別計量作業・地域通貨の発行及び配付)
- 広報活動(・定例公園清掃活動・自治会定例会議・広報紙発行)活動成果;ゴミ分別の意識向上・地域住民と学生との友好関係・地域商店の活性化
課題と展望
1 課題
- 古紙保管庫での分別計量作業の軽減化・地域通貨の流通と繁栄
2 今後の展望
- これまでの活動内容の分析・改善を施し、より多くの理解者並びに協力者を拡大する。
- 活動範囲の拡大
環境保全活動に取り組む市民団体代表:ながさきホタルの会会長
ながさきホタルの会は、ホタルの保護観察を通して、水辺環境の保全や小さな生きものを育み、自然環境保全活動に寄与することを目的とする。
活動内容
- 官民協働によるホタル発生調査(平成12年度~)
- 小学校等への環境出前講座(川の自然環境の保全について)
- 河川の清掃美化活動(2ヶ月1回)
- 情報誌ホタルレター発行(年3回)
- 第41回全国ホタル研究大会長崎大会を長崎市で開催(平成20年6月6日~8日)
- 長崎県ホタルの会結成(平成22年1月)
- 第3回子ども自然サミット開催予定(平成23年2月5日)
活動成果
- ホタル発生調査や情報提供により、自然環境保全に対する意識の向上
- 県内ホタルネットワーク構築により、県内のホタル発生状況、イベント等の情報把握
- 過去2回の子ども自然サミット(市内8校出演)の開催により、他校の取組みにも波及効果
課題と展望
1 課題
特に子ども自然サミット等の開催には、多額の費用を要するため資金調達が難しく毎年度開催が困難となっている。
2 今後の展望
- 県内のホタルネットワークの構築により、更なる展開を拡大する。
- 子どもたちへの環境教育の観点から、子ども自然サミットの毎年度開催を目指す。
事業所代表:三菱重工業株式会社 長崎造船所 総務課長
三菱重工業では、CSR行動指針を設定し、それに基づき各種活動を実施している。
CSR活動
- 地球との絆;緑あふれる地球を環境技術と環境意識で守る。
- 社会との絆;積極的な社会参画と、誠実な行動により、社会との信頼関係を築く。
- 次世代への架け橋;夢を実現する技術で,次世代を担う人の育成に貢献する。
環境に関する取組み
- 環境にやさしい製品の提供環境に配慮した製品=エコエナジー(エコロジー+エコノミー+エネルギー)製品をお客さまへ提供することが,当社の最大のCSR活動であると位置づけている。
- 水資源の有効活用工場で発生した生活排水の再利用や井戸水・海水を活用することによって,工場の水道使用量の約6割を自給で補っている。
- 工場で発生する廃棄物のリサイクル促進工場での作業で発生する金属くずなどの廃棄物の分別を徹底し,売却や固形燃料化するなどのリサイクル促進を図っている。
- 緑のカーテンへの取組み
各工場内で自主的に緑のカーテンへ取組み,地球温暖化対策への意識を高めている。 - ノーマイカーデーの実施
マイカー通勤者へ呼びかけるなど,地域のCO2削減活動へ積極的に参加している。 - 新入社員による地域清掃活動の実施
新入社員教育の一環として,市内各所の清掃活動を実施している。
今後の課題
- ゼロエミッションの継続
当社のゼロエミッション>、埋立処分される廃棄物量を全廃棄物の2%未満に押さえること。 - 工場の省エネ化およびCO2(二酸化炭素)削減対策の促進
- 社員参加型の環境活動の実施
教育機関代表:長崎市立稲佐小学校 教頭
省エネ共和国とは?
省エネ共和国とは、地球温暖化防止のためにエネルギーを考え、省エネルギー・環境・リサイクルなどを推進する地域活動の実践を、それぞれの特性に合わせた、プランに基づいてめざす人々の集まり。財団法人省エネルギーセンターが統括。稲佐小学校は、平成15年9月に建国し今年度で8年目。
活動内容と成果:校長を大統領として、「節電省」「節水省」「食料省」「地球環境省」「リサイクル省」の5つの省がそれぞれ目標を掲げて活動している。各省には、6年生の大臣がいる。高学年の委員会活動を中心に取り組んでいる。
1 5つの省
- 節電省:全校に省エネを呼び掛け、電気の付けっぱなしをチェックしたり、使用していないコンセントを抜いたりする。
- 節水省:全校に節水を呼び掛け、水の出しっぱなしをチェックしたり、使用上の決まりを掲示したりする。
- 食料省:給食の食べ残しなどを無くすための呼びかけしたり、残した食べ物を肥料にする活動に取り組む。
- 地域環境省:学校敷地内はもちろん、隣接地区の地域のゴミ拾いをしたり、ポイ捨てを無くす呼びかけをしたりて、地域の環境を守る活動に取り組む。
- リサイクル省:5つのR(リフューズ・リデュース・リペア・リュース・リサイクル)を実践し輪を広げて行く。
2 省エネパトロール
1~6年生から毎学期、各学級5名ほど募り、主に休み時間中の節電・節水の調査を行い、無駄を無くす呼びかけをする。
3 総合的な学習(6年:環境)
課題と展望
- 課題~マンネリ化への対応
- 展望~創立130周年(建国10年目)へ向けた仕切り直し
大学生代表:長崎大学環境科学部EMS学生委員会 元代表
環境科学部の運用している環境マネジメントシステム(ISO14001に基づく)の運用を支援するとともに、学内外への環境マネジメントに関する情報発信を目的としている。
活動内容(平成19年~)
1 環境科学部における業務の補助
- ISO14001運営委員会への参画
- 事務局補助
- 内部環境監査(教職員、EMS運営委員会等に対するヒアリング)
2 学内外への情報発信
- 環境報告書発行
- 九州・山口EMS学生シンポジウム開催
活動成果
- 内部環境監査実施(原則年1回:平成18年~)
- 環境管理マニュアル改訂(通年:平成19年~)
- 環境報告書発行(年1回:平成20年)
- シンポジウム開催(年1回:平成20年~)
- 省エネシール等による学内啓発(平成21年)
課題と展望
1 課題
- 環境マネジメントに関する教職員の理解・協力があまり得られていない。
- トップダウンが働きにくい。そのため、現在事務局やEMS学生委員会に業務が集中してしまっている。
2 今後の展望
- ISO14001運営委員会を中心に環境マネジメントへ教職員うまく巻き込んでいく。そのために、研修会への参加を呼び掛け、理解者を増やしていく。
- ISO14001に基づくシステムであり、分かりにくいので、教職員にも理解しやすいシステムへと改善していく。
- 環境報告書を発行するなどして、取り組みを周知するとともに意識を高めていく。
会長
事務局から長崎市の環境の現状と目指す環境像、5名の市民の方からは意見発表があったが、何か質問はないか。
市民
稲佐小学校の方では、給食で出ている牛乳の紙パックというのは、リサイクルされているか。
教育機関代表
全学年ではなく、5・6年生が取り組んでおり、低学年・中学年は普通どおり給食室に戻しているので、ごみとして出ることはない。どの学校も他のごみと一緒に出していることはないと考える。
会長
他に質問はないか。
市民
稲佐小学校の方では、水の流れを鉛筆1本位にするというが、どんな方法で止めるのか。
教育機関代表
ポスターにして、水道を捻る時は、鉛筆1本ぐらいにしましょうと張ってある。心掛けの問題と考えている。
市民
稲佐小学校の取り組みで、現在までずっと続いているということは、本当に素晴らしいことだと考える。生ごみの処理をしている関係から、学校給食の食べ残しを土にかえすというような取り組みもしているが、残飯の中にパンがたくさんあり、開封していないパンも入っている。貴小学校には、食糧省があるが、他の学校との比較あるいはどれくらいの食べ残しがあるのか。
教育機関代表
単にエコのためということではなく、食育という観点から食に対する教育も深めていきたいと考えている。その一環として、物を大切にするとか、食べ物に感謝ししっかり食べてほしいと願っている。残量の数値的なものは、良く分からないが給食の調理員さんからは、残量が少ないと喜ばれている。他の学校との比較は分からないが、個人差があるのでクラスで協力しながら、目標を持ったり先生方の働きかけで変わってくるので、地道な取り組みが必要と考える。
会長
時間が後40分ぐらいしかないので、これから、意見交換会に入りたい。環境ということに対して、口では格好のいいことを云うが、いざ、自分達が身に立った時にどうすればいいかということが一番の課題だと思う。例えば、小学校で学んだ環境教育と家庭とのギャップ或いは学生の教員に対する不満等いろいろあるが。
市民
何かと言われれば、一つだけ目的の共有ができていない。頂上のことができていないので、教職員であれ学生であれ、手段方法論は別の次元である。逆算して、今の現状を把握しながら、そして目的を共有しながら、一つ一つステップアップしていくことだと思う。
会長
長崎市でも、「人と自然と文化が輝きつづけるまち」、これがまさしく頂上の目標で、それに向かって我々がどうするかということを、これからの基本計画でやっていかなければならない。
市民
地域にいると、どちらの話しを聞いていいのかわからないことがある。個人として何がどうできるのかについて、意識の共有というのがあったが、その通りだと思う。長崎市は、今年度は,これを頑張るんだとか、あれをするんだという指針、目標を明確に市民に打ち出してほしいと思う。
会長
ほかに、審議会の中でこうだという意見はないか。
審議会委員
今の意見に関連することでもないが、市民・行政・事業所等が何か目指す環境像が非常に分かり易くて、共有できるような、目指す方向が明確になるような、例えば、トンボが飛び交う都市、そういう小さい時に生活した生活空間の環境イメージに近いものが、環境像として詰められないかと思う。環境像を生物指標にできないかいか皆さんの意見を聞いてみたい。
会長
環境に関する理想、目標像を分かりやすくきめたらどうかとういう意見であったが、その中でも、生物指標とかあるがそれに対して意見はないか。
市民
長崎は結構、独特な生物がおり、長崎の名前がついた植物もいる。長崎は海に囲まれているが、案外、海辺の生物を知らない。身近な生き物を知って、それに親しんでいくということが一つの環境を守る方法でもある。
会長
長崎独特の生き物を旨くPRしていくことも必要だと思うが、他に意見はないか。
市民
今、豊かな暮らしを望んで贅沢をしているのではないかと考えられるので、それに対応するには、節約が一番大切だと思う。節約する日でもいいし、毎日節約を続けていけば、環境は元の状態に戻ると思う。
会長
確かに、そうだと思うが、中々それが難しいんですよね。
審議会委員
人間というのは、一端そのところまでいったら、中々それを削っていくというのは、一人では、なかなか実行できないので、もし、今の日本がエネルギーを本当に削減しようと思えば、極端ではあるが、消灯時間を決めて取り組むぐらいの危機感をもって取り組む方法しかないと思う。
審議会委員
どっぷり使った生活から、シンプルな生活に変えていこうという意識の向上が大事であると思う。我々は、これから、どのような生活スタイルをやっていけばいいかというと、行政・企業・住民がそれぞれの立場で義務を果たしていくことが大事であると考える。
会長
節約というのは、大事なことで数字を上げてやると非常に分かりやすいこともある。もうひとつ、CSR、EMSとか単語がどんどん飛び交っているが、市の広報紙等でもう少し、詳しく説明した方がいいか。やさしい言葉とか要望・意見はないか。
市民
専門的というか、例えば、COP10、1990年(平成2年)比25%削減などと云われるが、市民としてあまりにも、抽象的し過ぎて実感がわかない。
市民
数字として出すのは、非常にいいことだと思う。何からやっていいのかわからない、具体的にああだ、こうだといわれるが、2者択一だとか、そういうふうな思いではなくて、できるだけ今の生活のより負荷の小さいものの取り組みをやったらどうか。
市民
昔の時代に戻れということが云われるが、快適な生活、楽しく暮らせる生活を維持しつつ、子供たちにもケチケチするのではなく、とにかく無駄をなくし、それと物を大切にする心掛けが必要で、昔の生活に戻るということではないと思う。
会長
省エネの削減が進んでいるのは、企業、業界で民生は進んでいない。私たちの生活が、やはり、おごってしまっている。この便利な生活を昔に戻れということはできないので、生活のレベルを落とすのではなく、生活のパターンを変えることを考えないといけない時代になっていると思う。
審議会委員
昔に戻るのではない話しは、要は、統制をする、規制をする、自主的にやるというのを区別しなければならないということで、今、求められていることは、自由を確保することは必要であるが、その中で何をどのように規制するかということで、合意する必要があるレベルとういうことである。そのためには、目標をどうするのかが重要であり、1950年代(昭和25年代)から60年代(昭和35年代)の生活レベルに戻ると、エネルギー的には、今の生活で節約するということでは、とても間に合わず石油に頼っているのではなく、自然エネルギーなり代替エネルギーを生活の知恵の中で探してみないといけないと思う。規制に対しては、長崎市が目標を市民の方と共有して示し、それに対してどのようにシステムを動かせば、その目標を達成できるのかという計画を作らなければならないと思う。
会長
ほかに意見はないか。
市民
現在の環境基本計画をどう実行したのかということが、次のステップの計画と考えるので、課題検証を行い公表するとともに、市民中心に意見を聞いて、次の計画の中に長崎市がやらなければならないことをしっかり明示していただきたい。
会長
以上で意見交換会を終了する。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く