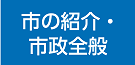ここから本文です。
平成26年度第5回 長崎市建築審査会
更新日:2015年3月2日 ページID:026598
長崎市の附属機関等について(会議録のページ)
担当所属名
建築部建築指導課
会議名
平成26年度第5回 長崎市建築審査会
日時
平成26年11月20日(木曜日) 13時30分~
場所
長崎市男女共同参画推進センターアマランス 第1会議室
議題
<第8号議案>
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可について
<第9号議案>
建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の報告
(平成26年9月1日から平成26年10月31日まで)
<第10号議案>
建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の報告
(平成26年9月1日から平成26年10月31日まで)
審議結果
<第8号議案> -審議結果- 同意する
【会長】
議案書39ページの日影規制に係る建築許可の運用基準審査表の中の(6)「周辺の居住環境」の欄に、“土地の状況等により、周囲の居住環境を害する恐れがない場合”とあり、これが今回の許可のための判断の根拠となっているようである。この申請書の中で(1)~(5)の項目では敷地全体のことを述べているのに対し、(6)だけ増築部分のみのところを述べているように見える。(6)も敷地全体で捉えるべきではないか。
【事務局】
日影算定の規定の中では、敷地全体で全ての棟を複合した日影を算定するものである。議案書22ページの計画日影図にあるように、建築基準法上不適格な日影を落とす既存建築物(体育館と武道場)の日影が現実に変化するのではなく、全ての棟を複合した日影を作図するために、今回の増築によって平均地盤面が下がり、理論上の日影が伸びる。このように日影算定の規定の中で既存建築物の理論上の日影は伸びるが、実際に変化する建築物は今回の計画の増築棟のみであり、増築棟の日影は周辺の居住環境に影響を及ぼさない。よって、(6)の部分は敷地全体で捉えた時の判断根拠となる。
【会長】
現実の日影が伸びなくても、建築基準法の適切な運用上では日影図が伸びているのが事実である。この書き振り(議案書40ページ、“申請敷地周辺に及ぼしている実際の日影が、今回の増築棟による日影の影響を受けない”)では誤解を与えるので、あくまでも日影が変化した度合が大きくないので居住環境を害する恐れがない、と明記するべきではないか。
【委員】
A部分は建築基準法を満足しているが、許可基準(5)-(イ)“基準時に日影が不適格となっている場所に、新たな日影が生じず、かつ、不適合な日影を増加させない”を満たしていない。B部分は今回の増築では日影はそこまで伸びていないが、許可基準(5)-(ロ)“隣地境界線から水平距離5mを超える範囲に、建築基準法第56条の2第1項に規定される”水平距離10mを超える範囲における日影時間の限度から30分を減じた時間以上の日影を生じさせない”を満たしていない。イもロもクリアしていないから(5)では許可することができないため、(6)に該当するかどうかを検討した、という認識でよいか。
【事務局】
その通りである。
【会長】
居住環境は、そこに住む人々が判断するものであり、我々審査会が勝手に“害する恐れがない”と断言し、(6)に該当すると判断する根拠はどこにあるのか。過去のそれぞれの許可のときはその判断が出来たかもしれないが、時代によって居住環境の捉え方は変化するものである。
【事務局】
(6)の“恐れがない”という文言を“恐れが少ない”という文言に変えることは検討の余地がある。
【事務局】
今回の建築物は昭和54年から何度か許可を取っている。過去の記録では隣接地からの苦情はないので影響は少ないと言えるのではないか。また、実際の日影が伸びないということからも影響が少ないといえる。
【委員】
問題点はB部分でなくA部分ではないか。B部分は既存建築物の日影が理論上伸びるものであるが、A部分の日影は増築棟の日影であり、直下に住居がある。A部分の日影が、許可基準を満たしていないが、建築基準法には適合している、という事は把握できたが、この日影が落ちる部分の住民からの苦情等は出されていないのか。
【事務局】
確かに、増築棟の日影は西側に伸びるのでA部分に影響がある。しかし、もともと更地のところに建てば問題があるかもしれないが、現在と同じ6階建ての建築物が建つ分には問題はないと考える。
【会長】
A部分の日影は建築基準法を満たしているようだが、前回までの許可でも満たしていたのか。
【事務局】
A部分は前回までの許可でも建築基準法を満たしている。B部分は今回の計画でも、前回までの許可でも建築基準法を満たしていない。
【会長】
日影の問題は隣接する敷地の財産権にも関わってくるため、慎重な議論が必要である。
現時点でまとめると、A部分は今回の増築によって日影は大きく変わるが建築基準法を満たしており、B部分は許可基準を満たしていないので、許可基準の(6)で判断したということである。
(6)の“恐れがない”という部分の判断はとても難しく、時代や状況に応じて日影に対する居住者の判断は変化するので、居住者の意思の確認が必要ではないか。前回までの許可の際に、当時(6)で判断した根拠がもし残っていないのであれば、許可の判断の妥当性が無いのではないか。例えば、類似の事例で居住環境を害する恐れのある人々に説明することはあるのか。
【事務局】
他の許可(建築基準法第48条)のときに意思を確認することはある。また、建て替えの際に長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例に基づいて事前説明の責任はあるが、時系列的には今回の許可が下りてから長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例の届出となるため、許可の判断の根拠とすることはできない。
【事務局】
今回のような日影の許可の場合、高さが決まっており、客観的に検証することができるので、今回出している書類を判断の根拠とするのが妥当ではないか。
【委員】
平均地盤面が下がったことによって理論上の日影が伸びたということだが、もし平均地盤面が変化しなければA部分やB部分で日影は現状より伸びるのか。
【事務局】
建物の配置や形状にもよるので一概に言えないが、大まかに同じものが建つと考えると大きな変化はないと考えられる。
【委員】
あまり日影が伸びないというのであれば、差し支えないと考える。
【会長】
影が伸びる部分の居住者に事前説明が必要であると考えるが、行政手続上それが難しいのであれば、現況と増築後の変化の度合いで居住環境の変化について判断するしかないと思う。B部分の日影はわずかな幅でしか動いていないように見えるが、どの程度のものなのか。
【事務局】
30cmも無い。
【会長】
その程度の幅しか日影が伸びず、しかもそれは理論上の値であり、決定的に居住環境に大きな影響はないと考えていいのか。
【委員】
B部分は元々許可基準を超えているが、その日影が落ちる部分が公共施設である学校の敷地だから数cm日影が伸びても影響がない、というのは理解できる。A部分の日影は建築基準法上問題無いが、もし万が一、A部分の日影が落ちる箇所の居住者が日影権を主張するようなことがあった場合、B部分が基準を超えているにも関わらず許可した判断の根拠を求められる可能性がある。事前情報として、A部分で日影等に関するトラブルがあるのかどうかを知りたい。B部分については“恐れがない”といえるが、A部分はそうではない時もある。
【会長】
判断根拠としては、1.日影の動き方がそれほど大きくなく、それも理論上の値である、2.多少日影は変化するが、B部分が不適合な日影を落とすのは公共施設であり、A部分は反対を受ける恐れが少ない環境である、という2点があると思われる。
【事務局】
A部分の日影は住居環境に影響を及ぼすと考えられるが、建築基準法上は問題ない。本来、A部分は通常確認申請の際の建築基準法の基準は満たしているが、B部分が建築基準法違反のため、長崎市の許可基準でみると、今度はA部分が許可基準を満たしていないことになる。許可は不適合な部分(B)に対して示されているものであり、そもそも問題なのはB部分である。
【会長】
先ほど述べた2点から今回の許可に同意して良いのではないかと考える。異議があるか。
【委員】
異議無し。
【会長】
ただし、法律は時代を反映するものである。この許可基準は日影について厳しく叫ばれていた時代の物であり、“居住環境を害する恐れがない”と明記されているが、本来であればそれを我々の勝手な判断で言い切ることは出来ないため、“恐れが少ない”と書くべきものである。また、どうやって“恐れが少ない”かどうかを判断するか、その手続きの明文化が必要である。
<第9号議案> -報告結果- 反対意見なし
【委員】
淵町バス停の標識が歩道の真中にあるが、これは問題ないのか。
【事務局】
標識を含めても歩道部分が有効幅員2mは取れているが、動かせるものなのかどうかを確認する。
【会長】
後ろの電柱も歩道の中に入っている。この標識の部分までしか歩道が無かったものが拡幅されたことにより、標識や電柱が歩道の真中に残っているのではないか。
【事務局】
その通りである。
【会長】
他に意見はないか。
【委員】
異議なし。
<第10号議案> -報告結果- 反対意見なし
【会長】
意見は無いか。
【委員】
異議なし。
―以上―
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く