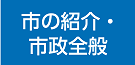ここから本文です。
長崎市総合計画審議会第4部会(地域経済と地域経営)第3回会議
更新日:2015年12月2日 ページID:027815
長崎市の附属機関について(会議録のページ)
担当所属名
企画財政部 都市経営室
会議名
長崎市総合計画審議会 第4部会(地域経済と地域経営)第3回会議
日時
平成27年8月6日(木曜日) 10時00分~12時16分
場所
長崎市役所本館 地下1階議会第4会議室
議題
1. 基本施策C2「域外経済への進出を加速します」の評価
2. 基本施策C4「地域内の経済循環を促します」の評価
審議結果
■議題1 C2「域外経済への進出を加速します」
〔基本施策主管課 説明〕
【委員】
C2-2の成果指標「海外展示会に出展した事業者数の割合」が平成23年度の実績から、それ以降極端に下がっているが、要因は何か。
【担当課】
市補助金は国内・海外双方の展示会を対象にしているが、海外展示会の実績が下がった要因は、中国・韓国などの国際情勢の影響だと考える。
【委員】
お土産品コンテストは、今後も継続していく方針か。
【担当課】
地方創生に係る国からの交付金を活用して今年度実施するものであるため、継続については効果をみて検討したい。
【委員】
お土産品コンテストへの応募は、アイデアレベルでよいのか。それとも製品を出さないといけないものか。
【担当課】
商品を写真に撮って応募する必要があるため、販売はしていなくても結構だが、モノは必要になる。
【委員】
よいアイデアをもっていても、製造できない人もいるかもしれない。アイデア部門を設定して実施してはどうか。例えば、軍艦島の形のかまぼこの商品化というアイデアがあっても、事業者とコラボできればよいが、素人にかまぼこはつくれない。
【担当課】
今後の参考にしたい。
【委員】
県の長崎俵物の取組みは、土産品として育てようとしたが、認定後の販売場所が乏しく、経済効果に結びつかなかった。今回のコンテストも、特典が弱いように思う。「受賞すれば売れる」というサクセスストーリーを設定しないと成功は厳しいと思う。例えば、ふるさと納税のリストに入れるなどが考えられる。
【担当課】
確かに、流通までが大事である。コンテスト後のフォローとして、販売までつなげられるよう検討し、商品の拡充を図りたい。
【部会長】
「長崎らしい商品」とは何か。
他でやっていないことをPRするのが差別化であり、それがブランド化につながるのではないか。何かで1位になっただけでは不足する。「長崎らしさ」を強調する手法を、市も事業者も検討すべきである。
【委員】
零細企業は商談会などには参加できないため、ふるさと納税のリストに載ることはチャンスである。
また、商談会では値段交渉されるが、クルーズ船の観光客は財布のひももゆるく、誰にでもチャンスがあると思う。
【担当課】
情報発信という面では、域外だけではなく、クルーズ船などへも積極的に行いたい。また、事業者に寄り添った支援となるよう検討したい。
【部会長】
現場感覚をどうスピーディに市の施策や取組みに活かせるかが重要である。
【委員】
評価が「Dc」となっている要因として、キトラスがあるのではないか。キトラス事業により、ノウハウは得られたはずであるから、その検証を次にどう活かすかが大事である。
【部会長】
キトラス事業では3億円以上の経済効果があった。販売の場所があることが、事業者にとってはプラスであったと思う。ただ、キトラスから百貨店での販売までにつなげる部分の取組みが弱かったのも事実である。検証結果を踏まえ、長崎らしさの付加価値をつけていくような取組みを来年度からは展開したい。
【部会長】
キトラスでは、どのような陳列状況のときに、どの年代が何をどのくらい購入したのか、というようなデータ分析できるまでの詳細なデータが十分残ってはいないのが残念である。
【委員】
3市で運営していたことがキトラスを難しくした要因だった。自社の分は偶数月しか販売できず、後の月は他市の事業者が販売をするという形態であったため、商品がなくなったという問い合わせもあった。正直、スペースが不足していたと思う。キトラスから首都圏販売につながると信じていたが残念。ノウハウを活かして、市単独での展開も検討してほしい。
【委員】
「長崎かんぼこ王国」の取組みは、全国から先進事例として問い合わせがある。材料費の高騰などつらい部分もあるが、かまぼこ業界としては何とかくい止めている状況。今年、商業高校とコラボしてかまぼこをつくるなど、話題性は十分あると思っている。市にも大いに協力していただいている。
【委員】
東京のスーパーマーケット・トレードショーには、これまで大手しか参加していなかったが、今では零細企業も参加し、1件でも新規を獲得すればやる気につながっている。「こだわりの少し」を探しているバイヤーもおり、少しずつ成果は出てきていると感じている。引き続き支援をお願いしたい。
【委員】
「長崎かんぼこ王国」の取組みが進んでいるなら、それをもっとPRすべき。売上データだけをみると遅れていると感じていた。行政と事業者と地域がより連携して、その部分はPRしてよいのではないか。
【委員】
「長崎かんぼこ王国」の売上目標120億円は、かなり厳しい数字である。ちゃポリタンや長崎おでんは頑張っているが、全国的な傾向として板付けかまぼこが食べられなくなっている。原料高もあり、くい止めるので精一杯なのが現状だが、120億円は諦めてはいない。
【委員】
ふるさと納税がなぜ重要かというと、そこに他との違いを書けるからである。長崎をPRする一つの起爆剤になり得るので、頑張ってほしい。
【担当課】
土産品開発や個別アドバイス会などにおいても、魅力を伝えきれていないという指摘を多くの事業者からいただいた。差別化の部分をPRするというのはあるが、どのような手法が最も効果的な手法であるか、難しいと感じている。
【委員】
アンテナショップで試食してもらい、ふるさと納税のカタログ代わりにする方法もある。
【部会長】
おそらく現状では、「伝えきれていない」ではなく「伝えていない」というレベルではないか。この場で様々なアイデアが出ているように、アドバイスは外の人に求めるべきである。
【委員】
長崎浜屋で、よく北海道物産展等が開催されているが、長崎も同様にどこかに出展しているのか。
【部会長】
大阪や福岡などのフェアに出展している。
【委員】
毎年、定例で出展しているものか。長崎での北海道物産展のように定着するには、戦略をもってやる必要があると思う。
【担当課】
県単位で実施しているもので、市は負担金を支出している。
【委員】
どこかの店舗や事業者のところにバイヤーが来ていれば、その情報を得て他の事業者が出向いていくような、情報のネットワークは長崎ではある程度できてきている。
【部会長】
物産展については、目的は売上だけでなく、そこでのチラシ配布など、宣伝費用だと思うことが大事である。その場でどれだけPRできるかが重要。市としては、例えばそこに専門家を手配することを支援するなど検討してはどうか。販売とともに、情報発信拠点として捉えることである。
【委員】
ふるさと納税には、長崎では旅行パックを設定するのがよいと思う。
【担当課】
検討中である。
【部会長】
スピーディに対応することが肝心である。
【委員】
C2及びC2-2の成果指標で、長崎港の定期コンテナ貨物の取扱量は増加しているが、アジア貿易額はそこまで増加していない。どのような関係性か。
【担当課】
取扱量の輸入と輸出の割合はおよそ8:2であり、輸入は欧米からの取扱量が増加している。
【委員】
指標として一方はアジアに限定し、一方は欧米も含んでおりそれが増加していることで、量と額とで矛盾が生じているように見える。施策としては、「域外への進出を加速します」であるため、C2の中の指標としては整合性をとるべき。
【委員】
コンテストでは、商工会議所青年部や青年会議所など民間を入れて、地域ぐるみで選考すべき。そうすれば、選考の重みや発信力も増す。場合によっては、よいものがなければ出さない、というぐらいの姿勢でやって、選出したものは柱として重点的にPRしていかないと重みをもたない。
「他に簡単に真似ができない」ことが差別化であり、この観点から考えないと差別化は図られない。例えば、長崎の歴史は絶対に真似ができないものであり、そこからアプローチするなども考えられる。
【担当課】
企画段階で関係機関との連携がもっとあってもよかったかと思うが、今回のコンテストでは、観光客に試食などで選考していただくようにしている。
【委員】
そのようなことではなく、重要なのは様々な方がコラボレートすること。ちゃポリタンも、かまぼこ業界だけでは成功しなかった。カゴメや麺業界とコラボしたからこそ成功した。それにより発信力がものすごくあがった。
【部会長】
「域外等へ独自の販売ルートを持たない中小企業」や「零細事業者が多いため、営業力が弱く、自ら商談の機会を持つことが困難」という記載がある中で、「長崎港から長崎カステラ10,000本を輸出」した事業者は零細ではなかったのか。
【担当課】
問題点等の箇所の表記については、全体的な傾向として記載している。
【部会長】
カステラの輸出に成功した事業者は、様々な場に見学に出向いていたり、コンテストに出場したりして、常にアンテナをはっていた。そのような方はチャンスをつかみやすい。要は、そのような方を市内にどれだけ増やすかだと思う。
【部会長】
成功事例は市内にたくさんある。それをヒアリングし、了解を得たうえで、チラシ等に掲載することも情報を広げる手法である。
必ず事業者も巻き込み、オール長崎で取り組むことが必要である。いかにトップのほうで議論をしても、それを事業者が取り組まなければ意味をなさない。
【委員】
事業者として韓国に魅力を感じないのだが、なぜ輸出において韓国に限定するのか。
【担当課】
限定しているわけではない。香港、中国、台湾などもある。韓国には釜山事務所もあり、ネットワークがあったため、今はそのような結果になっているということである。
【部会長】
意欲やアイデアのある市内の社長たちに集まってもらい、今後の方向性の議論などするとよいのではないか。
【委員】
複数の外国語のポップを貼るのもよい手法だと思う。例えば、ハトシの説明でも、複数言語の説明をホームページに掲載し、自由に使用できるようにしてはどうか。
【担当課】
年1回、インバウンドセミナーでポップの書き方の講座を実施している。
【委員】
そのようなものもホームページに掲載して活用してほしい。
【委員】
ポップの場合は、そこに日本語表記も入れておくとよい。形で覚えて、日本語表記だけの場合でも、それとわかる場合がある。
【部会長】
商業の分野に限ったことではないが、市だけで取り組むのではなく、必ず事業者を巻き込みながら進めていくことが必要である。評価は「Dc」であるが、事業者を巻き込むという点においては、より「Dd」に近いものであると感じているため、その点取組みを進めてほしい。
〔評価「Dc」について了承〕
■議題2 C4「地域内の経済循環を促します」
〔基本施策主管課 説明〕
【委員】
C4-2の今後の取組方針欄に「長崎かんぼこ王国」の取組みの記載があるが、補助金の検討も行ってほしい。
【担当課】
次につながるような他の業界の育成にも取り組みたい。補助金については、他の機関との連携の中で対応が図られるよう取り組みたい。
【委員】
市は担当者が変わっていく中で、思いが薄れてきている。市はナビゲートの役割を担っているという意識をもってほしい。体制を再度見直すべき。
【委員】
トイレの位置などインフラから取り組む動きもあるため、ビッグデータの活用を浸透させてほしい。全庁的な活用の方向性の統一に関し検討すべき。
【担当課】
商店街とも連携し、活用していきたい。
【委員】
活発でない商店街にはどのように対応しているのか。
【担当課】
講師派遣のマネジメント事業を行っている。また、他の商店街の取組事例を紹介する取組みも行っており、意欲の向上につなげたい。
【委員】
琴海の直売所では、ランタン期間中にランタンを飾り雰囲気づくりを行ったが、次回は催しもあわせてできればと考えている。地域のコミュニティを考えると、コンビニやドラッグストア等がある中で、やはり直売所がコミュニティの役割を担うような取組みを行いたい。施策の対象として、周辺地域は市中心部の次になるのは仕方ないのかもしれないが、何か取組みの活力になるようなものを提供していただきたい。情報提供も積極的に行っていただきたい。
【担当課】
琴海の四季彩館は活発に活動されている。地域おこし、まちおこしにもつなげられるよう連携したい。
【委員】
プレミアム商品券でも、当初は周知不足で売れなかったが、プレミアム付きという情報が広まると買い手が押しよせ、そこのギャップに苦情もあった。市中心部とでは商店街にも差があるため、更に積極的にPR方法等についても支援やアドバイスが必要だったのではないか。
【担当課】
プレミアム商品券については、商店街独自で折込広告などしていた。長崎は他県に比べ実施が早かったことも影響したかもしれない。
【委員】
まちづくりと域内の経済循環は関連するため、長崎サミットでも域内の経済循環は大事だと考えられている。例えば、域外にお金が出て行かない地域カードの仕組みも検討してはどうか。マクロの視点も頭に置きながら、域内経済のことを考えていただきたい。
【担当課】
検討したい。
【部会長】
長崎サミットには、商業振興課やまちぶらプロジェクトの所管課など、域内経済に関連する部局は積極的に入っていって話を聞いたほうがよい。
【委員】
平和町商店街のプロジェクトは、最後は金銭面の問題に直面し、難しかった。
【担当課】
頑張って成功してほしいと思っている。専門家が必要などあれば、支援したい。
【委員】
平和町には外国人が多いが、ただ外国人観光客は何も買って行かない。観光客向けの施設が何かあってもよいのかもしれない。観光客の動線に休憩所などのスポットが足りない。空き店舗等を利用してそのような場所を設けてはどうか。
【部会長】
評価については、「遅れている」となっているが、賑わいのある商店街もあるように感じられるため、引き続き連携を強め、必要な支援も講じながら取り組んでほしい。
〔評価「Cd」について了承〕
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く