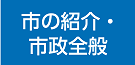ここから本文です。
平成27年度第2回長崎市水産振興計画審議会
更新日:2016年6月15日 ページID:028556
長崎市の附属機関等について(会議録のページ)
担当所属名
水産農林部水産振興課
会議名
平成27年度2回長崎市水産振興計画審議会
日時
平成27年9月25日(金曜日) 10時00分~11時55分
場所
長崎市役所 本館5階 大会議室
議題
(1)第3次水産振興計画の体系について
(2)その他
審議結果
1 会長挨拶
2 委員紹介
3 審議会の成立確認
4 議事
(1) 第3次水産振興計画の体系について
前回会議(ワークショップ)での意見の取りまとめ結果の報告後、体系案の説明、意見聴取。
【主な質疑応答、意見】
【A委員】
植物プランクトンや動物プランクトンが増えないと魚は増えない。魚が育つ環境ではないのではないか。海がきれいすぎる。海岸がコンクリートで固められて栄養分が海に入っていかないなど、基本的な事を考えないと種苗放流を行っても効果がないのではないか。
【事務局】
1)-2-1.に漁場環境の保全・再生の項目があり、計画的・総合的な藻場の再生、漁場の海底環境の改善の取り組みにより、藻場の再生、漁場環境の改善を図っていきたいと考えている。
【B委員】
第2次長崎市水産振興計画の中でも協業化・複合化の推進とあったが、具体的成果や取組みはあるのか。
【C委員】
前回の計画では、戸石でのカキ養殖と底曳業者との兼業の事例と、野母崎で底曳業者が定置を協業化して実施した事例がある。
諫早湾を閉め切った影響がかなりあり、橘湾の底曳の水揚が相当落ち込み、底曳がカキ養殖を兼業でやったらどうかということで実施したところ、今のような戸石のカキ養殖が浸透していった。戸石では、底曳業者が兼業という形でカキ養殖を実施している。
野母崎も同じように底曳業者であるが、水揚げがどんどん落ちた時期があり、定置網を4者の底曳業者で実施し、もう6年目くらいになる。正月から7月までは定置、7月から12月までは底曳と、時期を分けて定置は協業で実施している。多かったり少なかったりがあるが、順調に経営は続けられている。
【C委員】
個々の漁業の体制づくりをどのように展開するのかということについては、浜プランにかかっている。未策定地域があり、策定は難しい状況であると思うが、このプランを漁業の振興の柱としなければ、なかなか取り組めない。
協業化・複合化については、実際に6~7年前に野母崎や戸石で取り組み、いいとわかっていてもなかなかできない。漁業は農業と違い独立であり、全員が社長である。協業化や複合化は頭から誰もしようとしないため、やろうという意志と、リーダーシップが必要である。
しかし、今の単独の漁業者がいろいろなことをやろうとしても、力がない・体制がない・お金がないため、単独ではできない。そのような中で、漁業振興を図る体制のひとつとして協業化等を考えて、やれないことをどうしたらやれるのか、やらないことをどうしたらやろうとするのかを考えてやっていかなければ。口で言うのは簡単だが、実際にやろうとすると相当難しいし、やって失敗することが多いので、ここで載せるからにはそれだけの覚悟をしたうえで臨んでいただきたいと思う。
【事務局】
我々も浜プランを最重要部分としてやっていかなければ、今からの水産業は非常に厳しいものがあると思っている。自分たちのところは自分たちで計画するということが重要である。計画の中で、自分たちだけでは難しい部分については、国・県・市も協力するような体制をとっていきたい。
【B委員】
行政は情報共有を会議して意見交換できれば良いと考えがちだが、参加する業界の人達にとっても何かメリットがなければ続かないし、形だけになる。いろんな業界の方に話を聞くことをぜひやってほしい。また、同じ加工業者でもポジションによっては、メリットがある場合とデメリットがある場合が考えられるので、具体的にイメージしなければ文字だけになってしまう。
【D委員】
長崎で小売できる商品が少なくなっている。地元でブランド魚を含め魚の取り扱いが中途半端になっている。他所から来られるコンサルタント会社の方からは、他所では長崎の魚に対するお客様の信頼が高いが、長崎では特に何もせず販売されているため、もっと具体的にしっかりとした商品の売り方が必要と言われる。
【E委員】
生産者側としては、1つの考え方として6次産業化があるが、加工業者と一緒になって加工の取組みを進めていければという願いをもっている。その際に、加工業者の紹介も考えて取組みを進めてもらえれば、販路も広がるため検討いただきたい。
(2) その他
第3次水産振興計画における重点プロジェクト(案)を説明、意見聴取。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く