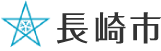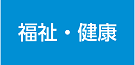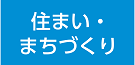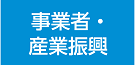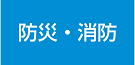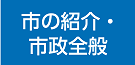ここから本文です。
第9回(平成29年度第1回)長崎市原子爆弾放射線影響研究会
更新日:2019年2月7日 ページID:032392
長崎市の附属機関について(会議録のページ)
担当所属名
原爆被爆対策部調査課
会議名
第9回(平成29年度第1回) 長崎市原子爆弾放射線影響研究会
日時
平成30年3月30日(金曜日) 14時00分~16時00分
場所
長崎原爆資料館 2階 平和学習室
議題
1 爆心地近くで被ばくした被ばく者の子孫における新規一塩基変化(新規突然変異)の検出について
2 第8回研究会までの中間経過報告について
3 子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題について
審議内容
開会
審議事項
1 爆心地近くで被ばくした被ばく者の子孫における新規一塩基変化(新規突然変異)の検出について
【A参考人】
私は人類遺伝学、DNAの研究をずっと行っており、その方面から見た被ばくの影響というのを考えて見ようということで、研究を行った。この研究が、3月の日本人類伝学会の雑誌に掲載された。
被ばく二世の新規一塩基変化についてである。ここに突然変異という言葉も出てくる。変異と言うと驚くが、変化と変異は同じ意味である。変異と言うと、研究者の方でも病気にすぐなると考えがちだが、それは全く関係がない。変化が起こったか起こっていないかということを調べた。
まず論文の結論として、今まで被ばくの影響として白血病や固形腫瘍が増えると言われてきているが、二世の人、遺伝という言葉は難しいところがあり、父から子、子から孫というように世代を超えて影響するかということを調べた。遺伝子への影響、本人のDNAへの影響はあるというのは、おそらく間違いないとことだと思っているが、それが子供にどう伝わるかということを、今回調べた。一塩基変化の数を、二世のお子さんにその変化が増えているかを数えたが、増えていないということが出た。解析数が3組の親子なので、数は少ないが、一応、変化はあまりないという結論になっている。
どうしてこういうことを考えたかということを、研究者の方々にも少し分かりづらいところがあるので、少し説明をさせていただく。DNAの方から見ると、放射線の影響はすごく捉えにくいものである。これは、被ばくによってDNAが傷付く際にどのように傷が付くかというと、細胞ごとに違う。それを検出する、検査する際に、ほぼほぼ見つけられないということになる。今まで見つけられないということだったが、どうやれば検出できるようなシステムになるかということを考えた。
総論的になるが、どんな病気が出るか、どんな風に外から見える特徴が変わるかということを見るということが一つの方法である。それは、言ってみれば疫学の調査ということになる。白血病がどれぐらい増えたかなど、そういう調査をする。がん発症と書いてあるが、がん発症が集団でどれぐらい増えたかということを計測するという方法がある。
もう一つは、インヘリテッド(※1)である。親から子へどのような影響が伝わったかというのは、先天異常、先天性の疾患がどれぐらい増えるかということで計測するという方法も考えられる。ただこれは、この資料にも書いてあるが、先天性の異常というのはものすごく少ない。少ないうえに、少ないけれども数は多い。それを計算してみても、観察対象と言うか、二世の方々の数がそれほど多くないということになる。そのため、先天異常の頻度が増えるかどうかは、計測しづらい。よって、表現型から見るということは、なかなか難しいだろうと考えた。
人類遺伝学ということで、私はこれまでDNAの研究を行ってきたけれども、DNAの損傷はどのようにしたら検出できるかということを考えた。そうすると、先ほども申し上げたとおり、DNAの損傷の具合が細胞ごとに違うため、一つ可能性があるのは、一つの細胞を取ってきて、どのような変化が起きるかというのを調べれば分かるが、人の身体には60兆個の細胞があるので、どの細胞を取るかというのは問題である。ただし、この方法では身体の外に細胞を取り出して、培養する必要がある。その際に変異することがある。培養する際に、人工的な変異が入る。そのため、放射線により入った傷か、途中の細胞培養やDNAを増やすといった作業の結果、増えたDNA損傷かの区別ができない。
そのため、人類遺伝学、DNAの方から見ると、被ばくした本人の解析をするのは結構難しいと考えている。細胞を一個分けないと解析ができないということで、どのように細胞を一個分けるかということになると、子供を解析すれば細胞一個を解析したことになる。元々は、二世の方を解析するということが最初の目的ではなく、どうすれば起こったDNAの損傷を検出できるかということを考えていった時に、二世の方の細胞を調べれば、損傷が分かるという結論に達した。子供は、父親から一つの細胞を受け取り、母親から一つの細胞を受け取る。そのため、完全にクローンという呼び方は少し違うけれども、父親の一つの細胞と母親の一つの細胞から成り立って、そのまま自然に増えていく。人工的な増殖をさせないということなので、もしDNAの損傷が伝わっていれば、ここで見ることができると、二世の方を解析すればDNAの損傷が分かると考えて解析をスタートしている。
今、遺伝的影響と申し上げたが、遺伝的影響というのは親から子に伝わることを一般的に遺伝的影響と言っている。日本語で言うと少し混乱するが、必ず伝わるということを遺伝的影響と言う。遺伝子への影響というのとは全く意味が違うため、そこが少し混乱するところではある。この伝わるところの影響を調べた。モデル動物では、放射線による遺伝的影響があると示されている。それは、まずDNAに傷が付く。被ばくした人である。その際には、細胞の様々なところに損傷が入る。もちろん、精子にも卵子にも損傷が入る。それが、子供に伝わる、影響するというのは、動物実験では知られている。しかし、被ばく二世の調査では、今のところはそういう影響はないだろうと言われていると理解している。細胞が一つ一つの損傷の部位により違うのかということを説明する。
これが、被ばくした人の細胞である。約60兆個ある。45から60兆個あると言われている。これに放射線が当たり、DNAが損傷する。これは、60兆個あるうちの1個である。これは全く計測不可能である。DNA損傷が全て違う。これに、運悪くがん遺伝子やがんの抑制遺伝子に変異が、変化が入って、がんになった途端に、それはクローンである。この1個の細胞から増えたものなので、解析が可能である。ここのがんの解析をすることは、たくさん研究されているけれども、ここを調べたいというのが第一のインタレストというか興味である。この1個の細胞がもし精子や卵子であれば、これが受精して、父と母からもらった二つの遺伝子があるので、一つは傷が付いたもの、もう一つは傷が付いていないものというのが検出できるというのが最初の出発点である。二世の方の解析を目標にしたと言うよりは、どのようにすれば放射線からの影響が定量的に見られるかということを考えて、研究を始めたということがスタートになる。
今回の研究の一塩基変化だが、一塩基変化というのはDNAの塩基の配列があるが、ACGTという文字の並び、それがどのように変わったかということになる。今まで、染色体異常というのは大きなくくり、DNAがコンパクトになって細胞の中に入っているわけだが、大きなくくりで染色体の異常がどうなっているかを見ていた。今回は、DNAのところ、一番小さな単位のところで見ていった。
DNAの変化だが、どのような変化があるかということと、どれが見つけられるか、見ることができるかということを考えると、ゲノムDNAの変化がどのようなものがあるかということを区別すると、小さいところから言うと、一塩基、ACGTの文字がどのように変化したかという一番小さなくくりから、欠失・重複・挿入と資料に書いてあるが、まとまった分、何十文字、何千文字や何万文字が一気になくなるなど、そういうことを解析することも可能である。そして、最後に一番大きな染色体。染色体のくくりとしてなくなったり、多くなったりというところ、小さいところから大きなところまで見る範囲というか、何を見るかで区別できる。今回見たのは、この一番小さなDNAの損傷というところを見た。
これを分かりやすく説明すると、ACGTの文字の並びがあるが、例えば異常がない人はGとCが向かい合ってある。もし何かあって、例えば病気の方などを調べると、時々、元はGAと向かい合っていたものが、ATと置き換わっていることがある。これが、DNAの一塩基の変化、一つの文字の変化ということになる。今回、検出したのはこの部分である。変わっている部分、この文字の並びが変わっている部分が二世の方でどれぐらい多いかということを検出したのが、今回の論文で発表したことである。
欠失というのは、この文字の並びがそのままなくなると、何十ベースも何百ベースもなくなるということである。挿入というのは、文字が何百ベースの文字が入ってしまう異常というか、変化になる。本当は、放射線による損傷というのは、大きな単位でなくなるというのがおそらく一番多いだろうと考えられている。本当はこれを解析したいのだが、技術的な制限があるため現在は解析することはできない。この欠失する、なくなるということを見つけるのは、今の技術をもってしても困難である。そのため、現時点で解析可能な一塩基の変化を解析したものが、今回の研究である。もっと大きなくくりの話だが、染色体の異常についても今回の研究で見ているが、これについても影響がなかったというのが結論である。
この資料は他の研究者からいただいたものであるが、放射線影響研究所で実施された被ばく二世の遺伝的影響、親から受け取った遺伝子で子供に何らかの変化が起きるかということを解析している。調査項目と書いてあるのは、最初に説明したとおり、表現型というか特徴である。DNAを見ているわけではなく、どんなことが起こったかである。例えば出生時の異常が増えたかや、体重や性比がどうかなどを調べている。一応は、今のところ有意差はない、影響はないという結論になっていると言われている。
今回の研究の方法として、トリオ解析を行っている。これは、両親と子供、三人という意味である。今回の調査対象は、父親が近距離被ばくをした人、母親は被ばくしていないという人、そしてその子供である。その三人について、概ね一人60億塩基対と言われているが、その約70%を対象に解析している。約42億塩基対を調べている。測定項目については、新規の突然変異、新規の突然変化である。これは何かと言うと、親になくて子供に現れた変化である。DNAのACGTの文字の並びを検出することを、第一の大きな目標とした。他にも、構造異常、染色体異常等もシーケンサーで解析すると見ることができるので、それも見た。この新規の突然変異については、全て確認した。あることを確認した。後ほど他の研究者の論文を引用して説明するが、計算上これぐらいはあるのではないかとされている研究であるが、ここまで真面目にと言うか、精緻に新規の変異を検出したのは今回の論文が初めてのものである。
ここからが論文の内容になる。第1トリオ、第2トリオ、第3トリオと、対照として両親ともに非被ばく者のトリオである。被ばく者は父親で、爆心地からの距離がそれぞれ示されている。また、何歳の時に被ばくしたかということと、子供ができた時に何歳だったかということを調べている。この時に、近距離被ばく者である、放射線を浴びたということを担保するために、脱毛の症状があった人を対象に調べている。確認された新規の突然変異、被ばく二世の人だけに現れた突然変異、塩基の並びの変化が、第1トリオでは62個が新規突然変異である。第2トリオでは81個、第3トリオでは42個だった。非被ばく者の両親の子供は48個の新規の突然変異があった。これだけを見ると、増えているとも減っているとも言えない結果になる。次は大きな構造異常と記載しているが、染色体を見て分かるようなレベルの異常である。これは一応ないということになる。これはもう少し詳細に解析しないと、本当にないのかと言われると、微妙なところである。シークエンスの解析や塩基配列の解析をする中で、見ることができた構造異常はないという結果になっている。
次の資料が最初に参考にした論文で、2012年に発表されたものである。横軸は子供が生まれた時の父親の年齢で、縦軸が子供に起こった新生突然変化である。父親の年齢が上がると、子供にDNAの損傷、新規の突然変化が多くなる。大体、父親の年齢が10歳上がると2個増えると言われている。リニアと言うか、直線的な関係である。少しばらつくが、父親が30歳の時に子供が生まれたとすると、その子供は60個程度、多いところで80個、少ないところで40個ぐらいの幅で新生突然変異が起こる。父親の年齢が40歳ぐらいになると子供は80個ぐらいの突然変異が起こるということが、この論文で出ていた。先ほど説明したが、この論文では最後まで目で見て変異があったかということは確認していない。次世代シーケンサーでは機械で数字が出てくるが、それで確からしいというところを拾い上げると、父親が30歳の時に子供が生まれると60個の変異があるということである。私達の研究では、最後まで調べて40個から80個の変異があるということを確認している。この、数字だけで選び出した新生突然変異の数だが、そんなに間違っていないと思う。40個、60個、80個の変異というのは、このレンジの中に入る。これは、言わば一般集団の中の親子関係から生じる新生突然変化なので、この直線から大きくずれていることはないだろうと考えている。
結論としては、被ばく二世の方には新規の一塩基変化が増えているという証拠は、今のところないだろうという論文の結論になっている。今回の研究で、一塩基変化を確実に捉えることはできた。全ゲノムシーケンス法で全て数えた。被ばく者以外の一般のトリオで先ほどの論文のような直線が引ければ、被ばく二世がどの直線に乗るか、どれぐらい離れているかということで、ひょっとしたら個人の放射線によるリスクが定量化できる可能性があるのではないかと考えている。この研究では二世の方を調べているが、元はと言えば被ばく者の一つの細胞に、この場合は父親なので一個の精子に入っていた変異を数えているということになる。それは、被ばくしていない人とほとんど変わらないだろうという結論になる。後方視的に何を調べたかということを考えると、そういう結論になる。
研究の限界と書いてあるが、ゲノムの変化、今回、一塩基変化を見たけれども、欠失を捉えられていないということは最大の問題である。これは問題ではあるが、機械の限界なので仕方がない。ちなみに、CNVと書いてあるが、1,000個の文字がなくなっていたり、増えていたりということは、50組を調べたら1組あると言われている。ほとんどないということである。これは機械で現在は検出できていないので、機械が発達すれば調べられるだろうと思う。また、調査対象が3トリオだったので、統計学的にどうか、優位性があると結論づけることができる対象数かと考えると、解析対象が少ない。今回は、個別に3トリオの対象の方に個別に同意書をいただいているが、もし大規模に調査を行うとなると、システマティックに旗を振ってやるべきではないかと思う。私からの説明は以上である。
【会長】
私が知る限り、DNAレベルで一塩基の変化を追及したのは、事実上世界でこの論文だけである。方法が発達してきたということも背景にあるかと思うが、限界もあるということ。私がDNAの専門家ではないので理解できない部分もあったが、委員の皆様の多くはDNAの専門家であるので、質問があればぜひお願いしたい。
【E委員】
急性症状が出ている父親を対象にしているが、その被ばく者の方の被ばく線量はどれぐらいか。
【A参考人】
情報としてあったが、今お答えできる資料を準備できていない。今この場できちんとお答えすることができない。
【会長】
被ばく距離が1.0キロメートルから1.2キロメートルなので、100mSvは超えて200mSVから300mSv程度だろう。
【A委員】
研究費が高額なので、たくさんの方を対象にすることが困難な研究だと思う。まずは3トリオ、10人弱の方を対象に調査してみたというところで、比較的被ばく線量が多い方を選んだつもりではあるけれども、結果が出ていない。もちろん、動物実験ではマウスであるが、マウスやヒトの違いはあるかと思うが、今回の研究はデータとして意味があると考える。
【会長】
マウスでは影響があるとの報告があるのか。
【A参考人】
マウスの精巣に高線量を照射して、その子孫に、その研究では表現型だったが、遺伝病や奇形などがどれだけ出たかを数えて、増えるというのがマウスでの報告である。
【会長】
説明の序盤で、疫学調査についてご説明いただいたが、疫学ではポジティブというか、はっきり影響があるということは、今まで一度も検出されていない。今回、初めてDNAの研究がなされたが、結論としてはポジティブではなかったということである。しかし、方法としては新しい方法なので、今後、欠失等が検出されるようになれば、同じ方法で調べることができるということか。
【A参考人】
方法論としては、これで確定だと思う。あとは、何を見るかである。欠失を正確に見ることができるのであれば、もちろんその方が良い。通常50組に1つあるとされている欠失が、例えば1組に1つあるとすればそれは大変なことになるので、きちんと調べられるのであれば、欠失を見るのが一番である。
【B委員】
技術的なことを教えていただきたい。これは次世代シーケンサーで解析されたと思うが、その時の一塩基のバックグラウンドと、実際の変化というのを、バックグラウンドのレベルはどれぐらいになるのか。
【A参考人】
バックグラウンドというとなかなか難しいと思うが、次世代シーケンサーが吐き出してくる情報の中の確からしさというのは、一応、使っている。このスライドで、ここが一応、確からしさの基準である。このGQが90以上というのが一緒に吐き出されてくると、100なら調べると58個あるということになる。このGQというのが90を下回っていて、もう一つの値、クオールというので調べてみると、170あって本物は4つだけということになる。この数字のどこで切るかということでバックグラウンドは変わるが、大体40%ぐらいは本物というところを探せるぐらいの精度である。
【B委員】
それは、今後の技術開発でバックグランドが広くなるという可能性はあるのか。
【A参考人】
このシーケンサーを使う限りは、このあたりがマキシマムではないかと思っている。百発百中当たるということにはならない。50%ぐらいがせいぜいだろうと思う。
【D委員】
大き目の構造異常のところで、これはPCRで、この三つのトリオとそれから対照群では数字があまり変わらないが、プライマーヘッドとの関係と言いうか、こんな遺伝子の場合にはどうなるといった関係が分かるのか。
【A参考人】
一塩基変化に関しては、中身は見ていない。それはアミノ酸が変わったり遺伝子が壊れるものもあるだろうし、全く関係ないものもあるだろうけれども、中身は全く見ていない。見てもしょうがないだろうと思って、研究をしている。
構造異常に関しては対象領域が70%と言ったが、30%はどうしてもプライマーが作れないので、70%と70%のところがつながった構造異常のところに関して調べて、ないという結論を出している。
【C委員】
この三トリオは、親に脱毛があるいということだが、対象はどのようにして選定したのか。
【A参考人】
血液内科の先生と、この論文の第一著者である先生が健診を行う中で、まずは被ばく者ご本人に説明し、次に配偶者、最後に二世の方に説明し、三人の承諾をいただいた上で調査を行った。
【C委員】
解析を行うのに、どれぐらい時間がかかるのか。
【A参考人】
研究を始めた時点では、一人の解析を行うのに3~4ヶ月必要だった。今は機会も進歩したので、1ヶ月程度でデータは出る。その確認作業に1ヶ月程度必要である。
【会長】
この研究では、最終的にどれぐらい時間がかかったのか。
【A参考人】
5年程度かかった。
【会長】
大変な研究である。精子と卵子が放射線を受けて傷が付くのが100%ではなく、10%や20%とバラつきがあるのであれば、これを疫学調査として影響の有無を見極めるためには、相当な数の対象者を選定して研究する必要があるのか。
【A参考人】
資料の最後のところで引いた直線が引けるかということになると思う。被ばく者の方々と一般集団の方々を比較して、線の傾きや分散がどうかということに、最終的には落ち着くことになるかと考えている。
【会長】
もし、今回の調査で一例でも200や300の変異があった場合は、三トリオの調査であっても有意な差があると言えるようなものか。
【A参考人】
有意な差があるとまでは言えないと思うが、影響があると考え、一塩基変化についてより本格的な調査を行うのではないかと考える。
審議事項
2 第8回研究会までの中間経過報告について
【会長】
私から報告させていただく。厚生労働省の原爆被爆者援護対策室に行き、室長ほか数名の職員の方に資料に基づいて説明してきた。
この際に用いた資料は、今回の研究会の資料2の16ページまでで、第1回から第8回までの概要をまとめたものである。
第1パラグラフは、被爆未指定地域住民の推定被曝線量については、「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告(岡島報告)」の間接的セシウム線量に基づく線量推定と、被爆後早期に測定された理化学研究所仁科研グループやマンハッタン調査団及び米国海軍医学研究所による空間線量測定(実測値)のデータ、島原半島まで測定したデータとも比較した。これらの推定線量データから、「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告(岡島報告)」と同程度の20mSv近傍の最大推定線量を得た。これらの結果から「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告(岡島報告)」の空間線量を導き出す方法は確実なものであったとの結論に至った。また、広島大学の静間特任教授の被曝推定線量も「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告(岡島報告)」の被曝線量の推定値はほぼ妥当であるとの評価が得られた。以上の結果より、被爆未指定地域の一部の地域において、20mSv近傍を超える低線量被曝があったことが推定されると結論した。
一方、100mSv以下の低線量被曝の人体影響については、鹿児島大学の秋葉教授の「低線量放射線の健康リスクについて」、放影研の小笹疫学部長による「原爆被爆者追跡調査(寿命調査:LSS)における低線量被曝リスクの評価」の研究について100mSv 以下の被曝線量では明瞭な癌、白血病のリスク上昇はないとの説明をいただいたほか、フランス、英国、米国の3カ国原子力施設労働者の後方視的国際研究(INWORKS)による癌と白血病のリスクありとする報告、米国学士院の「低線量被曝による健康リスクに関する委員会」の1997年の報告書に含まれる妊婦の骨盤X線検査による胎児被曝により癌及び白血病のリスクが上昇するとした英国オックスフォード大学スチュアート教授グループの研究などの国際的論文を収集し、研究会で種々の角度から検討を行った。
その結果、被爆未指定地域において推定された20mSv程度の低線量被曝の影響を示す論文として、スチュアート等の報告が米国学士院報告では挙げられている一方、このスチュアート論文も含め、当研究会委員の間でも判断が分かれるINWORKS論文なども存在する。したがって、現在のところ20mSvを含む低線量被曝の人体影響についてはなお不確実な状況であることを申し述べた。
この他にも、小児のCTスキャン被曝による癌及び白血病のリスク上昇ありとする英国、オーストラリアなどの報告について、現在Epi-StudyというヨーロッパEU11カ国から120万人の小児及び青年におけるCTスキャンの低線量被曝の癌及び白血病のリスクに関する追試研究が進行中であるが、昨年中には結果が出なかった。今後も引き続き最新の研究論文等の情報を収集し、検証していくことが必要であると考えている、ということが今回の報告の骨子である。
また、放射線影響研究所や原子爆弾後障害研究会における被爆二世における白血病の増加の論文を解析したが、科学的には十分な根拠を欠いているとの結論を得ている。
以上のように、20mSv程度の低線量の人体影響を確定できる確固たる疫学データ等はまだないものの、今後も引き続き最新の研究論文(Epi-Study)等の情報を収集し、検証していくことが必要であると報告してきた。
厚生労働省側から突っ込んだ質問はなかったが、よく分かりましたということで、中間経過報告を受け取っていただいた。
審議事項
3 子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題について
【B委員】
それでは、日本学術会議が「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題について」ということで報告書をまとめているので、ご報告させていただく。これは、臨床医学委員会に放射線防護・リスクマネジメント分科会というものがあって、そこがまとめた報告書である。副題として、現在の科学的知見を福島で生かすためにということで報告書が出されている。
報告書の内容を説明したいと思うが、時間が限られているため、関心が高いと思われる放射線の健康への影響とリスク評価を中心に説明させていただく。また、福島での事故における実際に健康影響がどのように評価されているのかも説明する。
資料の1ページには、この報告書をまとめた背景が記載されてある。東京電力福島第一原子力発電所事故から既に6年が経過している。この間、災害弱者であり、放射線感受性が成人より高いと言われる「子ども」と「放射線」の問題については、数多くの、非常に様々な議論がなされた。福島原発事故を含む災害の影響から、子どもを守るとともに、被災地を復興するために何をすればよいのか、学術コミュニティではこれからも科学的知見と現状に立脚した議論を行うべきであるため、本分科会の責務として、こうした議論のベースとなる報告書を作成することとしたものである。
そして、先ほど説明したとおり、この報告書では、子どもを対象とした放射線の健康影響や線量評価に関する科学的知見を整理するというのが一つの目的である。それからもう一つが、福島原発事故後の数年間に明らかになった健康影響に関するデータとその社会の受け止め方について整理・分析を行うということである。なお、この報告書における「子ども」とは、胎児と0歳から18歳までを指している。
目次をご覧いただくと分かるが、このように非常に詳細な内容になっているので、先ほど申し上げたような内容について説明させていただく。具体的には、2の子どもの放射線被ばくの影響というところでは、(1)の子どもの放射線被ばくによる健康影響に関する科学的根拠、(2)の子どもの放射線防護における課題、(3)の福島原発事故による子どもの健康影響に関する社会の認識、そして(4)の放射線影響をめぐる様々な見解、これらについて説明する。それから、3の提言に向けた課題の整理だが、上記を踏まえた上での課題の整理を行っているが、時間の都合上、割愛させていただく。
2ページから、2の子どもの放射線被ばくによる影響ということで、(1)の子どもの放射線被ばくによる健康影響に関する科学的根拠ということで記載している。我々が放射線影響について考える際に、一番大きな参考資料とするのが、国際機関の評価になると思っている。特に、国連に附属している原子放射線の影響に関する国連科学院会、UNSCEAR(※2)と呼んでいるが、この報告書は世界中から放射線影響の専門家が集まって、今までに発表された放射線影響に関する論文を評価して、非常に中立的な、あるいは科学的な立場から評価をするため、客観性があるとして国際的には評価されている。その評価から始めている。ここでは、最初の導入として、福島原発事故に関する評価が記載されている。これによると、計画避難区域住民の事故後最初の1年間の実効線量は、成人だと4.8から9.3mSv、1歳児だと7.1から13mSvという評価になる。それから、同じ集団での甲状腺の等価線量については、成人で16から35mSv、1歳児では47から83mSvと推定されており、UNSCEARでは1歳時で最大83mSvという評価である。この評価を基に、将来の健康影響について評価しているが、将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因し得る有意な変化がみられるとは予測されない、また先天性異常や遺伝性影響はみられないとしている。一方、甲状腺がんについては、最も高い被ばくを受けたと推定される子どもの集団については、理論上ではあるが、リスクが増加する可能性があるとしている。こういう評価をした科学的根拠について、これから説明する。その根拠については、国際機関の見解に基づいて概説することとなっている。
それでは実際の国際機関の見解について説明する。1.が子どもの放射線被ばくの健康影響に関する国際機関の見解ということで、アとして確定的な影響、有害な組織反応について、子どもの影響がどのように評価されているかということが記載されている。子どもと成人とで感受性に相違がみられるということは広く知られている。例えば認知機能、白内障、甲状腺結節は子どものリスクが高く、肺機能不全、骨髄不全、卵巣不全は、子どもは比較的、抵抗力があるということである。神経内分泌機能や腎機能への影響は成人と変わらないというのが、確定的影響で子どもに関する評価ということになる。
それから、発がんに関する確率的影響だが、UNSCEAR2006年報告書では、幼少期に放射線被ばくした人々の生涯発がんリスク推定は不確かであるが、あらゆる年齢で被ばくした人々の発がんリスクに比べて2~3倍高いかもしれないと記載されている。さらに2013年の報告書では、子どもと成人の放射線影響やリスクの相違に注目した、より詳細な解析を行って報告をしている。その結果が、20ページの表1である。ここに記載されているとおり、成人と子どもを比較した場合、子どもの方が一般的には2、3倍感受性が高いということだが、詳細にみると臓器によって異なるということである。がんを部位ごとに記載してあるが、肺がんは成人と比較して低いということになっている。そして皮膚がんは、子どもの方が感受性が高く、乳がんも子どもの方が高い。膀胱は大人と差がない。脳や甲状腺については子どもの方が感受性が高く、慢性リンパ性以外の白血病と骨髄異形成症候群も子どもの方が大人よりも感受性が高いと記載されている。それ以外にも、十分なデータがないために比較ができない臓器もある。
これらをまとめると、白血病、甲状腺がん、乳がん、皮膚がん、脳腫瘍などおよそ25%の腫瘍の発生は子どもの放射線感受性の方が高いということになっている。膀胱がんなどおよそ15%の腫瘍では子どもと成人の放射線感受性は同じぐらいである。肺がんなどおよそ10%の腫瘍では外部被ばくへの感受性が子どもの方が低いという結果になっている。食道がんなどおよそ20%の腫瘍では発がんリスクと被ばく時年齢との関連を結論付ける十分なデータがない。ホジキンリンパ腫、前立腺がん、子宮がんなどを含む約30%の腫瘍では、全ての被ばく時年齢で、放射線被ばくとリスクの間の相関がほとんど観察されなかったということが報告されている。
それから、ウに記載しているのが遺伝性影響である。先ほど、非常に詳細な分子レベルでの遺伝的影響がA参考人から報告されたが、ここに取り上げているのは2001年にUNSCEARが遺伝的影響についてまとめたものである。この報告によると、原爆被爆者二世をはじめとして、多くの調査があるが、放射線被ばくに起因するヒトの遺伝性影響を示す証拠は報告されていないということになっている。具体的にどういう指標で測定したかということだが、放射線被ばくした両親から生まれた子どもに染色体の不安定性の増加、ミニサテライト遺伝子変異、経世代的遺伝子不安定性、性別比の変化、先天的異常の増加、発がんの増加等について調べた限りでは、変化が認められていないというのが2001年までのUNSCEARの報告である。
妊娠している母親が被ばくした時の子どもへの影響ということだが、まず確定的な影響としては、着床前の放射線被ばくによる胚の死亡は100mGy以下の被ばくでは極めて稀であると報告されている。それから、ここは非常に重要なところだが、主な臓器の形成期、器官形成期に被ばくすると、奇形発生のリスクが最大になるということが報告されている。その例として、妊娠8~15週の時期に胎児が被ばくすると、生後の重篤な精神発達遅滞が起こる可能性があるということである。そのしきい線量は低くても300mGyだろうと報告されている。定量的に表現すると、1GyあたりのIQの低下が25と推定されるという報告になっている。それから、広島・長崎の原爆被爆者の調査では、被爆妊婦の子どもに小頭症がみられたことが報告されている。
それから、胎内被ばくでの発がんリスクについてだが、胎児の生涯がんリスクは乳幼児と同程度であると報告されており、これによると全人口についての放射線誘発がんリスクは最大で3倍程度高いということになる。
次に、子どもを対象とした線量評価の特徴ということでまとめている。リスク評価をする上では線量評価の評価になるが、子どもを対象とした線量評価は特徴がある。次のページを見ていただくと、外部被ばく線量がアという項目に記載されている。子どもは成人に比べて臓器を遮蔽する役割をする周囲の組織が少ないので、同じ被ばく線量を受けても、成人より吸収線量が高くなる傾向がある。それから、身長が低いので、臓器が地面に近く位置することになり、地面からの被ばく線量が高くなる傾向がある。
それから、内部被ばくに関しては、子どもの成長に伴って代謝や生理機能、食事や呼吸量、あるいは身体活動などは非常に目まぐるしく変わり、同じ年齢でも個人差が大きいということがあり、正確な評価は難しいところがある。特に放射性核種のうち、子どもと大人で大きく違うものがある。その代表が、ヨウ素131である。これは、乳児が大人と同じ量のヨウ素131を摂取しても、甲状腺の吸収線量が大きく異なり、具体的には大人よりも8~9倍大きくなる可能性があるということである。一方、セシウム137に関しては子どもの生物学的半減期が成人より短いということだが、最終的には大人と子どもで差がないということである。それを図で示しているのが、21ページの図1である。青色で示しているのがヨウ素131で、橙色で示しているのがセシウム137である。セシウム137は年齢であまり差がないが、ヨウ素131は1歳や生後三ヶ月だと成人に比べて8倍から9倍程度、単位摂取量当たりの預託実効線量係数が大きいということになる。このように、大人と子どもでは同じ量の放射性物質が体内に入った場合でも、ヨウ素131の場合は非常に高い甲状腺の被ばくがあるということになる。
ご存知のとおり、チェルノブイリ原発事故後に小児甲状腺がんが増加し、6,000人が手術を受け、15人が死亡したと報告されている。これは、先ほどのデータからも明らかなように、同じ量のヨウ素131が体内に入った場合は子どもの方が大人よりも被ばく線量が高いことに加えて、チェルノブイリの場合は汚染したミルクの飲用により、より多くのヨウ素131を摂取したことによって内部被ばく線量が大きくなったものと考えられている。例として、チェルノブイリ事故後48時間以内に避難したプリピャチの居住者の場合、成人の甲状腺吸収線量が0.07Gyと推定されているのに対し、乳児は2Gyと推定されている。子どもの場合は、非常に高い線量の被ばくをしたということになる。
それから、3.に子どもの放射線防護における課題ということで記載されている。ここでは、我々が小児科学を大学で学ぶ際に最初に言われることでもあるが、子どもは「小さな大人」ではないということである。先ほども説明したとおり、子どもと大人は違うということだが、放射線防護体系を見ると、まだ子どもに特化した放射線防護体系というのはできていないため、現在、その基礎となるデータの蓄積が行われていて、子どもに特化した放射線防護体系の確立に向けて調査が行われている段階である。
放射線防護体系の中で、実際にどのように行われているかということだが、実際には実効線量の子どもへの適用がなされている。実効線量とは、標準男性と標準女性を平均して実効線量を求めていて、それを一般に適用している。この値は、実際にはこの実効線量の推定値として求めている実用量というものがあるが、これは体格の小さい子どもにとっても十分安全側の推定値となっていることが多い。こういったところで、子どもに対する放射線防護の安全性が確認されているということである。
今後の子どもの被ばく線量やリスクの評価における課題だが、今あるデータは基本的には、原爆被爆時の高線量率被ばくに基づくデータであるので、今後は低線量、低線量率被ばくでの年齢別・臓器別の感受性を明らかにするようなデータの精密化が必要であるということである。
次のページには、医療被ばくにおける子どもに関しての記載がある。(2)に子どもの放射線診断・治療と防護ということで記載がある。
1.が子どもの医療被ばく防護ということで、医療被ばくにおいても放射線防護の3原則、正当化、最適化、線量限度の適用の3原則があるわけだが、医療被ばくにおいては診断や治療の目的を阻害しないために、線量限度の適用は用いられていない。正当化に関しては、最終的には医師が放射線診断や治療が患者の利益になるということで用いられている。最適化に関しては、放射線診断に関しては診断参考レベルが採用されており、放射線治療に関しては正常組織への被ばくをできるだけ低くするということで治療が行われている。
現在は、子どもに対しても放射線診断や治療の機会が増えており、特に血管内治療、IVRが普及して、子どもにも適用されるようになっている。IVRの場合は、比較的被ばく線量が高くなる。これらに関して注意喚起されており、例えばICRP(※3)は、診断に当たっては、診断に支障のない範囲で重要臓器、特に精巣、卵巣、甲状腺に遮蔽処置をすべきだとしている。また、核医学では、子どもの年齢に応じた放射性医薬品の適正な投与量を決める必要があると指摘されている。
続いて、医療放射線による子どものがん罹患リスクについて説明する。この研究会でも論文を紹介していただいたが、医療被ばくに伴って子どものがんリスクが増えているのではないかと報告が出てきている。それを概説している。
アとして、小児患者の医療被ばくということで、これはこの研究会でも取り上げたが、1985年から2002年に初めてCT検査を受けた22歳未満の約18万人を対象に疫学調査が行われている。これは英国の調査である。この結果によると、CT検査で各臓器・組織が受けた放射線量と罹患率との関係が解析され、1mGy あたりの過剰相対リスク(※4)は、脳腫瘍で2.3%、白血病では3.6%と増えているとの報告である。しかし、絶対リスクそのものはそんなに大きくないということである。同じ様な調査がオーストラリアでも行われており、この場合はCT検査一回あたり全がんの罹患率が16%増加するという報告である。さらには台湾やドイツでも調査が行われているが、これらの調査でも脳腫瘍などのリスクが増加することを示唆する結果である。ここで注意しないといけないのは、普通はCT検査を受けないので、CT検査を受ける要因があるということである。CT検査を受ける必要があった子どもたちは、疾患特異的、あるいは何らかの病態を既に持っている可能性がある。そういう要因は、集団を解析する場合には、選んだ集団に偏りがある可能性があるので、そういうことも注意して解析する必要があるということが述べられている。
それから、小児がんの治療後に見られる放射線誘発二次がんについても記載されている。特に子どもの場合に注意しなければならないのは、大人よりも放射線感受性が高いということと、大人よりも長く生きることになるので、放射線の影響が出る可能性があるということである。そういったことから、放射線治療後の二次がんについても注意する必要があるということで、ここでは取り上げている。具体的には、小児の放射線治療で頻度が高い二次がんとして、骨軟部肉腫、甲状腺、脳と乳腺のがんで、二次がんの80%に相当するということが記載されている。
それから、子宮内での被ばくである。イの項目だが、有名なオックスフォードのサーベイである。これは、妊娠中にX線診断を受けた母親から生まれた子どもの小児がんのリスクが1.4倍程度高かったという報告である。この被ばく線量が約10mGy程度ということで、非常に低い線量であるが、リスクが高かったということで注目されている。このデータがシステマティックレビューというものが行われている。このシステマティックレビューというのは、データを体系的に評価・検証する作業であり、その作業を行った結果では、統計的有意なリスクの増加が認められなかったということになっている。その後、このデータに関して新しい情報が報告されている。どういう情報かと言うと、骨盤計測とは、胎児が非常に大きい場合に出産が非常に困難になる可能性があるということで、骨盤のX線診断を行うが、大きな胎児は特定のがんのリスクが高いという結果が出ている。そうすると、リスクが高い胎児の集団を見ているために、放射線の影響として捉えられた可能性がある、因果の逆転の可能性があるということが指摘されている。それについても結論が出たわけではないので、今後もこういった調査が必要であるいということになっている。
次に、福島原発事故による子どもの健康影響に関する社会の認識を説明する。これは冒頭の部分で説明したとおりUNSCEARの評価が基本となっている。UNSCEARの評価によると、甲状腺がんは最も高い被ばくを受けたと推定される子どもの集団については理論上のリスクが増加する可能性があるが、それ以外の影響、先天性異常や遺伝性影響、小児甲状腺がん以外のがんに関しては、有意な増加は認められないだろうと予測している。こういう国際機関の調査や予測があるが、一般の方まで情報が届いていないとうこともあって、子どもの健康影響に関する不安は根強いものがある。また、線量推定やリスク予測が困難ということがあり、様々な見解がある。そういったことが、不安の大きな要因になっていたものである。
事故後かなり時間が経過して、様々な影響評価に関する情報が集まってきているので、そういうものを踏まえて、ここでは健康影響の種類別、そしてその各健康影響に関して社会の認識についてまとめている。
最初に1.として、次世代への影響に関する社会の受け止め方ということで、先ほども遺伝性影響に関しての説明があったが、実際に社会にどのような受け止め方があるかということである。
遺伝性影響に関して、あるいは胎児への影響に関しては、日本産科婦人科学会等が胎児への影響は心配ないと言うメッセージを発信した。これは事故が起きてから、比較的早く発出された。そういうこともあって、福島では中絶が増えるということはなかった。チェルノブイリ事故に関しては、ギリシャなど欧州の国々で大変多くの中絶が行われた。その教訓が生かされて、日本では産婦人科学会や地元福島の産婦人科の先生方が非常に頑張って説明をし、母親らもそのことを理解してくれたということである。その後、福島県が実施した県民健康調査の結果が取りまとめられ、福島県の妊婦の流産や中絶は福島第1原発事故の前後で増減していないことが確認された。それに加えて、死産、早産、低出生時体重及び先天性異常の発生率においても、事故の影響が認められないことが証明されている。このように、上記のような実証的結果を得て、科学的には決着がついたとされているが、社会ではそう認識されていない。
ソーシャルメディアを介して、様々な情報が発信・拡散されており、次世代への影響に関する不安が増幅されている。具体的には、県民健康調査や長崎大学が川内村で実施したアンケート調査によると、回答者の半分ぐらいの方が「次世代への影響の可能性が高い」と答えている。それから、平成25年1月に福島県相馬市の医師が市内の中学校で行ったアンケート調査によると、女子生徒の約4割が「結婚の際、不利益な扱いを受ける」というような回答をしている。こういった、誤った先入観や偏見に基づく情報が流布されており、正確な情報を発信して改善していく必要性があるということである。
そして、2.が放射性ヨウ素と甲状腺がんに関する社会の受け止め方ということで、ここは情報が複雑になるので、資料で説明させていただく。まず、最初にあるのが国際機関の評価で、これまでWHO(※5)が最初に行って、その後UNSCEARとIAEA(※6)の報告書が出ている。次にUNSCEARの線量評価だが、甲状腺に関しては一歳児の吸収線量で83mSvという評価になっている。その下にあるのが、福島県が実施したホールボディカウンターによる内部被ばく検査の実施状況である。これは、平成23年6月から平成27年7月までの調査結果である。これによると、26万人以上の方に検査が行われているが、1mSv未満の方が99.99%ということで、最大値が初期の頃に3mSvであることを示した方が二人いたという結果である。
次のページには、現在行われている県民健康調査の概要が記載されている。この調査は、基本調査と詳細調査が行われており、基本調査は事故後4ヶ月の外部被ばく線量を推計するものである。詳細調査は健康状態を把握するための調査で、甲状腺のエコー検査、健康診査、こころの健康度・生活習慣に関する調査や妊産婦に関する調査が行われている。その下の図は、外部被ばく線量を推計するための説明図である。行動記録を取ると、その時の空間線量の分布が分かるので、それから外部被ばく線量が推計できるという内容である。
次のページには、外部被ばく線量の概要が記載されている。これは、平成29年2月20日に開催された県民健康調査の検討委員会での報告である。この調査では47万人以上の方の結果が報告されている。記載されているとおり、99.8%が5mSv未満であるということである。これは県全体の調査で、最高値が25mSvである。その下は妊産婦に関する調査で、早産率・低出生体重児率、それから先天奇形・先天異常発生率は全国の平均と差がないという結果になっている。
次のページには、子どもの甲状腺検査についての資料がある。下の表だが、対象者が約37万人いて、そのうち約30万人の調査が行われている。結果のところに、A1、A2、B、Cと記載されているが、これはエコー所見の分類である。A1は所見が何もなかったということだが、A2は5ミリメートル以下の結節がある、あるいは20mm以下ののう胞があるという所見である。これが47.8%あったということで、この数値が高いのではないか、そしてそれは放射線の影響ではないかということで、最初は大変心配をされた。福島以外の県でも同様の調査が行われている。長崎県、山梨県、青森県で同じような調査が行われていた。その結果として、A2あるいはBと判定される頻度は、事故の影響がない3県と変わらないという結果が得られ、母親らの安心が得られたものである。しかし、この3県の調査は対象の年齢の分布が一致しているわけではなく、厳密に比較することはなかなか難しいものの、概要はこのように比較できるというものである。
その下には、最初の3年間に先行調査ということで、エコー検査が行われており、その結果がまとめられている。その結果、悪性ないし悪性疑いという子どもが116例見つかったということである。その下に年齢分布が記載されている。ここで注目されているのが、0歳から5歳までの子どもでは、悪性ないし悪性疑いは見つかっていないということである。
次のページには、これまでよりたくさんの甲状腺がんあるいはがんの疑いの子どもが見つかったということである。それは、今までの報告で見つかった、臨床的に見つかった甲状腺がんと比較すると、非常に高いということで、その比較を示している。女性だと26.6倍、男性だと40倍以上高いということである。この論文の趣旨は、過剰診断ではないかということを示唆するものである。ここで確認していただきたいのは、福島で行っている検査では、症状のない子ども達を検査して見つけているということで、それは臨床的に症状があって甲状腺がんだと診断されるケースとは随分状況が違うということである。臨床的な、症状が出て見つかる子どもあるいは大人では非常に頻度が低いが、エコー検査で詳細に見ればそういう異常が見つかるという内容である。その下にあるのが、地域ごとに悪性ないし悪性疑いの割合に差があるかを検討した結果、そういう差はなかったという報告である。こういったことから、最初の3年間に見つかった甲状腺がんが放射線によるものかどうかということの検討が行われている。それを行ったのが、県民健康調査検討委員会というところで、中間評価が行われている。これによると、被ばく線量はチェルノブイリ事故と比べて総じて小さい、被ばくからがん発見までの期間が概ね1年から4年と短い、事故当時5歳以下からの発見はない、そして地域別の発見率に大きな差がないということから、総合的に判断して、放射線の影響とは考えにくいという評価がされている。これが、最初の3年間の調査で見つかった子ども達の甲状腺がんに対する影響評価ということになる。
その3年間が経過して、第2ラウンドの検査が行われており、一応、区切りがついている。その結果が記載してあるが、71例の子ども達に悪性ないし悪性疑いが見つかっている。次のページに、先行調査と本格調査のまとめが記載されており、その下に年齢分布が記載されている。最初の3年間に行った調査と、平成26年から平成27年の2年間で行った調査との比較である。この様に、たくさんの子ども達の甲状腺がんが見つかっているが、それは日本だけの現象ではなく、世界各国、特に先進国でそういった現象が見つかっている。それを紹介しているのが、次のページの論文である。これは韓国の例だが、1999年頃から甲状腺がんが非常にたくさん見つかってきている。しかも、その内容が甲状腺の乳頭がんということである。一方で、甲状腺がんが見つかるものの、死亡率は変わっていない。なぜ、このようにたくさんの甲状腺がんが見つかるのかというと、この論文で指摘しているのが、検査の頻度が増えると甲状腺がんの発見率が増えるということで、検査をすれば甲状腺がんがたくさん見つかってくるということである。その下はアメリカの例だが、アメリカでも同様にそういった結果が見つかっている。
次のページを見ていただくと、各国の、アメリカ、イタリアやフランスと書いてあるが、そういった先進国でも同様に、検査をすることによってたくさんの甲状腺がんが見つかってきているという報告がなされている。福島の1回目の検査では、検討委員会で放射線の影響は考えにくいという評価だが、現在、2回目の検査の評価が始まったというところである。
このように、甲状腺の検査を行えば甲状腺がんが見つかるということで、一方で過剰診断の可能性があるのではないかということが指摘されている。検査をすることが、果たして患者さんの利益になるのかどうかという様な、倫理的な観点でも今後検討する必要があるということが議論されている。それが、福島の現状ということである。
それから、放射線セシウムに関する社会の受け止め方ということで記載がある。放射線セシウムに関しては、今まで様々な報告があるが、放射線セシウムとがんのリスクを証明するようなデータはまだない。その結果を得るためには、非常に長期の観察が必要ということになる。
最後に、リスクの相対化ということで、チェルノブイリ事故との比較について説明する。リスク値を言われても、実感として捉え難いところもある。比較することでリスクを実感しやすいという利点があるので、それを行っている。外部被ばく線量に関しての比較では、比較的外部被ばく線量が高いと推定されている川俣町の住民の皆様の調査結果と、チェルノブイリの事故との比較がなされている。それが、22ページの図2である。先ほども紹介したが、99%の方がこういった比較的高い地域であっても5mSv未満であるということである。これに対して、ウクライナの避難者は平均で20mSvあり、ベラルーシでは30mSvである。チェルノブイリよりは、はるかに低い被ばく線量であるということが確認できている。
それから、放射性ヨウ素による甲状腺の被ばく線量だが、チェルノブイリの場合は非常に高い線量が確認されている。20ページの表2にまとめられている。ベラルーシ、ロシア、ウクライナということで、非常に高い甲状腺の吸収線量が確認されている。これと福島の被ばく線量を比較したのが、表3である。左のカラムが福島の子ども達の被ばく線量で、30mSvに99%以上の人が入っている。これに対して、チェルノブイリの場合は100mSv以上に99%以上が入っており、福島とは大きく違う。今後、甲状腺の被ばく線量と健康影響に関して検討が進められるということだが、甲状腺への影響には様々な議論があり、国際的な評価以外にも、国際的な評価とは異なる観点から放射線の影響があるのではないかと評価する専門家もいる。今後も、科学的なエビデンスを積み上げて評価する必要があるということである。この報告書の内容についての説明は以上である。
【会長】
私から質問させていただきたい。福島のことはよく分かったのだが、前半の部分で日本のデータがあまり出てきていない。外国のデータが多いが、日本人の子どもの論文はあまりないのか。
【B委員】
子どもだけの論文はあまりない。情報となるのは、原爆被爆者のデータである。
【会長】
承知した。少し気になったのが、我々は現在、CT検査を注目しているわけだが、イギリスやオーストラリアのデータはあったが、日本ではそういった研究はされていないのか。どこかで発表などを聞いたこともないか。
【E委員】
日本で、小児の放射線検査を受けた方の調査が出てこないのは、ひとつは、がん登録が全国規模であるかどうかということである。これは、小児がんは症例数が多いわけではないので、ある程度プールされたデータでないと、きちんとした判断ができないということが一番大きい理由ではないかと思われる。
【会長】
日本でもCT検査を受けた子どもは、結構いるのではないかと思っているが。
【B委員】
一応、放医研が中心となって、そういうデータは集めている。
【会長】
承知した。欧米で結論が出れば、もちろん出ない可能性もあるが、結論が出た場合に日本はどうなのかということになるかと思ったので、質問した。
それから、書きぶりが不明瞭な部分があるように感じる。オックスフォードの小児のがん研究のところだが、この委員会がどのように判断しているのかが伝わりづらいと感じる。例えば、10mSvという非常に低い線量でリスクが1.4倍になると書いているが、これについては何も評価していないのか。
【B委員】
それについては、システマティックレビューで統計的な有意差が確認されていないということが記載されている。
【会長】
この委員会では否定されているということか。
【B委員】
そのとおり。
【会長】
そういったところが分かりづらく感じた。論文の引用・説明でつないであって、委員会として、日本学術会議としてどう判断しているかが伝わりづらい。
【B委員】
ご指摘のとおり、そこで完全に否定しているという表現にはなっていない。
【会長】
技術の進歩によって被ばく線量が低下しているためではないかという記載があったが、これは最初のオックスフォードスタディーの線量と追試の線量は比較できるはずである。アメリカの学術会議ではそれを比較しているし、オックスフォードスタディーも線量が時代とともに低くなっているというデータを出しているし、そういった検討が少し不足しているのではないかと思う。
この会議は、それぞれの委員の方が、自分が論文を読んでの判断や、CT検査でのリスク等を表明するような会議ではなかったのか。
【B委員】
文章をまとめる仮定で議論は行うが、例えばCT検査に関してもそれで結論が得られるようなデータが、現時点では得られていない。そのため、こういった事実があるということを記載するにとどまるということである。
オックスフォードの件についても、10mSvという非常に低い線量でオックスフォード調査ではリスクがあるということだが、一方でシステマティックレビューをすると、リスクは検出されなかったということである。それは、それで決まったということではなく、診断被ばく線量が低減しているということもあるのでそれも説明しないといけないし、一方で別の情報としては計測をするような大きい胎児は別のリスクを持っている集団だということも分かってきたので、そういうことからすると因果の逆転の可能性もあるということである。それについても、因果の逆転が証明できたということではないので、決定的な結論には至らないということである。
【会長】
承知した。以上で、第9回研究会の議論を終了する。
〈用語解説〉
※1 インヘリテッド
遺伝性の、遺伝した。ここでは、遺伝を指す。
※2 UNSCEAR
原子放射線の影響に関する国連科学委員会。電離放射線による被曝の程度と影響を評価・報告するために国連によって設置された委員会である。
※3 ICRP
国際放射線防護委員会。専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う民間の国際学術組織である。
※4 過剰相対リスク
相対リスクから1を引いたもので、相対リスクのうち、調査対象となるリスク因子(この場合は被曝放射線)が占める部分をいう。
※5 WHO
世界保健機関。人間の健康を基本的人権の一つと捉え、その達成を目的として設立された国際連合の専門機関である。
※6 IAEA
国際原子力機関。国際連合傘下の自治機関であり、原子力の平和的利用の促進を目的としている。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く