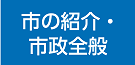ここから本文です。
令和元年度第2回 長崎市市民力推進委員会
更新日:2019年9月12日 ページID:033429
長崎市の附属機関について(会議録のページ)
担当所属名
企画財政部 市民協働推進室
会議名
令和元年度第2回 長崎市市民力推進委員会
日時
令和元年8月5日(月)18時30分~
場所
長崎市市民活動センター「ランタナ」 会議室
議題
市民力向上と協働の推進に係る今後の方向性について
(1)市民活動団体アンケート調査結果の報告
(2)協働研究部会・表彰部会での協議内容の報告
(3)市民活動センターにおける市民活動の現状について
(4)各種調査結果のまとめ
審議結果
■「市民力向上と協働の推進に係る今後の方向性について」
《委員長から市民活動団体アンケート調査の結果報告、事務局から協働研究部会・表彰部会の協議内容の報告、市民活動センター長から市民活動の現状について説明。委員長が各種調査結果のまとめを行った後、委員による協議を行う。》
【委員長】
私から提案だが、今回の調査結果で、改善すべき点が明らかになったので、長崎市における今後の市民力の方向性について、委員の皆さんに意見・提案をいただいた内容を、市長に報告したいと思うが、いかがか。
【全委員】
(異議なし)
【委員】
本日の協議は、市民活動団体どうしの協働ではなく、市民活動団体と市との協働について検討するのか。
【委員長】
長崎市としては、市民活動団体どうしや市民活動団体と企業の協働についても考えているが、本日は、主に市との協働について協議してよいと思う。
【委員】
市民活動団体と市の協働が進まない理由として、市民からすると、市が何をしているかわからないからではないか。このため、各課の仕事内容の公開を工夫したほうがよいのではないか。公開できるもの、できないものがあると思うが、各課の仕事をデータベース化としてみてはどうだろうか。
【委員】
アンケート結果から、4割弱がボランティア団体で、3割が課題解決型であると見えている。こういうところからのアプローチがあるのではないか。
市民活動をどうやって次世代につなげていくかということについては、ボランティアも一般と何ら変わらない。ボランティアであってもお金とは無関係ではない。
やはり、市民活動表彰というと、上から物を言うようなところがあって、そうではなく、市民活動団体と他の主体をマッチングする場が年に何回かあってもよいのではないか。まずは、マッチングに参加してもらうことに注力してみてはどうかと感じる
【委員】
県庁舎には協働スペースが設けられているが、新市庁舎の設計において、各セクションに協議スペースを置くなど、所管課を気軽に訪ねられるようなハード面での設計がなされれば、職員の意識も協働に向かざるを得ないのではないか。
【事務局】
新市庁舎の市民の交流スペースは、現時点で設けられるように計画されており、市民協働にも活用できると思われる。その他、個々の所管の会議スペースについては、確認のうえ後日お知らせしたいと思う 。
【委員】
協働というものを考えるときに、成果として数字を求めるのではなく、数字ではない質のところを成果としてみてほしい。
【委員長】
それは、常日頃から行っているプロセスを公開し、そこで変わっていく様子がわかれば、数字があがらなくてもよいということか。
【委員】
そうである。協働したら、そのノウハウを公開するとか、そういうことの方がよっぽど役にたつと思う。例えば、協働し、不登校者が100人減ることも大事であるが、このノウハウを誰にでも提供することで、必要な情報が世間に広まっていいのではないかと思う。
【委員】
市民活動団体を紹介するハンドブックを発行することになっているが、その周知をもっと図ってよいのではないか。また、ハンドブックをイベント等のブースに設置することで、自団体の活動内容を知らせるとともに、新しい出会いにつながると思う。イベントに市民活動団体が出向くことで、自団体を知らせることも大切ではないか。
【委員長】
情報の公開は非常に大事だと思う。ホームページの内容は、アーカイブ化して、検索できるようにデータを蓄積していってもよいのではないかと思う。
【事務局】
各課の仕事の公開という点であるが、業務については組織規則で規定されており、どの所属でどのような業務が行われているかわかるとともに、担当者が行うような、より詳細な業務についても示すことは可能である。
また、事業は予算の中で、主な事業についての端的な説明を付した資料を、議会に提出しているので事業についてある程度、把握していただくことはできると思う。
情報の周知については、市のホームページにわかりにくい部分があるので、市民にわかりやすいように改善していきたいと思う。
【委員】
「業務」の協働と「事業」の協働を同じものと考えない方がよいと思う。今回のアンケートにおいて協働の経験の有無について確認を行っているが、この協働には「業務」での協働と「事業」での協働が含まれているのではないか。
また、協働の形も様々あり、わからない点も多くあるので、日常生活の中でのマッチング、協働の入門編のようなものをテーマにしてよいのではないか。
【委員】
行政側もできている点とできていない点を整理して、できていない点を協働すべきではないか。
行政側はできていない点は認めて、市民もこれを理解し、そのうえでどうするかを考える文化が必要なのではないかと感じる。
【委員長】
他自治体では、失敗例を成果とした事例もある。失敗した原因を発信することで、その後に活かされることを考えると、失敗も一つの成果としてみることができるのかもしれない。
【委員】
協働は行政のニーズがないところから生まれることもある。この場合、複数の部署にまたがることもあるので、予算の枠組みが難しい傾向にある。
【事務局】
現在、行政の予算は目的別になっているが、今後は、最終的な効果を想定しながら、部署なども含め総合的に考えていく必要があると感じる。
ただし、厳しい予算下で、何を選択するかが大切であり、そのような中で実行していくことが求められていくと思う。
【委員】
人件費の話しになるが、行政が協働により事業を委託する場合、そこで働く人がどのように生活していくかということも想定し、官製ワーキングプアをつくらないようにする必要がある。
【委員長】
民間では、この人件費の考え方はSDGsにあらわされるように当たり前になってきているが、行政も考える時機を迎えているのではないか。
【委員】
行政が団体のスタンダードを知らないので、仕方がない部分もあるが、団体の考え方を理解できる部署が、間でつなぐ仕組みがあってもよいのではないか。
【委員】
人を活動に引き入れようとするとき、どのようにすると興味をもってもらい、いかに次の世代につないでいくかが課題である。
また、あまりだめな部分や失敗事例は表に出てこないものであるが、第五次総合計画の策定などにおいても、そういう部分や協働してほしい部分を表に出していければいいと思う。
【委員長】
自分ごととして関わるためには、課題の明確化が大切である。例えば、長崎市の人口が減っていることは、皆知っているが、どこの地区がどれだけ減っているかは知らない。課題を明確に把握していないので、人口の減少が自分自身にどのように影響してくるか想像ができない。
成功しているまちは、このような課題を、多くの人が自分自身の問題としてとらえているように感じる。
【委員】
市民や市民活動団体は、行政の仕事を理解することで、協働する大切さについて意識が生まれてくるのではないかと思う。
行政は、市民が様々な問題を自分自身の問題として考えられるように、情報を発信していくことも必要だと感じる。
【委員】
学校教育の中で、学生達がボランティアに取り組めるように取り組んでおり、今後も協働の考え方を実践していきたいと考えている。
【委員】
課長・係長研修の協働研修は、何らかのアウトプットができるような研修にしてもらいたい。
【委員長】
協議の主要な点をまとめると、まずは、市民と市がお互いを認める、わかりあう環境づくり。そして、ニーズに対応するため、見えていなかったものが見えてくるという意味での課題の明確化。次に、マッチングの問題。決まった型にはめるマッチングもあれば、新しい形を作り出すマッチングもある。その後、実行していく中で、それぞれの市民活動団体が、いかに次の世代に継承していくかということ。継承していく過程では、新しい人や若い人をいかに巻き込んでいくかという点も重要だといえる。その他、活動、生活していくために、ソーシャルビジネスや社会的企業を視野に入れながら、団体を支援していく、育てていく視点もあってもよいのではないかと感じた。
本日、検討した内容をベースに、これまでの調査結果と併せて、報告書の案を作成し、皆さんに意見をいただきたいと思うが、いかがか。
【全委員】
(異議なし)
【委員長】
それでは、先ほど提案したように市長に報告書を提出する方向で進めていきたいと思う。
- 以 上 -
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く