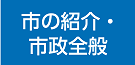ここから本文です。
令和元年度第2回 長崎市個人情報保護審議会
更新日:2020年4月14日 ページID:034464
長崎市の附属機関について(会議録のページ)
担当所属名
総務部 総務課
会議名
令和元年度第2回 長崎市個人情報保護審議会
日時
令和元年8月22日(木曜日) 15時00分~
場所
長崎市役所本館5階 大会議室
議題
・諮問第55号 金融機関への口座振替データの伝送に係る外部電子計算機との直結について(こども部幼児課)
審議結果
結 果 諮問第55号については承認された。
〔質疑〕
【委員】
送信と受信の頻度について
【実施機関】
月に送信1回、受信1回。
【委員】
操作ログと送信ログの確認について、どのように、誰が、どのくらいの頻度で確認するのか決まっているのか。
【実施機関】
特に決まっていない。
【委員】
定期的に行うべき。
【実施機関】
定期的に行う体制をとるようにする。
定期的に紙の使用簿とログを突合するようなルールをつくる。
【委員】
資料の中に、データ伝送用パソコンを出納室職員の目が届くところで管理しており、出納室職員が伝送処理目的以外で使用することがないよう監視しているとあるが、画面等を監視するのではなく、誰が来て作業しているということがわかるとこいうことか。
【実施機関】
使用簿に記載してから使用するルールにしているため、使用簿に記載しない人が勝手に使用することがないようにしている
【委員】
共有フォルダにデータが蓄積されるのか。
【実施機関】
共有フォルダは、一時的にデータをやり取りするためフォルダであるため、基本的には、データの受け渡し後、削除する。データは残らないようにする。
【委員】
出納室に備え付けのUSBを使用し、幼児課からUSBを持ち出すことはないということか。
【実施機関】
はい。以前からUSBにデータを入れて持ち運ぶことによって、紛失等が起こるリスクがあるというご指摘をいただいていたので、ネットワーク上でデータのやりとりすることにしている。ネットワークが繋がっていない部分があるため、必要最低限、USBにデータを移して移動させている。同じ机の上にパソコンを2台置いて、USBの差し換えをして、データを移しており、紛失もする恐れもないということで、運用している。
【委員】
USBの管理体制はどのようになっているのか。
【実施機関】
出納室内で貸し出しを行い、返却の際は、出納室職員がUSB内にデータが残っていないか確認後、記録を取っている。
【委員】
共有フォルダは、他の課とは共有されていないということか。
【実施機関】
共有フォルダは、自所属のID、パスワードを知っていて、自所属のフォルダしかアクセスできないようになっている。
USBは、出納室の2台のパソコンでしか使用できないような設定にしている。
【委員】
USBを紛失した場合は。
【実施機関】
業務自体は、もう1本の予備で行い、探しても見つからない場合は、紛失したUSBは使用できないようにパソコンを設定する。
【委員】
自所属で歳入予算として管理するということは、幼児課で管理するということか。
【実施機関】
これまでは、保育料は、強制徴収債権であったため収納課で一括して管理していたが、今回、幼児保育の無償化により、副食費等は強制徴収債権にならないため、幼児課で管理することとなった。
【委員】
効率化を考えると、出納室の職員が全ての伝送処理を引き受けた方がいいのではないか。
【委員】
セキュリティ上、責任上は、各所属で行う方がよい。出納室の職員が全ての所属の情報を見ることができるのはよくない。現状のやり方の方がいい。
【実施機関】
伝送する所属に専用のパソコンを設置すれば、移動の手間は省けるが、端末や回線の費用などの面から効率化が損なわれるため、そういう面では、一箇所に集めて作業した方が、端末や回線の効率化は図ることができると考えている。
〔審議〕
【委員】
公益性はあると思う。
セキュリティの面では、統一されてきて、だんだんよくなってきている。
ISDNが2024年で終わるが、そのあとはどうするのかという共通的なところを付言して、ログをチェックすることを追加してもらいたい。
【委員】
ある時期から共有フォルダを使用するようになったが、以前、審議会に諮って、USBを持ち運んでいた件も、共有フォルダに変わっているということか。
【事務局】
はい。
【委員】
専用のUSBメモリがなくなったとき、基幹業務系PCと伝送用PCの両方において、なくなったUSBメモリを使用できないように、無効化するという仕組みはいいことだと思うので、USBメモリがなくなったとわかったときは、基幹業務系PCと伝送用PCの両方とも使用できないように設定するということを明言してもらいたい。
【委員】
答申は会長一任で。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く