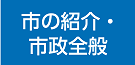ここから本文です。
令和2年度第1回 長崎市ハラスメント調査等審議会
更新日:2020年5月29日 ページID:034681
長崎市の附属機関について(会議録のページ)
担当所属名
総務部 人事課
会議名
令和2年度第1回 長崎市ハラスメント調査等審議会
日時
令和2年5月15日(金曜日) 13時00分~
場所
長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室
議題
ハラスメントに関する指針等について
審議結果
委員改選後、初めての審議会開催であったため、会長の互選後、事務局から会議の進行及び審議会の概要についての説明が行われた。
その後、「ハラスメントに関する指針等について」配付資料に基づき、事務局による説明が行われ、その後、説明に対しての質疑応答のほか、具体的な審議が行われた。
ハラスメントに関する指針等について
【参考:各資料の要綱等の名称】
資料1. ハラスメントの防止等に関する要綱
資料2. ハラスメントの防止等に関する要綱の運用について
資料3. セクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針
資料4. 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針
資料5. パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項についての指針
資料6. ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針
<資料1.・2.の要綱及び運用について>
委 員
資料1について、⑶パワハラの場合には「職場内外における」という記載があるが、⑷マタハラの部分については、「職場において」という記載になっている。
マタハラはパワハラとやや似ている部分があるので、マタハラも「職場内外」という文言にしたほうがいいのではないか。
事 務 局
想定では、妊娠、出産等々によって「職場環境」を悪化させるというところや「制度の利用に関して」という部分があったので、職場外もあるのかと考えたが、想定ができなかった。今はその記載にしているが、もう一度事務局で職場外のことが想定されないのか考えたい。
会 長
パワー・ハラスメントのところに「職場内外」と書かれているのは、例えば市役所の中だけではなくて、職場の宴会等、建物の外でもパワハラになることがあるという背景があって、「職場内外」と記載しているということでよろしいか。
事 務 局
物理的な職場のほか、宴会等もあるが、市役所は事業者に色々な工事や物品等の発注者としての立場もあるので、こういった立場を利用してというところもあり得るのではないかと思っている。この2点が含まれるということで、「職場内外」という記載にしている。
<資料3~6の各指針について>
委 員
資料3の第3についてだが、国の指針で「限定列挙であり、全てを表すものではない」という文言があるが、そういう文言が必要ではないのか。
また、最近手軽に写真を撮れる状況になっているので、線引きは難しいが、「性的な関心や欲求に基づく」という前提があるので、「写真」に関することも載せたほうがいいのではないか。
事 務 局
まず1点目だが、「例えば次のようなものがある」と記載しており、これ以外にもあるということは、分かってもらえるかと思っているので、この点については、原案の通りとしたい。もう1点の写真については、盛り込む方向で考えたい。
委 員
資料3の第3の1⑵「セクシュアル・ハラスメントに対する行動をためらわないこと」で、書かれていることはもっともだが、「自分に落ち度があった」とか「隙があった」という部分でなかなか声を挙げられないこともあると思うので、そういったところも加えた方がよい。
あと資料4だが、制度の利用によってバランスが崩れることでハラスメントが起きがちであるので、制度は誰もが利用できるという、制度の利用を積極的に推進するための相互の意識づけを育むといったところがあるとよい。
一つ質問だが、こういったことを相互に意識するために年に1回研修を受けなければならないということがあるのか。
事 務 局
まず資料3で、自分に落ち度があったのではないかと考えがちということは、事例としてあった方がいいので、追記したい。
資料4は、制度を運用すべき土壌を作るというところで、女性活躍のための特定事業主行動計画においても、休暇、休業等、管理職も意識をもって使えるように、管理職側の認識も大事であるということは盛り込んでいるので、この指針の上でも整理したい。
もう1点研修についての質問だが、厚労省が作成している事業主全体に向けた指針では、年に1回という回数までは規定はされておらず、研修を行い職員に対して周知等を行っていくという規定がされている。長崎市では要綱の第5条で研修等の規定をしているが、新しく管理監督者になった者や新規採用職員を中心にハラスメントの研修を実施している。
会 長
先ほど制度を利用する土壌を作るという話が出たが、制度の周知は具体的に市ではどのようにしているのか。
事 務 局
妊娠・出産に限ったことではないが、職員の勤務条件の部分も含め、庶務の実務に関しては各課の庶務担当を中心に研修をし、そこで周知をしている。
他にも、職員互助会という仕組みがあり、職員が掛け金を払って給付を行っているが、出産時の祝い金給付の際にも、制度を通知している。
委 員
資料3の第1の1⑷人事院の指針で「女性を劣った性として見る意識をなくすこと」という書きぶりになっているが、例えば⑶だと「相手を性的な対象としてのみ見る意識をなくすこと」で「相手を」という文言もあるので、ここは「女性」に限らず、「相手を」という書きぶりであってもいいのではないか。
事 務 局
ご指摘のとおり、セクハラの指針ができたのが、男女共同参画や男女雇用機会という背景があり、従前から「女性を劣った性として見る意識をなくすこと」という文言であるが、最近は認識の変化があっているので、過去からの経緯や立法の意図を事務局で調べたうえで、整理したい。
会 長
以前は、男女というだけであったが、最近はLGBTの問題も出てきているので、必ずしも男女だけの問題ではない。その点も加味して検討してほしい。
委 員
資料6の第1の1の3に「秘密を厳守すること」という個人情報のことが書かれているが、相談をしたことによって、相談者の不利益になることはないという、情報の適切な取扱いに関することが読み取りにくい。個人情報が書かれたデータの取扱いや紙媒体の紛失とか、そういったことを含めたほうがいい。
事 務 局
おっしゃるとおり、読み取りにくい部分があるので、表現をこちらの方で工夫をしたい。
委 員
資料6の第3⑶で「被害者に対して指導・助言をする」という文言があり、加害者に対する指導というのは分かるが、被害者に対して、相談員が指導という立ち位置をとるのが妥当なのか、表現が気になった。例示の内容を見ても、「助言」というのが妥当であると思う。
事 務 局
おっしゃるとおり、実際のところ、相談員からは助言をしていることが圧倒的に多いと思うので、助言が前に出るかたちに改めたい。
委 員
相談員は相談を受けるにあたって何か研修を受講しているのか。
事 務 局
相談員になった人は全員ではないが、機関は定かではないが研修を受講し、相談員等の中で周知をしている。
会 長
今回の意見については、事務局の方で検討し、次回までに反映するということでよろしいか。
事 務 局
整理したい。
(14:00 -閉会-)
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く