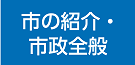ここから本文です。
令和5年度第3回 長崎市入札監視委員会
更新日:2024年8月7日 ページID:042486
長崎市の附属機関について(会議録のページ)
担当所属名
理財部契約検査課
会議名
令和5年度第3回長崎市入札監視委員会
日時
令和5年11月21日(火曜日) 13時30分~
場所
議会第1委員会室
議題
1 抽出事案について
審議結果
1 抽出事案について
(1)女の都3丁目(径50・30粍)配水管布設工事
【委 員】本件は、入札参加承認者数4者に対し、同日落札2者や入札不参加1者があり、結果的に最終入札者数1者、落札率100%での落札となっている。同日落札の2者については、未開札とのことであるが、契約検査課で入札金額は把握しているのか。
【事務局】同日落札者については、入札金額は確認していない。
【委 員】本件落札者が100%で落札できた理由はどのように考えているか。入札不参加者に対するヒアリングは行ったのか。
【事務局】不参加者に対するヒアリングは行っていないため、不参加の理由は分からない。同日落札の2者については、金額は把握していないが、入札は行っていることから、一定の競争性が働いた上で、公正な競争が行われたものと考えている。
【委 員】競争入札であるため、一般的には91%~93%の間で入札することが多いと思うが、結果的に本件落札者が100%で落札していることに少し疑問を感じる。同日落札の2者の入札額が分からないので何とも言えない部分はあるが、契約検査課ではこの入札結果に疑問は感じないのか。
【事務局】過去に、事業者に対して、100%で入札した理由について聴取したことがあるが、その理由としては、「金額的に厳しいが、予定価格の100%であれは受注できる。」という場合か、「必ず落札したい工事ではないが、100%での落札なら、受注してもよい。」という場合の2つのパターンが述べられることが多い。
各入札参加者は、他者の入札状況が一切分からないなかで入札に参加している。本件は結果的に1者応札で落札率100%という結果になったが、4者の入札参加承認者がいるなかで3者が応札しており、一定の競争性は確保されている。また、落札金額についても、最低制限価格から予定価格の範囲内であることから有効なものと考えている。
【委 員】同日落札の場合には開札をしないとのことだが、何かできない理由があるのか。本件の場合、同日落札の2者が落札者よりも低い金額で入札していることが分かれば疑念はなくなると思う。
【事務局】同日に別の案件を落札した者の入札は無効とする取扱いとなっているため、開札していない。
【委 員】無効であっても、金額を把握してもいいのではないか。
【委 員】公正な入札が行われたということを事務局できちんと把握するスタンスで検討してほしい。
【事務局】検討したい。
(2)宮摺地区送・配水管布設工事(その4)
【委 員】入札参加承認者数15に対して入札者数1となった理由はあるのか。
【事務局】入札参加業者へ聞き取りを実施した結果、受注している他の工事との調整により、作業員の確保が困難であるとの回答を受けている。また、当工事区間には、幅員が狭小な里道に水道管を布設する箇所が含まれており、当該箇所は人力による布設・土工を伴う施工内容となる。このことから現場環境は、他工事と比較すると条件が悪い方であると考えられる。
【委 員】例えば10者以上など、ある程度の入札参加承認者数に対して、入札者数0となった案件はあるのか。10者以上など、ある程度の入札参加承認者数に対して、入札者数が0になった件数と1になった件数を比較したときに、極端な差があれば確認した方がよいかもしれない。
【事務局】入札参加承認者数が10者以上で入札者数が0となった案件を確認したところ、令和5年度はなかった。令和4年度においては2件あり、それぞれ入札者数が0となった理由については、人力工事等で施工条件が悪いことや、市街地の夜間工事で技術者を確保できないことが挙げられた。
【委 員】人力施工の場合、予定価格の積み上げはあるのか。
【事務局】機械施工、人力施工それぞれの歩掛があるので、人力の場合はそれに応じた歩掛で積算している。
【委 員】本件落札者は、施工現場に近い事業者なのか。
【事務局】市内業者ではあるが、施工現場は長崎市南部であり、本件落札者の事業所は長崎市西部所在のため、それほど近いわけではない。
【委 員】入札参加申請と実際の入札までの期間について伺う。
【事務局】毎週火曜日に公告を行っており、事業者は翌週の火曜日を期限に入札参加申請を行う。その後、500万円未満の案件は入札参加申請期限と同じ週の金曜日に開札、500万円以上の案件は入札参加申請期限の翌週の金曜日に開札を行っている。
【委 員】作業員が確保できないことなどを理由に入札に参加しなかったという事業者がいたとのことだが、入札参加申請から開札日までの短期間で状況は変わらないのでは。なぜ人員確保について事前に検討した上で入札参加申請をしないのか。
【事務局】あまり熟考せずに一応入札参加申請して、入札参加申請後、現場を下見した上で辞退・不参加をする事業者がいる。事業者には安易に入札不参加を選択するのではなく、きちんと辞退届を提出していただけるよう行動を転換させるなかで、じっくり考えて入札参加申請をしていただくような対策を検討している。
【委 員】そうしていただくことで、お互い仕事が減ると思う。事業者においては、入札参加申請についてしっかり検討して、一定の入札参加の見込みがあるときにだけ行っていただくことを原則とするべきではないかと思う。
【委 員】入札不参加者への対応については、検討を進め、今年度の報告書内に盛り込んでほしい。
(3) 琴海南部浄化センター汚泥脱水機整備工事
【委 員】本件は随意契約方式によるものであるが、他の案件と比して決定率が非常に低い(74.42%)。事業担当課による積算と、事業者の積算額が大きく離れている理由を伺いたい。
【事務局】予定価格における資材や人件費等(機器費・複合工費が該当)は、製造メーカーからの見積書をもとに、「プラント設備機器等の見積による運用指針」より査定し、積算している。請負代金内訳書と本市の設計を比較したところ、諸経費に大きな差が見られた。
諸経費については、積算基準(下水道用設計標準歩掛表)による経費率にて積算しているが、落札者においては、独自の経費率で算出されているものと思われる。この差が本件の決定率につながっているものと考える。
【委 員】諸経費で200万円近くの差が出ていたということか。
【事務局】そうである。
【委 員】なぜ諸経費にここまで差が出たのかヒアリングはしたのか。
【事務局】ヒアリングはしていないが、推測するに、現場ハウスも置かず、工場に持ち帰りなどせずに現場において短期間で作業を行ったため、経費が抑えられたものと思う。
【委 員】諸経費の差について、契約検査課としてはどう考えるか。
【事務局】昨年度、類似案件の事業者にヒアリングをしたところ、当該事業者は公共の積算体系を知らず、民間企業から求められたレベルの見積書を提出しているとのことであった。行政の積算は国の基準を用いているが、それが適正であるかどうか、積算に関して改善する余地がないか、今後の課題であると考えている。
【委 員】予定価格の設定が実勢とかなり離れているように思うが、予定価格や決定率は公開するのか。
【事務局】契約後に公開する。
【委 員】随意契約ではこのくらいの決定率で契約しているとなると、工事品質の確保や適正な利潤の確保といった、一般競争入札における最低制限価格制度の意義に疑義が生じることとなるのではないか。予定価格と実勢が乖離しすぎないようにすべきだと思う。
【事務局】一定の技術力があり、その1者しかできない工事であることから随意契約するものである。工事品質も確保できることから、最低制限価格は設けていない。ほかの市町でも、特定の1者しか施工できない場合の随意契約においては、最低制限価格は設けていない。
【委 員】随意契約に最低制限価格を設けてない趣旨は理解できるが、随意契約であれば予定価格と決定金額がかけ離れていても問題ないとなると、一般競争入札で最低制限価格制度を用いる根拠が薄れてしまうのではないか。予定価格が実勢とかけ離れているということであれば、その出し方を見直すべきだと思う。
【事務局】確かに、本件においては、随意契約の決定率が本市の最低制限価格率と20%程度離れている状況であり、こうした状況については他都市調査も含め整理する必要があると考える。
【委 員】予定価格積算における経費率を過去の実績に基づいて決めることはできないのか。
【事務局】本件の事業者に関しては、前回の実績が10年ほど前のものであり難しいが、近年に実績があれば活用できる可能性はあるかと思う。他都市調査や下水道ブロック会議などを通して研究を重ねていきたい。
(4) 西部下水処理場自家発電設備改築工事
【委 員】1者応札で落札率100%になることはある程度想定されたか。
【事務局】本工事の入札参加条件として定めている公共工事実績を確認すると、長崎市で本工事の代表構成員となれる業者は8者、その他構成員となれる業者は14者いることから、最大7組の3者JVが応札可能であることを確認していた。よって、競争性は十分働くと考えていたため、1者応札で落札率100%になることは想定していなかった。
【委 員】応札者数を増やす何らかの取り組みはしたか。
【事務局】入札参加要件としては、自家発電設備は下水道施設に限らず設置されるものであるため、下水道施設用としての要件を加味しておらず、また、民間事業者での実績でも良いこととした。
【委 員】1者が入札否認されたことについて伺いたい。
【事務局】JVの構成員のうち1者が、直近1か月以内に1億5千万円以上の工事を落札していたため否認した。
【委 員】競争性の確保が難しいなかで、1億5千万円以上の工事に関する落札制限にはどのような必要性があるのか。
【事務局】大規模工事はどこの会社も受注したいなか、年に何回も同時期に同じ事業者が受注すると、市内業者の適正な育成ができなくなるため、多くの事業者に分散して受注していただけるようこの落札制限は必要である。
また、長崎市内では、市庁舎、西九州新幹線、長崎駅前の商業施設等の大型工事も一段落し、仕事量も全体としては減ってきている。そのような中、今年は昨年より不調も減少してきている。
従って、この落札制限は存続すべきと考えている。
【委 員】最大7組のJVの応札を想定していたとのことだが、この程度の数であれば、市内の事業者がJVの構成の協議を行う中で情報交換がなされ、誰が入札参加したのかが分かりやすい状況になり、その結果、100%で落札できるとの考えに至ったとは考えられないか。100%での落札が悪いというわけではないが、このように大規模工事で入札参加者が少なくなると想定される場合は、適正に競争性が確保されているか気を付けた方がいいかと思う。
【事務局】本件のように、想定していたよりも応札者が少なかった場合は、何が問題だったのか、業界の仕事量の状況等について調査していくべきだと考えている。談合については、一般的には、談合に関する情報を得た場合には直ちに公正取引委員会に通報することとしているが、今の段階では、応札しなかった者にその理由を聞いていく方法が適切と考えている。
(5) 市営横尾アパート2棟横児童遊園ブランコ設置工事
【委 員】再度公告となっているのは、予定価格が1,302,000円と低く人気がないからか。
【事務局】入札不調となった1回目の入札参加承認者3者に聞き取りを行ったところ、入札を見送った理由について、「工事の規模が小さかったため入札を控えた。」旨の発言ほか、「作業員の確保が難しかった。」「下請けの確保が難しかった」などの発言も見られた。
【委 員】予定価格を変えずに再度入札を行い、工期も繁忙期である10月を含んでいるが、今回4者から応札があったようである。何か考えられる要因はあるか。
【事務局】年に6件の落札制限の適用除外としたことが要因として考えられる。
(6) 東望海岸高潮対策工事
【委 員】入札者数が増えれば落札率が低下した可能性があったと考える。
入札辞退に関しては、「入札参加辞退届」が整備されており、辞退理由が収集されているようだが、入札不参加に関しては、そのような書式が整備されていないのか。入札不参加についても、事業者の状況や意向を収集するために 似たような書式を整備し、事後的に提出させてはどうか。
【事務局】入札辞退届の様式をホームページ上に掲載しているが、こちらは紙での入札の場合に使用するものである。電子入札における辞退届には、辞退理由を記載する欄を設けておらず、辞退届を提出する時点では辞退理由を収集する形にはなっていない。しかしながら、辞退理由については、入札事務の円滑化のために収集すべきであり、今後、電子入札システムの見直しを進めるなかで、検討事項としたい。また、入札不参加については、本来辞退届を出すべきものなので、不参加やその理由を届け出る書式等はないが、入札に参加しない場合は、辞退届を提出するよう注意喚起していきたいと考えている。
なお、入札不調など次の対応を考えなければならない事案があれば、必要に応じてヒアリングを行い、辞退や不参加の理由の収集に努めるようにしている。
【委 員】入札参加承認者数は8者であるものの,実際に入札したのは1者のみ。落札率も高い。どのような工事だったのか,また8者中7者が辞退または不参加だった理由を確認したい。
【事務局】本件において入札辞退又は入札不参加を行った7者にその理由を聞いたところ、下請け業者が見つからなかったこと、擁壁築造や消波ブロックの設置の海中作業となる部分は、風による波の影響を受けることから施工条件が厳しくなるなどの理由があった。
また、本件については、過去の類似工事と比較すると作業規模が小さいことも応札者が少なかった一因ではないかと考えている。
【委 員】施工条件が厳しいことなどは入札参加申請前から分かるのでないか。繰り返しにはなるが、やはり安易に入札参加申請が行われすぎているように思うし、入札に参加しないのであれば、少なくとも辞退届は提出すべきであると思う。
【委 員】入札不参加者に対する対応については、契約検査課で検討していただきたい。
(7) 山里小学校校舎大規模改造外壁工事
【委 員】内訳書の不備により失格となり、落札者が次点の入札者となっていることについての質問であるが、
・内訳書とは、どのような目的で提出させるのか。
・「内訳書の不備」は、入札手続きの流れのどの時点で把握するのか。
・入札参加業者が「内訳書の不備」に自ら気づき自ら補正することは可能か。
・僅かな「内訳書の不備」であっても失格と扱いとなるか。
について伺いたい。
また、これは意見になるが、今後、「内訳書の不備」が増加するようなら、入札事務適正化のためにも注意喚起をされてはどうかと思う。
【委 員】本件における内訳書の不備とは、どのような内容だったのか。
【事務局】内訳書について、明らかに端数処理を行ったものであるなど、積算の過程を伺える場合は有効としているが、本件については、工事内訳書内の金額を積み上げた金額が入札額と合わなかったため、内訳書の不備と判断している。
【委 員】内訳書の提出のため、内訳書内の金額を調整しなければならないとなると、事業者に余計な仕事をさせているように感じる。入札書の金額と内訳書の金額が一致しなければならない理由はあるのか。
【委 員】ほかの自治体でも内訳書を求めているのか。
【事務局】「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」で定められているため、必ず提出してもらっている。
【委 員】内訳書の趣旨は、適正に積算が行われていることを確認するためのものであり、入札書の金額と内訳書の金額が一円単位で一致している必要はないのではないか。
【事務局】内訳書の取扱いについて、内訳書を提出させる趣旨を踏まえ、国の指針等も確認しながら検討させていただきたい。
【委 員】内訳書に不備があると、入札が無効になるのか。
【事務局】無効である。
【委 員】入札が無効となる根拠規定はあるのか。
【事務局】公告文11(1)において、「入札に関する条件に違反した入札」は無効であると規定している。
【委 員】国の指針には、「金額の相違が著しい場合は入札無効」とあるが、多少の金額の相違が「著しい相違」にあたるのか。
【委 員】公告文に無効に係る記載があることは分かるが、一円単位の相違でも無効とする取扱いをこのまま継続するのか。継続するのであれば、より明確に示すべきかと思うし、個人的には、一円単位の相違まで無効とする必要はないのではないかと思う。この部分については早めに検討したほうがいいと思う。
【事務局】検討したい。
(8) もみじ谷葬斎場電気集塵装置(11号、小型炉)改修工事
【委 員】こうした心理的負荷のかかる工事を引き受けてくれる業者は県内にはおらず、東京都の1社しかない、ということか。また、遠方の業者を選定する経緯等を知りたい。
【事務局】本工事の対象であるもみじ谷葬斎場の排ガス処理設備は、平成20年度から平成22年度の3か年にかけて、本工事の受注者により施工されたものである。
排ガス処理設備は、火葬炉からの排ガスに含まれるばいじん等の有害物質を回収し、基準値以下に低減した後に大気中に放出するための設備である。本工事では、排ガス処理設備の主要部である電気集塵機の整備を行い、性能を維持することを目的としている。電気集塵機の部品や資材はメーカーである高砂炉材工業のみが供給できるほか、分解および組立施工に必要な詳細図面や技術情報、ノウハウも同社のみが保有している。本工事の受注者以外の者に施工させた場合、電気集塵機の性能保証が得られないだけでなく、火葬炉の使用に著しい支障が生ずる恐れがある。
以上の理由により、本設備の製造・設置メーカーであり、施工時及び施工後の対応について一元化した責任体制をとることが出来る唯一の事業者である本工事の受注者と随意契約している。
なお、もみじ谷葬斎場火葬施設内の工事であっても、一般的な設備や汎用機器に関する整備工事、改修工事に関しては、制限付一般競争入札を行っており、市内の事業者も参加している。
(9) 西泊地区子育て支援センター新築電気工事
【委 員】6者が入札したものの、最低制限価格率が上限に近くなったため,落札者以外の5社は最低制限価格未満で失格となり、落札率も高くなっている。
【事務局】予定価格は契約上の上限価格ではあるが、市場の標準的な工事価格であり、本件落札額は予定価格と最低制限価格の範囲内であるため問題のない落札であると考えている。
【委 員】結果に問題があるわけではないが、安い金額で受注したい事業者もいるのに、予定価格の付近で入札した事業者に決定するような結果になるともったいないように感じる。このような結果をできる限り減らすような方策について、検討すべきだと思う。
【委 員】入札制度においてはどうしてもこのような事象が起こりうるということも認識した上で、今後も議論していく必要があると思う。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く