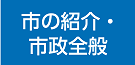ここから本文です。
令和5年度第3回 長崎市入札監視委員会
更新日:2024年8月7日 ページID:042487
長崎市の附属機関について(会議録のページ)
担当所属名
理財部契約検査課
会議名
令和5年度第3回長崎市入札監視委員会
日時
令和6年2月7日(水曜日) 13時30分~
場所
議会第1委員会室
議題
1 抽出事案について
2 指名停止について
審議結果
1 抽出事案について
(1)「東部下水処理場No.1汚泥脱水設備改築機械工事」
【委 員】1者入札で、落札率も極めて高い。同日に入札が行われた電気工事も同じ状況である。このような状況が事前に想定されたのかを確認したい。
【事務局】発注前にコリンズ(工事実績情報システム)を用いて本工事へ入札参加可能である業者が複数いることを確認しており、競争性は十分に働くと考えていたため、1者応札で高落札となることは想定していなかった。同日に入札が行われた「東部下水処理場No.1汚泥脱水設備改築電気工事」においても、同様に確認を行っており、1者応札で高落札となることは想定していなかった。落札率が高くなった原因については、受注者に聞き取りした結果、工事費に占める機器費が大きな割合を占めるため、メーカーとの価格交渉がうまくいかず価格が下がらなかったと聞いている。
【委 員】また同じような案件が出てきたときに同様の結果になりかねない。何か対策は考えられるか。
【事務局】応札者が少なかったことに関しては、ヒアリングの結果、技術者不足や工期が3年と長いことが要因と見られた。工期の短縮などは容易なことではないが、極力事業者のニーズに合った内容になるよう研究していきたい。
【委 員】工期が長いことにより、技術者を一定期間確保しなくてはならないことが応札の支障となっているのか。
【事務局】そういった理由もあると思うが、そもそもの技術者数が少なくなっている。そのためよりよい条件の案件を優先的に受注しているということだと思う。
【委 員】技術者不足により他の案件が優先されたとのことだが、事前に応札者がこの1者だけではないかという予測はついていなかったのか。
【事務局】予測していなかった。金額が大きな工事であることから、工期が長くても一定数実績のある事業者が参加してくれるものと想定していた。
【委 員】本工事で設置されたスクリュープレス脱水機について、特殊な機械かと思うがメーカーは何者くらいあるのか。
【事務局】メーカーは6者ある。
(2)「船石ポンプ場ほか電気設備更新工事」
【委 員】最低制限価格の決め方について疑問がありお尋ねしたい。長崎市の最低制限価格率は小数点以下2桁までで算出されており、本件では92.76%となる。入札執行書の6番目の入札者の入札率は92.76%で最低制限価格率と一致しているが、金額で見ると同者は最低制限価格未満となり失格となっている。最低制限価格の決定に係るルールはどのようになっているのか。
【事務局】最低制限価格率の計算方法は公告文の(8)に記載しているが、予定価格に最低制限価格率をかけて、小数点未満を切り捨てる計算方法となっている。本案件では、最低制限価格が2,600万628円であり、6番目の入札者の入札額2,600万円は入札執行書上の最低制限価格率で見ると一致しているが、金額で見ると端数の628円分下回り、最低制限価格未満となっている。
(3)「元船町・出島町(径700粍)配水管推進工事」
【委 員】高額な工事にもかかわらず、3者が入札辞退をしている。3者の辞退理由について伺う。
【事務局】通常、落札された案件については辞退理由の確認はしないが、本件が抽出されたにあたり辞退した3者にその理由に係る聞き取りを行ったところ、いずれも「下請け業者の確保が困難だった。」旨の回答を得ている。本件はトンネルを掘るような手法で水道管を布設する専門的な工事になるため、それに対応できる下請け業者を確保することが難しかったようである。
【委 員】本件工事で入札辞退した3者の入札参加業者(JVを組んだ各事業者)は、本件工事の下請け業者になることについての制限があるか。
【事務局】本件工事は制限付き一般競争入札のため、下請け業者の使用に関する制限は特にない。ただし、指名競争入札の場合は、同一工事の指名業者を下請け業者として使用することは可能な限り避けることとし、止むを得ず使用する場合は、事前に契約検査課に届け出ることとしている。
なお、現在長崎市の建設工事において指名競争入札は行っていない。
【委 員】入札辞退する事業者から辞退理由は収集されないのか。
【事務局】現在の電子入札では辞退理由を収集する形になっていないが、辞退理由を収集することについては一定の意味があるかと考えており、現在検討しているところである。
【委 員】入力項目を増やすことは難しいことではないと思うので、ぜひ検討願いたい。
(4)「東山手・南山手地区案内・誘導サイン設置工事」
【委 員】案内・誘導サイン設置工事で、見積額にこれほどの差(92%、100%)があるのはなぜか。
【事務局】入札金額について、落札した事業者と最低制限価格未満であった事業者に聞き取り調査を行った。聞き取り結果から、両者とも最低制限価格付近の金額でも施工は可能であったことが分かったが、工事規模が小さかったこともあり、利益の幅をどう考えるかという両者の方針の違いにより入札金額に差が生じたものと考えられる。
(5)「長崎駅東口駅前広場内径800粍汚水管移設工事」
【委 員】入札参加承認者数18に対して入札者数1という結果になった理由について伺いたい。
【事務局】入札参加承認を受けたものの、入札を行わなかった事業者のうち数者に聞き取りを行ったところ、入札を見送った理由について、夜間施工であること、掘削時の地下水対策が必要であること、既設管の加工が難しいことなど、施工上の制約が多いことが挙げられた。また、同日の別の工事案件に入札することとした旨の回答も見られた。
【委 員】過去にも同じように多数の入札参加承認者がありながら、応札者が少ない結果となった案件があったかと思うが、それらと本案件とで共通する特徴のようなものは見られるのか。
【事務局】本案件の特徴として、夜間工事であることのほか、現場が輻輳していて工事が難しい、他工事等との調整が必要、長崎駅周辺の再開発工事であり、事業期間が限られていることなどがある。本件と同じような入札結果となった案件をいくつか抽出したところ、やはり夜間工事であることや他の工事と輻湊しており施工が難しいといった共通の特徴が見られたことから、こうした条件が重なると同じような入札結果となりやすいのではないかと考えている。
【委 員】こうした応札者の少ない案件があることにについて、対策はあるのか伺いたい。
【事務局】本件はたまたま入札不調にならなかったが、全国的に人手不足で不調が多いなかで、不調が予想されるものは、例えば発注ロットを大きくしたり、積算のやり方を見積りにしたりするなどして、現場の実状に合わせることにより、参加意欲を高めるようにしていくべきだと考えている。また、積算や発注に関するヒアリングを行ったり、入札参加者が少なくなることが見込まれるときには、発注基準のランクを広げ、対象となる事業者を増やしたりしていくことも必要であると考えている。
【委 員】公告から入札までの期間について伺いたい。
【事務局】毎週火曜日に公告を行っており、事業者は翌週の火曜日を期限に入札参加申請を行う。その後、500万円未満の案件は入札参加申請期限と同じ週の金曜日に開札、500万円以上の案件は入札参加申請期限の翌週の金曜日に開札を行っている。
【委 員】とりあえず入札参加申請した上で、後から実際に応札するかどうか判断する事業者もいるのではないか。公告から入札参加申請までの期間をもう少し長くすれば参加率も上がるのではないかと思った。
【委 員】比較材料として示された別冊資料の案件(滑石3丁目・滑石4丁目(径75粍)配水管布設工事)は落札率が低く、きちんと競争しようとする意志があるように見えるが、審議対象の本案件は高めに応札したところ、たまたま落札できたというような状況であり、入札結果としては別物という気がする。どちらかというと別冊の案件の方が、落札者は91~93%の間で入札できているのに他の事業者は入札しなかったのかが気になるところではある。
(6)「グラバー園エスカレータ・トラベータ年次改修工事」
【委 員】本工事の受注者が、79.83%という著しく低い決定率で落札している。他の随契事案11件と比較しても、また同者が落札した他の3件と比較しても、その差は顕著である。その要因について、説明してもらいたい。また、過去に同者もしくはその系列会社が行ったグラバー園エスカレータ・トラベータ改修工事につき、予定価格と決定金額にどの程度の乖離があったのか知りたい。
【事務局】本工事は、年次改修計画に基づき複数年にわたって改修工事を行っている。
過去3か年の決定率は、95~98%程度に収まっており、本工事を除いて決定率に大きな差はなかった。
本工事を含む随意契約工事の予定価格については、次の手順にて積算を行う。まず、工事内容、作業項目、作業量および施工条件について、随意契約を予定している業者と打ち合わせを行い、これに基づいて工事見積書を提出してもらう。例年の工事や他の業者に発注した類似工事の入札結果を参考に、提出された工事見積書に査定を行って適正と思われる直接工事費を算定する。この直接工事費に、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事積算基準」に基づいた諸経費を加算し、予定価格を算出している。この設計手法は随意契約を予定しているすべての工事で同様に行っている。
本工事が他工事に比べてかなり低い決定率で落札していることについてお尋ねであるが、積算の根拠となる工事見積書が比較的高かったことが考えられ、その原因について受注者に問い合わせたところ、次のような説明を受けている。
本工事では観光施設を営業しながらの施工となるため、他工事に比べ施工時間の制約がある。一方、昇降設備業界の技術者不足が全国的な問題となっており、本工事においても技術者・作業員の確保が難しい状況が続いている。設計時点では、全国の他の工事案件との調整から、まとまった期間に集中して技術者・作業員を配置することが困難な状況で、現場の入場回数を複数回に小分けして施工する計画で積算しており、結果的に提出した工事見積書が高めにならざるを得なかった。その後、入札時期までに技術者・作業員の確保に目途がつき、作業の効率化が見込めるようになったため、再度積算を見直して入札に応じたとのことであった。
以上より、現在の昇降設備の技術者・作業員の不足状況を鑑みると、受注者も一定のリスクを考慮して見積書を作成せざるを得ない面もあり、今回やむを得ず予定価格と決定金額に乖離が生じたものと考えている。
【委 員】最初に出された見積りが高かった理由は今説明があったとおりで、作業の効率化が見込めるようになったため金額が下がったとのことだが、結果として20%近く下がっている。事業者が見積りをし直して結果的には安くなったのだとは思うが、当初出された見積りのとおりで工事すると言われたらその金額で契約するしかないのだろう。今後も継続的に工事していくことと思うが、最初に見積りをとるときに高く出てくる可能性はあるだろうから、その段階で金額を精査できないのだろうか。
【事務局】私たちとしても事業者との打合せにおいて、見積りがこれまでと比べて高めではないかと話はしていたが、技術者不足が深刻な状況にあることは認識していたため、やむを得ずこれまでよりも高めに予定価格を算出した。その後、事業者が積算をし直したとのことだが、私たちも何人の技術者が現場に入り、どのくらい作業をしているかなどは確認をしているため、事業者も適正な金額で見積し直したのだと思う。技術者不足は構造的な問題であり短期間で改善するものではなく、資材が高騰している状況もあるため、今後も見積額は高めに出てくることが考えられるが、金額を精査し、他工事やこれまでの工事と比較して高いと見られる場合は確認や指摘をしていきたいと思う。
【委 員】契約検査課としての見解はどうか。
【事務局】難しい問題であるが、市としては、建設業界の情勢等を把握しながら、設備課長が申したような監督業務の中で施工体制のチェックや確認を適正に行っていく以外に今のところ方策は見当たらない。
(7)「蚊焼小学校校舎屋上防水改修工事」
【委 員】19社が入札し、自由競争原理が健全に働いている入札結果だと思われるところ、一般的に「防水改修工事」というのは利益幅が大きいなど人気がある工事なのか。
【事務局】本案件を含め、一般的な学校の屋上防水改修は、平らな屋根に平場を塩ビシートにて覆い、パラペットなど垂直に立ち上がっている部分はウレタン塗膜防水と呼ばれる塗料を塗って改修を行っており、使用している材料や施工方法は一般的な改修方法である。発注工種は防水で、本案件の規模で入札参加資格のある業者登録数が多いことや、建物の屋根形状等も比較的単純で施工もしやすいことから入札参加者数が多かったものと思われる。
【事務局】防水工事の人気について、令和5年度(令和6年1月29日時点)は建設工事全体の平均入札者数約6.6者に対し、防水工事は約16.1者とかなり多くなっている。その理由としては、防水工事は民間で発注されることが多く、建築一式工事の一部として防水工事が発注され、防水工事の事業者は下請けに入ることが多いところ、長崎市は防水工事を単独で発注するため直接受注することができることから、入札者が多い傾向にあるのではないかと考えている。
(8)「西町小学校改築主体工事」
【委 員】本件のように規模の大きな工事は落札率が100%付近になりがちな印象があるところ、本件は2者応札であったため落札率が100%付近にならなかったようにも思えるがどうか。
【事務局】制限付き一般競争入札においては、他にどの事業者が入札参加しているか、何者が入札しているかなど一切わからない状態で入札が行われるため、1者応札だから必ずしも高落札になるというものではない。
【委 員】1者応札を防ぐために特別な取り組みをしたのであれば伺いたい。
【事務局】まず、大規模な工事が予定されているといった発注見通しの公表を行っており、事業者の方で事前に準備していただけること。さらに、大規模工事であるため3者JVを構成するという条件を付しているところ、代表構成員は最高ランクとしているが、その他の構成員の参加条件を緩和して、できるだけJVが組めるようにした。
【事務局】本案件は老朽化により校舎や屋内運動場を改築するもので、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積 6,000平方メートルを超える規模のものを新たに設ける工事である。使用材料は一般的な材料を用い、特殊な材料や工法等は採用せず、通常行われている工法による施工が可能であることから、特別な技術を求めるものではなく、市内業者のみで工事を行えるよう設計をしている。
【委 員】一般的に、夜間工事や難しい工事になると入札参加者が減り、落札率が高止まりする傾向にあるということか。
【事務局】特殊な工事になれば、市内、県内問わず施工可能な事業者が限られてくるため、入札参加者が少なくなることはありえると思う。
【事務局】入札額が上がるか下がるかについては、民間工事の発注がどれくらいあるか、事業者の手持ちの工事がどれくらいあるかなど、そのときの事業者の状況にもよるかと思うが、夜間工事に関しては、下請け業者の確保が難しかったり、下請け業者に支払う金額が高くなったりすることなどから、入札者数が少なくなる、落札率が高くなるといった傾向はあると思う。また、スタジアムシティや長崎駅周辺はまだ大規模に工事中であるが、新幹線やJR長崎本線連続立体交差化事業、市庁舎建設事業、長崎駅前の商業施設などの長崎市の大規模工事が一定落ち着いたことも本件に起因していると思う。
【委 員】本件は約17億円の工事であるが、契約保証金として約1億7,000万円を納付しなければならないということか。また、納付した契約保証金は工事完成後に還付されるのか。また、市の工事について、履行保証保険を利用し、契約保証金の代替措置とできるのか。
【事務局】契約保証金は工事金額の10%の納付が必要であり、完成検査後に事業者に還付するものであるが、履行保証保険を利用すれば、事業者は契約保証金の納付の免除を受けることができる。本案件は議決後に本契約予定だが、その時点で履行保証が確認できれば、契約保証金が免除される形となる。
【委 員】議決後に本契約予定とのことであるが、債務負担行為の承認を受けるということか。
【事務局】予算はすでに承認されているが、地方自治法上、1億5,000万円以上の工事の契約に関して議会の議決を要するものである。
【委 員】小学校の改築工事であるが、児童らは仮設校舎に移るなどして授業を行いながら、新たに校舎を建造するのか。
【事務局】仮設校舎ではなく、既存の校舎を使用しながら、学校敷地内の広場に新たな校舎を建造し、完成後、新校舎に移ることとなる。
【委 員】夜間工事は行わないとのことだが、工事の作業音が授業の支障とならないよう、一般的に学校の工事であれば夏休みや夜間に行うものではないのか。
【事務局】作業時間は一般的な工事と同じく8時から17時までを原則としている。現場が住宅街に囲まれていることや、建物内部の工事ではなく新しく建物を建造する工事であることからも、夜間作業は原則行わないこととしている。工事の作業音については、建物を遮音シートで囲むことで、一定の防音対策を講じた上で工事を行う。通常、ほかの学校工事も同じように防音対策を講じた上で昼間に行っている。
(9)「神浦青年部事業所貸付施設ほか解体工事」
【委 員】最低制限価格率が93%の近傍となったため、92.45%で入札した者が最低制限価格未満で失格となり、100%で入札した者が落札した結果については、長崎市の入札制度上やむを得ないとは考える。
これまでの本委員会の審議においても、本件と同じように、最低制限価格率が93%の近傍となったため、最低制限価格率の範囲内で入札した者の多くが最低制限価格未満で失格となり、100%付近で入札した者が落札者となる入札結果については度々議論されてきたが、こうした事象については、ルールに従って入札を行った結果であり、公正性の観点からは問題ないと考える。しかしながら、そこに競争性は適正に確保されていると言えるのかということについて伺いたい。
【事務局】ランダム係数を用いて最低制限価格率を算出する現在の長崎市の入札制度には、抽選的な要素はあろうかと思うが、いまなお全国各地で談合等の事件があっている中で、長崎市では過去の事例も踏まえ、予定価格の事前公表を行っており、従ってランダム係数による最低制限価格率は必要と考えている。
しかしながら、現在、制限付一般競争で入札を行っており、入札への参加や入札額の決定などはルールの範囲内で自由に行うことができることで、一定の競争性は確保されていると考えている。
また、入札は入札者の受注意欲とは別に、客観的に落札者を決定するものであるが、本案件の落札者においても、少なくとも応札していることから、落札したいとの意思はあったものと考えられ、その応札額の決定の過程で、他の競争者の動向の予測や現場確認後の見積額、一般管理費での調整等の結果、100%での応札を決定したものと推察される。
ちなみに、本案件の一部である神浦青年部事業所貸付施設については、昨年度2回の入札公告を行ったが、入札参加者がおらず不調となった案件であり、少なくとも事業者が特に落札を希望するような工事案件ではなかったことから入札額が二極化する結果となったものと考えられる。
【委 員】釈然としない部分はある。案件(2)において他の委員が指摘されたように、入札額が最低制限価格よりも600円ほど低いことで落札できないということも起きている。参考資料として提示された別の案件(矢上小学校プールろ過装置改修工事)について、10者は91%から93%の最低制限価格率の範囲内で入札しているところ、1者が98%で入札したために、ランダム係数が93%を上限に算出されることとなり、結果的に92.97%と高い率が出たことから、最低制限価格率の範囲内の入札者が全て失格となっている。仮に98%で入札した当該1者がいなければ、最低制限価格率の範囲内で最も高い入札率である92.89%を上限にランダム係数が算出されたはずである。各事業者が積算を行い、現在のルールどおり入札を行った結果ではあるが、案件(2)で議論となった最低制限価格の端数の取扱いの件も含め、今後も入札制度の研究を継続して行ってほしい。
2 指名停止について
質問等なし
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く