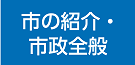ここから本文です。
令和5年度第3回 長崎市市民力推進委員会
更新日:2024年8月13日 ページID:042535
長崎市の附属機関について(会議録のページ)
担当所属名
市民生活部 市民協働推進室
会議名
令和5年度第3回 長崎市市民力推進委員会
日時
令和6年3月14日(木曜日)18時30分~
場所
長崎市役所7階 記者会見室兼中会議室
議題
議題1 市民協働推進室 事業体系・所管事業の状況について
議題2 市民活動団体に対する支援策について
審議結果
議題1 市民協働推進室 事業体系・所管事業の状況について
資料に基づき事務局から説明
【委員長】
事務局からの説明を踏まえ、ワークショップ形式で進めていきたい。事務局に進行をお願いしたいので、各グループで話をして各意見を発表していただきたい。
〇グループ1
・資料2 市民活動支援補助金の補助率に何の意味があるのか。全額補助ではだめなのか。
・市民活動センター事務室利用の出ていかれる団体の次はどういう行き先があるか。期限が来て市民活動センターを出られる状況になっていることがゴールだと考える。
・事務室の入居の条件は?金銭的に入らなくても大丈夫そうなところもある。入った後のサポートがあった方がいいのでは。
・長崎伝習所について、塾生も1万人を超えてすごいなと思う。長期間実施している事業なので、どんな効果が出ているのか教えて欲しい。
〇グループ2
・資料4 若者チャレンジ補助金について、18-30歳の30歳の区切りはなぜか。若者の定義は30歳から40歳など色々あると思う。もうちょっと広げていいのかなと。
・ケーブルメディアに関しては確かに時代の流れがあり見る人は少なくなっているだろう。動画配信でインフルエンサーの協力やtiktokなどをうまく宣伝するなど、やり方を工夫してみる。また、誰が発信するかも大事である。
・事務室については次のステップを考えるすごく大事なところだと思う。どうしたらニーズにかみ合う募集の仕方ができるのか。一般の事務室よりは廉価だが、シェアオフィスみたいな使い方もできるのではないか。
〇グループ3
・資料1 市民協働推進室の事業体系について、前回市民力推進委員会で行ったワールドカフェの意見を取り入れられてない。もう少し具体的に書いてあった方が良いのでは。
・資料2 予算額の執行額について、執行率が低いのは周知がうまく出来ていないのではないのかなと思う。ウーマンズウォークラリーなど参加者多いため、そういったイベントの中で周知をしてはどうか。
・資料3 指定管理の状況のなかで、利用者の年代の割合について知りたい。若者の参画の状況などがわかるのではないか。
・つながり事業、すごくいい取り組みだなと思う。呼ばれる3名は自分も知っているし、周りの若い人に周知できる。
【事務局】
補助金については、次の議題で取り上げるため、まとめてそちらで回答したい。
また、11月の市民力推進委員会でのワークショップのご意見については、令和7年度の見直しに向けてご意見を頂いたものであったため、掲載していない
【事務局】
事務室の基準については、基本的に補助金と同じ考え方で厳しい審査を行っている。今回事務室を出るところは、2団体は別の場所が見つけて決まっていると伺っている。事務局としてもずっと使っていただきたい気持ちもあることはご理解いただきたい。
また、今回の例でいうと、団体の方から事業を拡大していく中で活動場所は大きくなったものの事務室機能が足りなくなったというご相談があった。また、実際の財政状況をを確認した上で、審査会で決定したものである。
【事務局】
市民活動センターはもともとベンチャー支援施設だった。市民活動団体を支援するにあたって、全国の状況を調査しながら、事務室やロッカー、ポストもあった方が良いのではと始めた。設置当時、かなり応募があった。内部でもかなりの議論があり、そこで3年間で自立できるようにというのが条件となった。なんとか自立を促すため、補助金などを整備していった。補助金というのは足りない分を補助するという趣旨で、現在の補助率となった。佐世保などでも廃校を貸し出す取り組みをしていたが、現在は閉館している。事務室の需要はやはり減っているのが実情。学校や空き家などを市民活動団体に貸すとなると、市民活動団体が事務室を借りたくても借りられない、需要が一定あるという状況にならないと厳しい。
【委員】
ランタナの事務室を借りると、相談など手厚く対応していただけるなどメリットがある。どんどん広まってほしい。
【事務局】
出ていく団体が自立を目指したセンター。しかしながら現実的に難しいことも理解している。特に福祉関係の団体は利用者からお金をもらうのが難しい。自立支援が目的ということは理解してほしい。
【事務局】
伝習所は38年間で1万人を超える塾生がいる。伝習所は比較的自由な仕組みになっており、NPO法の縛りがあるようなミッションがあるような団体とは少し違う。ウーマンズウォークラリーは伝習所開始の2年目の紅塾として活動しており、グラバーパイプバンドの前身のバグパイプ塾など伝統の継承を行っているような塾もある。また、地球館の運営を行っていた国際塾や生ゴミシェイパーズなどもあった。昔は、大学の教授などが塾長になっていたり、塾数も多いなどかなり活発だった。伝習所から市民活動団体に移行していただけると、事務局としてもすごく嬉しいところはある。全部が全部大きな成果につながっているというわけではない…
【委員】
伝統があり色々な取組をやっているので、もっとアピールしてもらえれば。
【委員】
塾長の募集期間を長くしてもらえると応募したいという声があった。
【事務局】
あくまで若い人の活動を応援したいという趣旨である。伝習所の塾活動はまちづくりのリーダーを育成する場と考えている。若者チャレンジ補助金は、塾活動は公募で集まる塾生の年齢構成も様々であり人間関係が大変という声など、若い世代の代表者には塾運営のハードルが高いという意見もあり、令和3年度から若者向けの補助金を創設した。
動画については、全庁的な取り組みとしてもショート動画など新しいやり方を取り入れていく方針ではある。
【委員】
紹介してほしいという団体があったら市民協働推進室に言えばいいのか。
【事務局】
まだ現時点で詳細は決まっていない。今後検討していく。
【事務局】
市民活動センター利用者の内訳については、直近2月の状況として高齢者が50%、10~30代の若者の利用が24%。月によって変わっており、8月は若者の利用率が43%となっており、前の指定管理よりは若者の利用割合は増えていると考えている。また、若者向けの交流会や相談会も実施しており、SNSなども活用しながら若者を取り込んでいこうと取り組んでいる。
【委員】
つながり事業のオンライン配信をする予定はないか。
【事務局】
今のところはない。配信、アーカイブについて講師と交渉してみる。
――――――
議題2 市民活動団体に対する支援策について
事務局から資料をもとに説明
【事務局】
今後の流れとヒアリング対象の企業について、各グループからご意見をいただきたい。
グループ3
・補助金が続かないと続かない団体は自立できていない。補助金がなくても、活動できるような自立する団体を支援したい
・なんでも使える補助金は、団体よっては何に使えばいいか分からないというのもある。なんでも使えるではなく、例えばホームページ作成など目的別補助金などを複数準備するのはどうか。
・市外の行政間でヒアリングをしてもいいのでは。外に出ていってもいいと思う。久留米などは長崎より協働が進んでいるため、参考になるのではないか。
【事務局】
自立というのはすごく難しい。受益者負担ができる分野とできない分野があり、特にできない分野については補助金や委託、寄付が必要なものもどうしてもある。しかし、自立が目的ということをご理解いただけて幸い。
グループ2
・補助率について、敷居を低くという話が合った。特にスタート補助金については敷居を低くしたほうがいいのでは。申請が少ないというのは採用率が高いチャンスだが、それでも申請が少ない。やはり、申請からプレゼンなどの手間を考えると若者はクラファンにいってしまうのではないか。そこでスタートとジャンプのセットメニューなどがあればどうか。
・他都市では複数年、2か年補助メニューなどあるところもあるのでそういったものがあってもいいと思う
・お金だけでなく、場所のメリットの提供があればいい。また、人的なサポートなどがあれば、エネルギーに見合ったメリットになるのではという意見があった。
・結構長く活動しているのになぜ補助金を使わないのかそういう団体に話を聞いてみたいと思う。そこに大きな鍵があるのではないか。
グループ1
・ヒアリング先は企業に加えて社会福祉法人などを追加してもいいのではないか。
・過去に補助金を利用した団体に聞いた方が良い
・方針を決定する前にもう一回会議をした方が良いのでは。もしくは、事前に資料を配布し、内容を把握した上で話をできればと思う。オンラインでもいいのではという話もあった。
・補助金については、成果が求められすぎているのではないかと言う意見があった。特に提案型協働事業。
・人材育成補助金20人以上はハードルが高い。
・成果に人数を求めがちであり、評価基準については検討が必要ではないか
・補助金の申請は面倒くさい
【事務局】
補助金の見直しはすぐにできるものではない。また、どうしてもできることできないことがある。現在事業補助はしているが、運営補助はこれに依存してしまうと自立が進まないため、現在行っていない。
【事務局】
委員会については、6月から9月の間にもう一回開催できるようにしたい。
【事務局】
もしいろんな企業や自治体などの情報があったら教えて欲しい。
今後もワークショップ形式を活用しながら、みなさんと意見交換を行いながらすすめていきたい。
【委員】
長年審査部会で見ているが、ニーズや動向が変わってきている。長い間見直しができていないため、見直しを行う必要のある時期にきており。忌憚のないご意見をいただきたい。当初は年間1回で計画していたが、今は予算があるからと何度か開催している状況。審査部会の委員も団体の概要や目的、申請事業の資料をもらって1件1件判断している。
補助金の申請はやはり面倒。自分の仕事上でもなかなか活用が難しいところもある。プレゼンテーションや報告会を聞かせてもらうが、なんとも言いようがない。よかったとは思うが、今の形式の報告会は必要なのかという疑問もある。
例えば3分なら3分で時間をかけて動画で思いを伝えてもらい、追加でプレゼンしてもらうというようなやり方もあるのかなと思う。事前に審査員も動画でイメージを共有して審査できるのかなと思ったり、色々考えられた。
【事務局】
委員の任期の関係でメンバーが変わる。新しいメンバーとも共有しながら、しっかり形にできればと思う。
【委員長】
他の会議などでは、すでにある程度形になった段階で委員として意見を求められることがあるが、それに比べて、この委員会ではこのようなワークショップなど委員の意見を広く聞いて、最終形を求めていく形はすごくいいことのように思う。
補助金に関してはおっしゃる通りだと考える。やはり、補助金の前段のニーズのリサーチ、サービスの効果測定やいわゆる顧客満足度はしっかり把握していったほうがいい。
これからもアンテナを張っていろんなアイディアも出していただければ。
【事務局】
今後の流れについては、10月11月ごろ次年度予算を編成するため、9月ごろまでに結論をだして一定の形にできれば次年度に反映することができると考えている。
【委員】
そういったできるだけ具体的なイメージを共有してもらえたら助かる。
- 以 上 -
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く