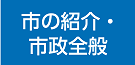ここから本文です。
令和5年度第2回 長崎市障害者施策推進協議会
更新日:2024年9月6日 ページID:042667
長崎市の附属機関(会議録のページ)
担当所属名
福祉部 障害福祉課
会議名
令和5年度第2回 長崎市障害者施策推進協議会
日時
令和5年11月28日(火曜日)14時30分~
場所
中央公民館2階 第4研修室
議題
⑴ 長崎市第5期障害者基本計画の概要等について
⑵ 長崎市第5期障害者基本計画素案の審議について
⑶ その他
審議結果
【事務局】
令和5年度第2回長崎市障害者施策推進協議会を開催する。本日の協議会は委員20名中16名の出席で、会議は成立している。議事進行を会長にお願いする。
【会長】
議事にはいる。議題1「長崎市第5期障害者基本計画の概要等について」、事務局から説明をお願いする。
【事務局】
(【資料1-1】障害者の状況及びアンケート調査結果の概要、【資料1-2】アンケート自由記述、【資料2】長崎市第4期障害者基本計画の振返り資料(全体)、【資料3】「障害者基本計画」及び「障害福祉計画」の策定について、に基づき長崎市第5期障害者基本計画の概要等について説明)
【会長】
今の説明に対し、質問、意見はないか。
【委員】
障害福祉センターの発達支援の充実について。今年の現時点での待機期間はどれくらいあるのか。また、診療後の療育については、待機することなく、適正な時期に適正な回数を行うことができているのか。
【事務局】
ハートセンター診療所の待機期間については直近では10か月程度で推移しており、想定以上に多く来られている状況。療育待機については、ハートセンターで診療を受けられた方はハートセンターで計画を立てて療育を受けられるので待機はない状況。ただ診療を受ける前に療育を受ける方はまだそんなにいないため、結果的に療育の開始が遅くなっているということは事実。ハートセンターの方でも、まず電話で相談があるので、その状況を見て、障害の特性によっては早期にした方がよい方がいるので、セラピスト等が事前の整理をしている。診療のあとに療育の時期が伸びているという状況はないとハートセンターからはきいている。
【委員】
ハートセンター診療所の待機期間について、月ごとに受付の人数は変わるが、約10か月ときいている。療育については比較的早い時期に適切な回数を、月2回くらいのペースでするということで、初診から必ずカンファを行って、早急に訓練に結び付ける努力はしているところではある。中には緊急性のあるお子さんや、超早期(乳児期の自閉症)のお子さんもいらっしゃり、ハートセンターのさくらんぼ園の超早期グループに入ってもらっている。ただやはり、入口の部分が10か月ということで、かなり長くなっているが、ただ、1歳半健診のあとでこられて、少し経過をみようという場面では、待っている間に療育というかたちではないが児童発達支援事業所を利用してもらったり、さくらんぼ園の待機児童のクラスを設定したりと、とにかく親御さんの不安を早くやわらげようという形でいろいろな取り組みはしているところではある。来年度、ハートセンター診療所に常勤医師が増えるということで、障害福祉課とも話をしている。それによりまた今後変わってくるのではないかと期待できる部分はある。
【委員】
アンケートについて質問が3つある。まず、誰に向けて行ったのか。基本的には本人に向けて案内したという理解でよかったか。
【事務局】
アンケートについては、障害者2000人に送ったものについてはご本人さまあてに送付している。ただし、ご本人の記載が難しい場合はご家族の方などご本人の状況がわかる方にお願いをしている。
【委員】
実際には本人の方やご家族の方が回答されたものがあるということで、内訳をグラフで示すとよいのではと思った。何人の本人の方が回答されているのがわかるとよいというのと、本人が回答しているのが何パーセントというのがわかると、その後の施策を考えるときに大事になるのではないかと思う。本人の方が求めていることと、家族の方が求めていることと、重なってくる部分もあるとは思うが、少し違ってくるところもあると思う。
2つ目は、「わからない」という選択肢をはじめから入れておくことを提案したい。知的障害の方だけに限らず、「わからない」という選択肢があると、おそらく「その他」や「無回答」となっているものが実際はわからないのかもしれず、「わからない」という選択肢を用意しておくことが、現状により即すのではないか。一定数「わからない」という回答が出ると思う。「わからない」という回答が多い質問については、それがなぜなのか検討する必要が出てくるかと思うので、はじめから「わからない」を選べるようにしておくのは大事だと思った。
3つ目は、通園通学での困りごとについて「放課後の預かり先がない」は保護者の視点になるため、ここは検討が必要ではないかと思った。
【事務局】
アンケートについては、ひな形自体は国から示されているものを参考に作っている。今回のアンケートでは、本人なのかそうでないのかという区分はできないようなので、次回からはできるように工夫をしたい。「わからない」という選択肢についても検討したい。ご意見ありがとうございました。
【委員】
アンケートの知的障害者の自由意見について。知的障害の方が自分でこういった意見を書かれる方は少ないので、おそらく家族の方が書かれているかと思うが、今の記載方法では障害者ご本人の年齢・性別しか書かれておらず、記載した方の状況がよくわからないので、年齢や性別などどういう家族の方が記載されたかを出された方がいいと思う。
もう1点、前回質問させていただいたが、市営住宅の入居については、障害者と高齢者の枠があるということだったが、ただ、知的障害の場合は支援ないと暮らせないため必要になるが、そういったものは条件があるのか。障害は身体・知的・精神とあるので、どの障害者の方も入居できるということなのか。地域でグループホームを建設するときに、反対されるのは知的障害の場合が多いので、他の障害の方と同じように入ることはできるのかが疑問だった。
【事務局】
入居できる枠としては高齢者と障害者が一緒になっているので、障害の種別までは分けていない。
【委員】
知的障害者の方もということだが、支援付きということがどうしてもあるかもしれない。
【事務局】
市営住宅に入っていただいてサービスを受けていただくということになると思う。障害種別で分けているわけではない。
【委員】
グループホームにサテライトという形があると思うが、そういったものにも利用ができると考えてよいのか。サテライトというのは利用者がグループホームから独立したいのでサテライト事業でそこで訓練をしてということになっている。事業所ももちろん支援付きなので支援してはいく。そういった形でもできるのか。
【事務局】
ご本人さんがそこでサテライトでも住まわれるということであれば可能だと思う。
【委員】
施設入所の地域移行の推進について、現状と乖離しているので意見を言いたい。グループホームの整備を通じて施設入所者を地域移行するということだが、課題のところに「地域生活への移行や、障害者の重度化・高齢化などにより、今後グループホームの利用の増加が見込まれる」とあるが、重度化して高齢化した場合に、グループホームでの生活は今のところ難しい。施設入所支援でしかできない。今のグループホームの制度では、職員が世話人であり、生活支援員ではない。世話人さんのレベルでは、重度化・高齢化した障害者を見ることは不可能。施設入所者の待機者が増えてきているのが現状。そのため、ここの課題の中で、グループホームが増えても利用することは不可能。今後の施設入所からのグループホームへの移行については、国からパーセンテージが示されているが、長崎市ではそのまま受け入れることなく、現状の施設入所の方の待機状況、地域での受け入れの状況を加味してパーセンテージを作ってほしいというのが希望。特にこの間の厚生労働省の説明ではグループホームを総量規制するという意見が出ていた。グループホームの総量規制をし、地域移行をさせることは、アクセルとブレーキを一緒に踏んでいるようなもの。グループホームだけではなく、施設入所支援の必要性、重要性を考えていただきたい。
【事務局】
施設に関しては、専門的な知識を持った方がそばにいた方がいいという方も一定数いることは間違いない。その方々が一気に地域で生活をするというのは現段階では厳しい。そういった意味で入所の施設の意味合いはある。意義としては十分わかっている。グループホームで重度の方を見ようという動きがあるのは間違いない。一方で施設も、人材や設備などの資源を活かそうということで国も考えているときいている。いずれにしても施設には施設として果たしていただく役割はあると思っているので、数字の部分についてはしっかり検討して、お話をしたいと思う。
【委員】
振り返りの資料について確認をしたい。障害のある子供に対する支援の充実の項目のところ。助成を行った旨が書かれているが、ここの課題について、「このまま増加傾向が続けば、市の財政負担が膨大になるおそれがある」とさらっと書かれているがすごく大きな問題だと思う。担当は幼児課と書かれているが、市の財政や議員さんも、どのように市の予算を市民の意見を聞きながら使っていくのか。他との兼ね合いも見ながら予算については見ていく必要がある。行政と議会、こういうものを見落とすことなく対応してほしいという要望と、第5期の計画にも盛り込んでいただきたいという要望。
【事務局】
財政負担が増えるのは間違いないが、ここの書き方は少し違うと思う。全体的な流れとしては、療育を受ける場面も必要だし、障害のあるなしに関わらず学校で集団生活をしていくというのも重要なことなので、障害のある方が保育所や通常学級に行かれるという場面が増えてくるはずなので、そういったことになると支援が必要な方に対する支援や市からの支出が増えてくるのが今からの流れだと思う。
ここの課題の書き方は少しちがうと思うので、所管課である幼児課とも確認して検討する。
【事務局】
あくまでも課題のところで書いているので、こども部としてやろうということではなく、課題として予算が大きくなるというのは当然あると思う。ただ、課題にこれがあるからこども部としてこれをやらないということではなくて、課題があるけれども議会や財政と相談しながら、進めていく必要があると認識している。
今の事実を書いているだけであり、だからどういうことをしていこうというのはこれからの話になる。
【会長】
議題1についてほかに意見、質問等ないか。ないようなので、議題2「長崎市第5期障害者基本計画素案の審議について」、事務局の説明をお願いする。
【事務局】
(【資料4】第5期障害者基本計画において取り組むべき施策の方向性・主な取組み、【資料5】国・市の現行・次期計画の比較、【資料6】長崎市第5期障害者基本計画(素案)に基づき、長崎市第5期障害者基本計画素案の審議について説明。)
【会長】
今の説明に対し、質問、意見はないか。
【委員】
心身障害者に対する情報バリアフリーについて。視覚障害者の選挙について、県議選については情報が早く入った。今までになかった画期的なこと。選挙管理委員会に感謝している。市長選は情報が入っていたが、市議選については全く情報が入っていなかった。選挙会場に言ったら書き出しはあったが、事前に情報を知ることができない。かといって政見放送はない。そのため視覚障害者が取れる情報の枠がない。市議選の場合は告示から投票までの期間が限られており難しいとは思うが、内容はともかく、候補者名や政党名等ぐらいの情報はいただきたい。
施策の中で視覚障害者が一番困っていることについて相談したい。視覚障害者は同行援護を利用している。これは国の支援事業ということでやっており、長崎市も負担をしている。同行援護をする事業者が激減している。先月、ある視覚障害者の方が40か所あたってやっと見つかった。しかも同行援護で使えるのはわずかな時間。月に10時間程度。事業者の事情はあるとは思うが、市の方からいろいろな指導や協力依頼ができないかなということを希望したい。
もう一つ、ハザードマップなど安全に対する取組みについては非常に感謝している。今までになかったようなハザードマップや、自分が住んでいる地区がどのような状況にあるかがわかりやすくなった。これについては市の広報誌等で伝達をしているのか。
【事務局】
選挙に関しては、選挙管理委員会とも協議をしたい。ただ市議選については、候補者も50名から60名ということと、告示から選挙まで1週間しかないということで、なかなか厳しいかもしれないが、一番身近な選挙なので、視覚障害者にも配慮した取扱いができるようにしたい。
同行援護については、重要な問題ということで認識はしている。高齢者の方も介護のヘルパーが少ないという中で、非常に難しいところはあるが、県も巻き込んで、ヘルパーに同行援護の研修を受けてもらって、なんとか同行援護できるヘルパーさんを増やしていきたいと考えているところ。
ハザードマップについては、色々な障害の種別にも配慮したハザードマップの広報にも引き続き努めていきたい。
【委員】
選挙について、候補者の数が多かったということと、今回の市議選は時間が短くてできなかったということだが、市民一人一人に対して候補者の想いをちゃんと伝えることができずにいたということだが、ただ、障害者や高齢者でないとわからない思いというものがあるので、そういった方々の市民の言葉を代弁してくれる方に一票を投じたいというのが市民の想いだと思う。今回は間に合わなかったということだが、ホームページやYouTubeなど、今は手段としていろいろなものがあるので、オンラインも含めて、候補として立ってくれた方々の想いを伝えてから一票を投じる仕組みを作ってもらえればと思う。情報を公平に知りたい。
【事務局】
ICT技術もかなり発達してきているので、次の選挙の時には選挙管理委員会とも連携して取り組みたい。YouTubeなど個人でされている議員さんもいるが、それを全員できるようにしていければと思う。
【委員】
相談支援事業所については新たに追加で指定を考えていることなのでぜひよろしくお願いします。
雇用就労経済自立の支援の項目について、長崎市就労支援相談所はハートセンターの中に設置されているが、今後国が就労選択支援を令和7年10月から始まるということになっている。A型事業所、B型事業所、就労系の事業所、特別支援学校の卒業生については、すべての方が就労選択支援のサービスを受けなければならないとなっているが、今後、就労相談事業所はいるのかどうか。今県の方でも、同じようなことをなかぽつセンターがかぶってやっている。長崎市の就労相談支援事業所を今後も続けていくものなのか、就労選択支援をここでもやるのかどうかを聞きたい。個人的には不要ではないかと思っている。県と連携をして、県と予算を出し合いながらやるべきではないかと思ったので意見しておく。
法定雇用率が来年4月から上がるが、長崎市も法定雇用率は達成しているかとは思うが公表はされていないのでわからない。法定雇用率の中の、障害者の方の種別について、知的障害者は雇っていないのではないかと思う。精神障害者はわからない。市の職員として障害者の方を雇用する場合、種別の枠を作った上で採用を募集してほしい。
福祉的就労の底上げについて。長崎市は令和4年度で7500万円の実績があり県内でもトップクラスで長崎県の3倍発注してもらっている。質問だが、官公需優先発注の中には、障害者福祉施設への物品調達と障害者を雇用している事業者(認定雇用事業者)への発注と二つある。それぞれどれくらいなのか内訳を教えてほしい。物品調達の方が恐らく少ないと思うが、7500万円の中の何パーセントが福祉施設への物品調達なのか。そこを増やしていかないと底上げをしていこうという方針にはならない。来年度は1億ということで、ありがたい話だが、福祉施設へ発注する数字を教えてほしい。
【事務局】
ハートセンターで実施している就労相談支援事業所について、令和7年10月から就労選択支援が始まることはきいているが、まだ事業の中身自体を詳しく把握していない。就労選択支援を必ず通っていくとなると今までの仕組みと全然違ってくるとは思うが、就労相談支援事業所が必要となるかどうかは今の時点ではお答えできない。県とかぶらない部分を市がやっていくということになるとは思うが、具体的な部分はお答えできない。
市の職員の障害者雇用の状況については、把握している限りでは知的障害者の方が雇われたという話は聞いたことはない。精神障害者の方はある一定の人数いらっしゃると思う。当然身体障害者の方はいらっしゃる。法定雇用率については、市役所と教育委員会と上下水道局とそれぞれで報告することとなっているが、いずれも雇用率は満たしている。雇用率自体は正規職員だけではなく、会計年度任用職員も含まれており、障害の重度や軽度といったことで少し変わってきたりもするが、雇用率は満たしている。内訳については数がお答えできるかどうかは、教育委員会、上下水道局を含め人事担当課に確認したい。
【事務局】
障害者就労施設への優先調達の発注実績は、160件の7500万円だが、認定雇用事業者の実績については契約検査課が所管しており、発注件数は437件である。長崎市の場合は、就労施設への優先発注と認定雇用事業者への優先発注は分けて実績を出している。7500万円は障害者就労施設へ発注した実績額である。
【委員】
7500万円を直接障害者就労施設へ発注しているという実績はすごいことだと思う。そういった事業所で育った方々が一般就労を目指していくことを思った際に、今のお話の中で市の障害者雇用の中に知的障害の方がいないというのはおかしいというか違うと思う。知的障害の方は困難さを持っているがすごい力も持っている。行政で雇用することによってすごい力を可能性として引き出してあげて、そしてモデルを示してほしい。課題に「法定雇用率を達成している事業所もあるが、未達成の事業所も多く」とあるが、事業所の皆さんは専門の知識や技能を持っていない方も多いので、障害者の方を理解するにはいろいろな困難さがあると思う。長崎市で雇用のノウハウを蓄積し、それを伝えることで、一歩踏み出そうという事業所も増えるのではないかと思う。いろいろな障害の方を雇用してみることによって、専門機関の人たちにも入ってもらって、受け入れる人たちが力をつければ、しり込みしている企業の方も一歩踏み出せるのではないかと思う。
【委員】
まずは意見として、就学教育相談の充実を挙げられていてとても大事なことではあるが、現状、長崎市や長崎県に限らず、全国的な傾向として、就学時健康診断を受けた際に、一定程度障害があると認められた時に、多くの場合は特別支援学級や特別支援学校への進学ということになるが、現状、決定権が各市町村の教育委員会にある。障害福祉課だけの管轄ではないとは思うが、インクルーシブを進めていくのは、特別支援学校ももちろん大事だが、一番大事なのはマジョリティというか通常の学校の側が多様な子どもたちの受け入れの場にならない限り進んでいかない。長崎市だけで解決するのは難しいかとは思うが、就学時健康診断の後に、教育支援委員会が開かれて、本人や保護者と一緒に就学先について考える場面がある。そこで障害があると言われても地域の学校に通わせたいという意見が出た際に、最大限それが叶うようにしていってほしい。大きな意見にはなるが、長崎市でもより積極的に考えていってほしい。
質問として、医療的ケア児への支援について。看護師資格を持っている特別支援教育支援員の把握はかなり難しいと思うが、どのような見通しか。学校看護師を配置していかないと解決していかないと思うが、どのように考えられているか。
【事務局】
教育研究所に医療的ケア児に対する特別支援教育支援員の配置について確認したところ、令和6年は、12の学校に13人の医療的ケアを要する児童・生徒が在籍する見込みであるとのこと。既存の看護師に加え新たに確保する必要がある看護師が3人という状況。現在3人のうち2人が確保できており、残り一人についても現在採用活動を進めており、年度末までに確保できそうな見込みであるとのこと。
【委員】
医療的ケアが必要な重度の子どもたちも、通常の学校に通える道筋が開いていくように、支援員の配置が拡充していければと思う。
【委員】
地域で生活するという視点から。ヘルパーの活用について。入所施設に入っている方は二重利用になるためヘルパーは使えない。グループホームの行き帰りも、グループホームスタートの自宅に帰るときは使えるが、自宅からの帰りがなかなか使えない。かなり柔軟にはしていただいているが、もともとヘルパーの発生というのがパーソナルアシスタントということで、地域での生活を全面的に支援するという発想でのスタートであることを考えると、もっと自由に使える。今、一番親御さんが困っていると声があがっているのが、高齢になられた親さんたちが、入所施設やグループホームに入所させて送り迎えができなくなってきている現実があるということ。ずっと会えていないという話を聞く。そういう時にヘルパーをうまく活用して、地域の中で自分が生活しやすいシステムを作っていければいいなと思う。この事業は移動支援ということで大項目があるので、なかなか個人の日常生活の中でどう使うかということは難しいのかもしれないが、本人の重度化・高齢化や親さんの高齢化が大きな問題になっている。アンケートの中にはあまり出てこなかったが、今とっても大きな問題。せっかくグループホームなどで地域の中で暮らしているなら、自由な利用の促進というのをお願いできればいいなと思う。
【事務局】
グループホームからの一時帰宅する場合のヘルパーの使い方など、基本的には地域生活支援事業なので市町村ある程度柔軟にできる分なので、総合支援法の中で施設の報酬の中で送り迎えが報酬になってくるのかというところは精査しなければならないが、そのあたりは柔軟に、今後必要なサービスにもなってくると思うので考えていく。
【委員】
医療的ケア児の看護師の確保について、教育研究所への要望になるが、お伝えしてほしい。必要な3名のうち2名は確保済とのことで、年度末までにはあと一人見つけるということだが、保護者からすると年度末までに希望する学校にいけるかどうかわからないのはすごく不安だし、万が一見つからなかった時の準備やどこに行くかといった問題もある。毎年確保することがかなり難しいことだとは思うが、できるだけ年度末ということではなく、最低3か月から4か月くらい前の12月くらいまでに確保してもらって、新年度への準備ができるように早めの確保をお願いしたい。
【事務局】
基本的には学校を決めないといけないので、できる限り早めに決めていただくように教育研究所にも伝えたい。
【委員】
雇用・就労・経済的自立の支援のところで、現場を見ている中で、課題のなかに各事業所における平均工賃の向上を図る必要があるという項目について、なかなか難しいと思う。正直に言って、B型事業所においては時間単価500円もらっている方は少ない。おそらく交通費も出ない。これが現状であると頭においてもらって、工賃を上げていくために市としての対策を具体的に検討してほしいと第5期の計画に向かって思う。頑張っている利用者さんもたくさんいるので、議会や行政においてそのような声を拾ってもらってよりよい施策を行っていただければと思う。
【委員】
技能を上げないと工賃はあがらないと思う。一般就労も同じ。福祉的就労においても決められた仕事ができなければ工賃はもらえない。資料4の文化芸術活動・スポーツ等の振興について、アート作品を作ることで仕事につながるとか、スポーツをすることで機能が開花して仕事につながるとかあると思う。障害者の方の技能大会であるアビリンピックが県の産業労働部に窓口があり、ポリテクセンターで地方の予選会があっている。長崎市の中でみんなが参加できるように広報を活発にしてはどうか。身体の方に比べて、知的、精神、発達の方には情報が十分に伝わっていないと感じる。挑戦のチャンスをすべての人に作っていくということが、工賃や一般就労の賃金につながる一つの方法だと思う。
【委員】
スポーツ活動について、自分の体験談だが、サウンドテーブルテニス(盲人卓球)で宮崎市に行った際に感動したことがあった。介護事業所の方たちが「さざなみの会」を作ってボランティアの活動をしているが、これがすごい人数でやっている。事業所が人を出したり、あるいは看護学校などから会員として入っていて障害者の活動を支援してくれる。九州各県を大会でまわったが、宮﨑市はすごいと思った。障害福祉課でもぜひ宮崎の方に聞いてみてほしい。活動をされている方は我々のまわりにもいるが、宮崎の場合はすごく大きい団体。非常にフットワークがよく、今までで一番感動した。よければ障害福祉課の方で、さざなみの会の結成の経緯など調べていただければ助かる。
【委員】
看護師の確保について、長崎県看護協会さんにききたい。退職された看護師さんなどいると思うが、処遇など情報が伝わっていない可能性もあるのでは。1日はできないが短時間ならできるとか、働き方の制約がある人についての間口を広げると見つかるかもしれないと思った。潜在的な有能なシニア人材の方々に活躍の場を与えられて、柔軟な働き方やちゃんとした処遇を明記して募集すると、もしかしたら発掘できるかもしれないと思った。
【委員】
看護協会でも定年自体が65歳で、65歳を過ぎても施設の中で年間雇用など、雇用体系も変わってきており、一般病院も高齢化になっているという現実はある。若い方の定着というところも看護協会として現実的な課題としてある。今まで会員が1万人いたが、割っている現状。県外に出ていくという現状もある。協会として、学生のころからアピールをしていかないとというところで、県南支部としても高校生などを対象に楽しさであったり、看護職の中でもいろんな分野が開けてきているので、そういった紹介をして一人でも多くの方が、県内に残ってもらえるようにという取り組みはしている。定年後のという部分は、医療的ケア児にもつながってくると思っていて、若い方は経験値が少ないので興味はあってもしり込みするところがあったり、また親御さんとのコミュニケーションもしっかりしていかなければならず、なかなか完結しないところもあると思う。看護協会としても、興味を持っていただくというところで、すぐすぐつながっていかない部分はあると思うが、いろんなところと協力しながら、協会から発信したりしていければと思う。協会に帰ったら共有したいと思う。
【委員】
グループホームの立上げについて、用地とか資金調達とか地域住民の反対など書いてあるが、もう一つ大事なのが、マンパワー不足。今長崎はとにかく人がいないということが現実。ぎりぎりの人数でやっているのが現状。グループホームを作りたいけれども人が足りなくて踏み込めないということがある。就労のマッチングということも出ていたが、市の方でもチャンスを検討していただければ。
【会長】
議題2についてほかに意見、質問等ないか。ないようなので、議題3「その他」だが、委員の皆様から何か意見、質問等はないか。
【委員】
事務局に要望。タイムリーに議事録を発行してほしい。時間をかけないまとめ方でもいいのかなと思う。何か月も前のことは忘れてしまうので早めにしていただければ。一字一句書き起こさなくてはいけないのか。
【事務局】
全文筆記と要点筆記がある。どちらにするかは審議会の中で決めていただく事項になる
【会長】
全文筆記か要点筆記か決定したい。全文筆記までは必要ないと思うので、要点筆記でどうか。
【各委員】
異議なし。
【会長】
では、要点筆記としたい。事務局には早めに議事録を作成するようお願いする。
【事務局】
了解した。
【会長】
ほかに質問、意見などないか。ないようなので、議題は終了する。議事を事務局にお返しする。
【事務局】
これで令和5年度第2回長崎市障害者施策推進協議会を終了する。本日はお疲れ様でした。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く