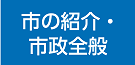ここから本文です。
令和5年度第4回 長崎市障害者施策推進協議会
更新日:2024年9月6日 ページID:042669
長崎市の附属機関(会議録のページ)
担当所属名
福祉部 障害福祉課
会議名
令和5年度第4回 長崎市障害者施策推進協議会
日時
令和6年1月16日(火曜日)14時30分~
場所
市庁舎9階 中会議室
議題
(1)長崎市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(素案)の審議について
(2)その他
審議結果
【事務局】
令和5年度第4回長崎市障害者施策推進協議会を開催する。本日の協議会は委員20名中17名の出席で、会議は成立している。議事進行を会長にお願いする。
【会長】
議事にはいる。議題(1)「長崎市第5期障害者基本計画(素案)の審議について」、事務局から説明をお願いする。
【事務局】
議題(1)に入る前に、前回の会議でいただいていた質問について担当者より説明する。(前回の会議で委員より質問のあった、長崎市の障害者雇用状況、宮崎県の移動支援に係るボランティア団体について説明)
【委員】
一般職における知的障害者の雇用がゼロということで残念に思う。県の方は4名雇用している。平成31年からずっと話をさせていただいている。身体、精神、知的それぞれ募集するよう県の方は変えてもらった。募集要項はどの障害があってもいいという風にしてほしい。採用されるかどうかは別として、精神、知的の方にも門戸を開いてほしい。実雇用率は2.9%でクリアされているが、4月から法定雇用率があがるのをどうされるか。重度の障害者の方のダブルカウントは企業がすることなので、行政は実人数で2.9%をクリアをしてほしい。県にも強く言っている。
【委員】
教育委員会での雇用はクリアしているのか。
【事務局】
法定雇用率は超えている。知的障害者の採用については、業務的に現実に難しい部分もあるかとは思うが、その中でも短時間勤務についてはできる部分について検討していきたい。市が企業等に率先して障害者の雇用を進めていく必要があるので、重度の方のダブルカウントについては実人数でクリアしていけるよう、人事部門とも話をしていきたい。
【委員】
知的の方も仕事がつくりづらいと思われていた時代もあった。一連の業務として行うのは難しいが、細分化するとできるという考え方も出てきている。
【事務局】
今の状態がベストだとは思っていないので、どういった仕事であればできるのか探っていって、3つの障害の差別なく採用できるように検討を進めていきたい。
【事務局】
それでは、議題1「長崎市第5期障害者基本計画(素案)の審議について」、【資料1】長崎市第5期障害者基本計画(素案)に基づき説明する。(【資料1】長崎市第5期障害者基本計画(素案)に基づき説明)
【会長】
今の説明に対し、質問、意見はないか。
【委員】
相談支援事業所の件については、令和7年度に1件増やすという回答をいただきありがたい。できれば、もう1か所増やしてほしい。ハートセンターの相談については今、児童に特化しており、成人の相談ができていない状況。成人は他の指定相談支援事業所にまわされている。どうしても数が多い。そこの部分を補てんしていただきたい。令和7年10月スタートの就労選択支援について月8人と見込んでいるようだが、新たに利用する人はすべて受けなければならない。8人としている根拠は何か。また、令和8年4月からは特別支援学校の生徒は全員受けることになるので15人という見込みでいいのか。受給者証の更新の場合も、受けるかどうか確認して受けると行ったら使うことになる。この人数でいいのかという確認。
【事務局】
相談支援事業所については、増やすのは絶対1か所だけとは思っていないので、令和5年度、令和6年度の状況を見ながら、柔軟に必要数を検討していきたい。変更があればご報告したい。
【事務局】
就労選択支援の見込みについては、令和7年10月開始で見えないところもある。現在の使用状況から見込んでいるが、特別支援学校の生徒さんもすべてという部分を勘案し、少し見直す余地もあると思う。
【委員】
同行援護事業について。県と連携をとって研修を進めていくということだが、研修を受ける人があまりいない。事業所さんに直接聞いたが、単価が安いとのことだった。同行援護は国の支援事業であり、国から視覚障害者1人あたり55時間の予算を配分されているが、額が変わっていないので、自治体でいくらか負担をしなければならない状況にある。長崎市は60時間いただいている。30~40時間で切る自治体もある。事業所がやらないのは単価が安いから。これから視覚障害者は、中途視覚障害者が増える。年を取ってからだと歩行訓練も難しい。そこで同行援護が必要となるが、41事業所のうち40事業所から断られた人もいる。やっと見つけて月に使えた時間が12時間だった。そこを解決してほしい。外に出るためには同行援護の力が必要。これから中途で視覚を失う人はかなり厳しい。今日の会議も同行援護の方に来てもらっているが安い。なんとか解決する方法を考えていただきたい。
【事務局】
同行援護の研修を受けたヘルパーを増やしていきたい。おっしゃるように、介護にあたる方の報酬面の問題が大きい。いろいろなサービスと比較して、報酬が適切かどうか、県と連携をとって報酬面についても検討させてもらう。
【委員】
サービスの提供側は単価が安いのでニーズがあっても受けきれないが、状況が整えばもっと利用者は増えるという認識でよかったか。
【委員】
視覚障害者の団体に新しく入ってきた方が同行援護で外出をしようと事業所を探してもなかなか見つからない。考えてみてほしい。40か所から断られている。1か所受けてくれたが使用できるのは月12時間がぎりぎりの状況であり、これでは外出できない。引きこもってる人が多い。全国的に見ても足りない。長崎市はよく時間をいただいているが、問題は事業所が応じてくれないということ。それを解決できる方法をというところ。
【委員】
次の点について教えてほしい。
1.共同生活援助の重度障害者について。軽度の方だけかと思っていたが、重度の方も入っているのか。
2.保育所等訪問支援の利用見込みが激増している理由は何か。
3.手話通訳配置の人数がずっと4人であり、派遣の数も減っているが、状況を教えてほしい。
【事務局】
重度障害者の共同生活援助については、もともと軽度の方でということではじまったが、現状は重度の方もできる仕組みになっている。事業所は苦労しながらやっていただいているのが実情。
【事務局】
保育所等訪問支援の見込み方については、令和5年度の実績を固めて、伸び率をもとに令和7年度、令和8年度を算出した。利用実績がここ2~3年ものすごく伸びている。通所支援がメインの中、保育所等訪問支援が平成24年から始まったが活用されていなかった。厚労省もガイドラインを作成して活発な利用をという取組みを行い、報酬改定もあり、事業所からすると参入しやすい事業になった。保護者から見ると通所ではなく、学校や保育所に専門スタッフが見に行くというもので、周知が進みこういった伸びになっている。
【事務局】
手話通訳者の配置数については、市役所とハートセンターの専任の手話通訳士の数は4名で、内訳は市役所2名、ハートセンター2名。この20年ほどは4人の状況。それぞれの職員として配置している。また、専任とは別に、手話通訳の登録制をとっているので、聴覚障害者の方が出かける際は、調整をしながら派遣をしている。専任通訳士が4人に増えた際は、ろうあ協会さんと手話通訳の団体さんの要望をいただいてのことだった。現時点ではご要望はいただいていないが、状況を聞きながら考えていきたい。
【事務局】
手話通訳、要約筆記の今後の見込みについては、コロナ禍の状況もあったが、過去の実績をもとに平均の数字を採用している。
【委員】
見込みが減っているのはなぜか。コロナはだいぶ落ち着いている。
【事務局】
過去の実績をもう一度確認して、見込みについては検討させていただく。
【委員】
視覚障害者の同行援護の話が出ているが、知的障害者についても行動援護の人手が足りないという状況がある。重度の方のグループホームでの生活を24時間体制で考えたとき、移動や帰宅、1日24時間のバックアップが不十分だと思う。重度の方が地域の中で暮らすためには、ヘルパーの充実が非常に大事。入所施設に入っていてもグループホームにいても、ヘルパーが普通に使えるという形になるべきと考える。国の方向性もあるが、検討してほしい。ヘルパーの活用、移動支援も柔軟に使えるように。パーソナルアシスタントという考え方を念頭に置いて、進めてほしい。
【事務局】
重度の方がグループホームと入所を選べる状況が一番いい。要望がかなえられるようにしていきたい。移動支援は市で若干融通が効く。そういったものを活用しながら、報酬も国も少しずつ増えてはきている。地域で暮らしていけるように要望はしていきたい。
【委員】
生活するという土台があっての働くということだと思う。外に出て買い物をするのは人間らしい行為。自分の能力を、働くという行為によって社会に貢献する。自分ひとりでできないのであれば、それをサポートする人たちの生活の保障、つまり報酬がないと成り立たない。長崎市だけではなく、県内の市町や県もつながって、国のパーソナルサポーターの人たちが生活の保証があり、制約がある困難を抱えた人たちが地域で生活し、働いて貢献して報酬を得るという形で進んでいってほしい。命を守るサポートだと思う。国レベルの研修とかオンラインでしていただいて、オンデマンド配信など、それぞれがいいタイミングで学べるように支援力を高めていただければと思う。
【事務局】
報酬面での要望をしていきたい。ヘルパーも事業所から派遣されるので、事業所にどれだけメリットがあるかということだと思う。報酬アップを含めて要求していきたい。
【委員】
報酬単価を上げてもらわないと、今、外国人労働者すらいない。地方から都会にとられてしまっているのでますます人手不足。報酬単価を上げてもらうことが大前提。地方で声をあげてもなかなか難しい。長崎市単独で福祉の施策として、グループホームは生活支援をしていくんだという風にしてほしい。国にあげるだけじゃなくて、長崎市の施策としてもやっていこうという気概を持ってほしい。
【委員】
参考だが、長崎市は同行援護の時間数は、九州では3本の指に入る。北九州、長崎、都城が手厚いと有名。長崎市で基本60時間の同行援護。これはヘルパーがいての話。東京都は無制限。財政的にも違う。京都府は33時間。どこに問題があるのか。生きるための環境である。都道府県で差がある。平等に、この国に住んでよかったという環境を構築してほしい。なぜ自治体が違うとこんなに差があるのがいつも疑問。
【委員】
1点は、保育所等訪問支援の増加に驚きを感じている。現状は保育所等訪問支援に対して危機感を感じている。質の高い事業者とそうでないところが乱立している状況。一番気になるのは、児童発達支援の事業所、つまり就業前のお子さんを対象にしている事業所で、かなり小さくて手がかかるお子さんも多いが、発達状況のやりとりがなく、訪問をして指導をしているというところが気になる。園によっては断っているところもある。園で大変だから事業所の方にという話をきくこともあり、インクルーシブという意味では後退している事例もある。中抜けという言い方をするが、保育園に行きながら保育料も払いながら週に何時間か事業所にも言って両方にお金を払うという状況が気になっている。中には、ハートセンターに訓練に来ているお子さんの発達状況やどのようにしたらよいかを聞きに来られる事業所も少数あるが、あとはやり取り等まったくない中でやられている印象が多い。放デイについては、本来は余暇活動の提供だが、その中で学校訪問という形でいかれていて、学校の方に聞いたところ、学校の中に来て、クラスの中で支援をしているとのことで学校の先生としては困惑するケースもあるとのこと。役に立っている部分もあるが、学校の先生や保育園の先生にアンケートをとってみてはどうかとも思う。保育所等訪問支援の見込を立てるのであればいいものにしないとと思う。
児童発達支援センターの機能強化に力を入れていただければと思う。ハートセンターの児童発達支援センターさくらんぼ園については通園している子どもの対応だけで精一杯の人員体制。人員を充実させることがひいては訪問支援に携わる方のアプローチになるのではと思うので、機能強化に力を入れていただければ。
これまでにない動きとして、以前は学童だったお子さんが放デイにきており、時代が変わってきている。子どもにしっかり寄り添った形での中身であることを願う。軽度は受け入れるが重度は受け入れられないという事業所もある。児童発達支援のはずなのに多動すぎて他のところに行ってくれという事例もあった。大変なお子さんが多いところには報酬の割合が変わるなどあるのか。そのあたりがまだまだ分かりづらい部分もあるようだ。現状を含めてお願いしたい。
【事務局】
保育所等訪問支援をはじめ、障害児の通所事業については、児童発達支援、放デイ含めて質に差があるという認識はある。保育所等訪問支援は原則月2回。特性にあった支援をされているかという確認や保育士たちへのアドバイスをするという支援であり、子どもさんの状況をわかってないと成立しない。大きな課題だと思うので、しっかりやっていきたい。学校の方は、教育委員会の方でも支援員さんがいたりする。教育研究所も研修をしている。ここでの意見は教育研修所に伝える。ハートセンターの児童発達支援センターさくらんぼ園については、行政がするからには困難な重度の方などやっていかないとと思う。事業所のバックアップもしていかないといけない。福祉は人手の部分が大きいので、ハートセンターが持っている知識を広めていけるよう、人員体制を含めて考えていきたい。
【委員】
施設入所者の地域移行と施設入所者の削減について、他の委員の方から意見があったが、減らしていくことは難しく、グループホームと施設は違うということだったかと思う。見込みの数値と目標値について妥当なのか。
【委員】
各入所施設には10人以上待機しており、現状は減らすことは無理。国は減らす目標値を6%にしているが長崎市は1.6%に減らしているので、納得はしていないがそのくらいでしょうがないかなとは思っている。地域移行しなければならないのはそのとおりだと思うが、地域が整っていないのに移そうとするのが疑問。入所施設の必要性など、厚労省が現状を分かっていない。
話は飛ぶが、災害について。石川県で地震災害があったが、在宅の障害者はグループホームではなく入所施設が看ている。入所施設は災害時必ず必要となる。長崎市とも入所施設は何かあった時のための契約をしている。シミュレーションや訓練もしていないのに明日地震があった時に動けるのか。何かあれば入所施設が中心になってやるしかない。その入所施設を解体して小さくしていこうとすると地域福祉も何もなくなる。そこを危惧している。
【事務局】
厳しいご意見だが、国の定める率からは大幅に減らしている。施設からの地域移行を目指そうということであげている数値である。施設入所者の中でもグループホームで過ごしたい方も何人かはいらっしゃるだろうというところも含めて、目指すべき数字というところでご理解いただきたい。
災害時の対応について、福祉避難所を指定させていただいている。訓練については高齢者はしているが、障害者はできていない。能登半島地震での障害者の避難所での苦労は聞いているので、福祉避難所としてどう対応していくのかということは、訓練も含めて考えていかなければと思う。
【会長】
議題1についての意見がないようでしたら、議題(2)「その他」について、何かありませんか。
【委員】
障害福祉課とは直接は関係ないかもしれないが、バリアフリーに関わること。新庁舎の玄関の点字ブロックの色がわかりにくく、視力が少し残存している弱視者の方が担当部署に見えにくいと訴えた際に、変えるつもりはないと一蹴されたとのこと。弱視者も一人でなんとか点字ブロックや白線をたどって歩いている。観光地では景観等もあり色を減じるところもあり仕方ないとは思うが、行政機関というのは誰もが利用する場所である。なんとかバリアフリー化するように進言してほしい。誰もが利用する行政機関の庁舎でそう言われても理解できない。
【事務局】
ブロックは弱視の方にもわかるように路面との差をつけるようになっている。所管課に要望をしたいと思う。
【委員】
資料についての要望。数値化しているとある面では現状がわかりやすいが、どういう数値なのかわからない。それぞれの数値がどう出されているのかなど。何を意味しているのか。今後は資料に入れていただければという要望。
【委員】
環境の整備について。長崎市役所という施設がモデルになったらいいのではないか。環境づくりを市役所から。報道機関も巻き込んで小さいことでいいので発信をしたらよいのでは。
【事務局】
新庁舎を建てる際には、担当部署がいろいろな団体の話を聞いて苦労して建てたと聞いている。以前に比べれば、使いやすい庁舎にはなっているが、一部点字ブロックの話などあるということで、改めて確認はしたい。お気づきの点があればまた教えてください。
【委員】
市役所雇用状況の職員に知的の方がいないというところで、そのお子さんに応じた支援や仕事があればと思う。社会でなにかしたい、役に立ちたいというお子さんたくさんいる。内容を決めてもらったら、長崎市役所の中でちゃんと仕事ができるお子さんたちもいらっしゃるのではと思う。
【事務局】
知的の方でもどういった業務ができるのか要件を探して検討している。役所は異動があるが、異動にも対応できるように業務を考えて、障害の種別に関係なく採用できるようにしていきたい。
【委員】
おそらく役所で考えても答えは出ないので民間を入れるべき。知的障害者を雇ったら専門の職員を配置をする。各課すべてに仕事をピックアップしてもらい、まとめる等して仕事を作ってやらないといけない。ぜひ来年度から、現状や特性がわかっている人を入れてチームを作っていただければ。
【事務局】
一般職は確かにいないが、短時間勤務の方は今も雇用している。その中で、仕事を作っていないという部分は確かにある。民間を入れてという部分も考えさせてください。
【委員】
試験的ではあるが、長崎大学の教育学部の中で、附属の特別支援学校の高等部の子たちに、授業の一環で、大学の研究室を回ってもらって、高等部の子たちがシュレッダーの箱を回収して、業務用シュレッダーにかけたり、タックシール、糊付け、封筒入れなどをやってくれている。部門を市の中に作って、どの課でも出てくる業務を集約して任せられる部分は知的障害者の方にお願いするという流れにする必要があると思う。子どもたちにもできることたくさんあるので、就職先の枠の広がりにもつなげていければと思う。議論させていただける部分もあるのでは。
【会長】
ほかに質問、意見などないか。ないようなので、議題は終了する。議事を事務局にお返しする。
【事務局】
これで令和5年度第4回長崎市障害者施策推進協議会を終了する。本日はお疲れ様でした。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く