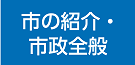ここから本文です。
令和6年度第1回 長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会
更新日:2024年10月15日 ページID:042806
長崎市の附属機関(会議録のページ)
担当所属名
企画政策部 長崎創生推進室
会議名
令和6年度第1回 長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会
日時
令和6年7月23日(火曜日) 14時00分~
場所
市役所8階 庁議室
議題
1 長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価及び検証について
⑴ 基本目標2の評価及び検証について
⑵ 基本目標3の評価及び検証について
2 その他
審議結果
1 開会
【事務局】
・企画政策部長あいさつ
・会議資料の確認
・新たな委員及び事務局側の出席者を紹介。
・会議資料の確認。
・委員数20名のうち14名の委員が出席しているため、長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会規則第5条第2項の規定により、会議が成立していることを報告。
2 議題審議
(1) 長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価及び検証について
ア 基本目標2の評価及び検証について
【長崎市】
・基本目標の目標評価シート及び検証シートについて部会長から概略を説明。
・委員からの事前質問に対して各施策主管課から回答。
【会長】
ここから意見交換したいと思うが、まず「(1)結婚・妊娠・出産の希望をかなえる」というところについて、事前質問への回答を含めた質問や意見等あるか。
基本目標2というのはまず出産までのところと幼少期のところ、それから学校生活の3段階に分かれて目標が設定されているが、出産までのところについてどうか。特にないようであれば「(2)子育ての環境を充実する」のところについてどうか。「(3)学校における教育環境を充実する」についてはどうか。
【委員】
事前の意見への回答について、私が書いていたのがどこの地区でどのような取組みをしていたのかということで、小島・大浦と西浦上でされている。それぞれがしていた活動内容の報告をしているという回答だったと思うが、聞いても内容がぼんやりしていてこの資料だけ見てもそれがどういうふうに利用者支援につなげていくのかよくわからない。どの機関、どの団体がされているのかというのがよくわからない。P11の一番下に「地域の身近な場所で不安を抱える子育て家庭の相談に応じ、各家庭の実情に応じた適切なサービスや事業を利用できるよう、地域の中で子育て支援を行う機関や団体等とのネットワークづくりを推進し」と書かれているが、この機関や団体はどこか決まっているのか。
【長崎市】
基本的に2つの地区でモデルをしたということになるので、大きくは大浦・小島・梅香崎地区が1つ、西浦上・三川地区が1つという形をとろうと思っていた。ただ、1年目だったので合同で開催することが多かった。基本的にはその地区その地区で顔が見える関係を作りたいので、例えば乳幼児であるならば子育て支援センターとか保育園とかがある。地域で活動している民生委員さんとかがある。こども食堂をされているところとか児童館とかがあるので、そういったところでどこってことではないが、大まかに妊産婦から18歳までの子どもを支援する団体がそれぞれ月1回の定例会に参加していただきお互いがしているそれぞれの内容をまずは紹介したというところである。実際に相談場所があればそこに相談に来られた時に、これはこの団体のサービスに繋げればいいよねとか、地域の中でその問題が解決できるようにまずは関係団体がどういうことをしているのかの関係づくりを始めたところである。それがまだ一気に解決までいくというところまではたどり着いていないので、令和6年度についても同じ地区でさらに連携強化であったり、具体的に相談をする体制を進めていきたいと考えている。
【委員】
モデル地区を2つに絞った理由はわかった。でも、中学校区に1つずつ子育て支援センターがあるので、その子育て支援センターを拠点にする考えはなかったのか。
【長崎市】
市内で教育・保育の提供場所としては16か所ある。子育て支援センターも16か所設置ができている。ただ子育て支援センターの元々の役割があるのが1つと今回の連携体制づくりっていうのは子育て支援センターとしては乳児期が中心になるので、学童期とかどういったところがいいのかというのも含めて検討したかったので最初から子育て支援センターということではなく関係団体で話し合っていこうという形をとった。
【委員】
素晴らしい取組みだと思ったので、ぜひ続けてほしいと思う。
【会長】
これまでの4年間の総合評価のところに移るが、「(1)結婚・妊娠・出産の希望をかなえる」について、質問や意見等あるか。
【委員】
婚姻数について実績を書いているが、結婚相談の希望を叶えるということをやったことと実際の婚姻数の因果関係がもしわかれば教えてほしい。
【長崎市】
そこが非常に難しいところである。基本、日本人は婚姻された方が子どもを産むということで婚外子は2%くらいということを把握している。そのため基本的には結婚されて子どもを産んでいただくという形になっている。そのため、そうした意味で少子化対策ということで子どもの数を増やすということで婚姻数を伸ばしていく結婚していただくというところを目標に掲げてやっているところだが、中々セミナーやイベント等を行って、それがマッチングというかカップルができたということがありはするが、その先の結婚されたのかというところを追いにくいところがあり、我々としてはそこもしっかり少子化対策としては婚活・結婚の支援というところをやっていかないといけないと思っているため今年度はアクションプランに力をいれるというところもある。正直なところ難しいところもあるが取り組みはやっていかないといけないと思っている。
【会長】
質問と今日配られていた質問の3番目は関係があって、WizCon NAGASAKIとかそういう取組みをされているのはよくわかるが、どうもミスマッチというかアンマッチというかターゲットにしている独身者の層にヒットしていないのではないか、さらに言えば子育てにおける経済的な不安を払拭することに効果を発揮していないというところがあると思うが、この点は何か検討はされているのか。
【長崎市】
ご質問の回答と重複するが、そういったところも昨年アクションプランを立てる中でいろんな分析をさせていただいた。未婚率が長崎市は高いとか、有配偶出生率が意外に高いとかそういった分析をさせていただいて、やはり結婚していただくというのは結婚したいと思う方の希望を叶えることが一番かなと思っているので、当然行政が無理強いをするということではなく、希望される方の希望を叶えるために県も一緒にやっていたが、そういったところとプラス市としても力を入れてやるべきと判断をして、WizCon NAGASAKIも委員ご指摘のとおり企業間の交流ということでやっていたが、時代にあっていないんじゃないかという声もいただいていたのでアプリとかで出会われる方も多いと聞いているので出会う場を提供する。あとは相談しやすい体制をつくるというソフト的なところも含めて全体的な交流会をやるとかいろんな手法・ターゲットを絞りながらいろんなパターンに対応できるような手法も考えながら市として取り組んでいきたいということで、今年度アクションプランに基づいてやっているところである。
【会長】
これまでの評価という点からいえばまだ効果や成果が出ていないところのような気がするし、今出てきたご意見も踏まえたうえでニーズに合わせて、そういうことも踏まえたうえで次の施策というか、今年度の取組みというか、そういうことに進めてもらえればと思う。
次に、「(2)子育ての環境を充実する」についてたくさん話が出ているが、ここに関して今後に向けて、またはこれまでの取組みの成果についてご意見等あればお伺いしたい。
【委員】
回答不要にしていたが、「子どもが遊び・学ぶ場の充実」のところで意見を述べさせていただきたいのだが、あぐりドームの運営改善として土日とかが予約が取れないと思う。一番子育て家庭が屋内で遊びたいというのが雨の日の土日だったりすると思うが、土日が一番予約が取れないと思うので施設の改善だけで本当にいいのかなっていうのを思った。ほかに身近に気軽に行ける場所に、あぐりドームだけでなく路面電車で行けたりとか、車ではなく公共交通機関で10分15分くらいで行ける場所に思いっ切り子どもが雨の日でも遊べる場所を作ってほしいというのが、私も小学生の子どもがいる母親の一人なので毎回思う。毎回書いていると思うけれども。公園の環境がちょっと悪いなと。自分の地区の公園の環境も遊びづらくなってきていて、ボール遊びが禁止だったりするが、いったいどこでボール遊びをすればいいんだろうとか、する場所がなくなってきてだんだん公園自体に子どもがいなくなってきている。悲しいなと思うので、公園の整備をもっとしていただけたらいいなというのが小学生の子どもを持つ親の願いである。
【長崎市】
まずあぐりドームについて、確かに土曜日日曜日の予約が多いという状況がある。オープンしてから1年以上経っているのでオープン効果というのは少し過ぎ去った感はあるが、今でも土曜日日曜日は予約をシステムで入れても埋まっているという状況が見受けられる。また一日を4回に分けて入場をしており1クール1時間30分で1日を4刻みにしているが、利用者の方が希望する時間が埋まっているということも考えられる。そんな中であぐりドームの運営の改善の考えとしては1つ考えられるのが1クールの定員を250人としている。もともと整備当初はもう少し入れるかなと思ったところもあったがコロナ禍ということで250人とした。実際それで回してみる中でお子さんと大人併せて250人だが安全管理を考えると適当な人数だなと今感じているが、お子さんと大人の人数が半々くらいの状況がある。要は250人と言っても遊んでいる子どもが半分程度ということでなのでそこのアナウンスがもう少し配慮できないのかなというところは指定管理者と協議をしていきたいと思っている。あと利用したい時間帯に予約が殺到しているというときに指定管理者も自主事業という形でゴーカートとかドッグランとか周辺でほかにもいろいろ展開をしているので、そこでうまく一日の中を長時間滞在できるような工夫もしているので、そういったところで希望する時間帯じゃなくても利用できるというところも余地があるのかなというのがあぐりドームの中での検討の余地である。
一方今おっしゃられた他の場所でこういった屋内の遊び場というご意見だと、これは毎年子育て家庭へのアンケートを実施する中でたくさんご意見をいただいている。一番多いのは経済的な支援の充実なのだが、二番目に多いのが遊び場の充実である。特にまちなかでとか屋内でっていうのはたくさんいただいているので、ここはこういうニーズがあるというのは認識している。今後どう展開していくか検討はしていくが、費用も含めたところ費用対効果を含めたところで検討していかないといけないと思っている。意見に書いていただいた子どもそのもののアンケートを実施してはというところも、まさにこども家庭庁が子ども基本法の中で言っているのが様々な子ども施策を展開する中では保護者だけでなく当事者である子ども若者の意見を反映させていくようにと言われているので、今後私どもも聞き取っていかないとと思っている。大人が必要じゃないかというところと子どもそのもののギャップがないようにしていかないといけないなと思っているところである。意見を聞いていくような展開を図るが、いずれにしてもこの遊び場というのは親の方のニーズが高いということで認識をしているので検討を進めていく。
【委員】
ありがとう。子どもが公園で遊べなくなるとどうしても室内にこもってゲームをしたりとかそっちに走ってしまうのでできるだけ早めに整備をお願いしたい。
【会長】
今のお答えの中で子どもさんにアンケートをとるという話をされていたが具体的にどういうふうにアンケートをとるか計画は持っているか。
【長崎市】
子どもさんから意見を聞く部分については具体的なやり方は今後の話になる。ただ、実は今子ども基本法の中で各市町、都道府県も子ども計画を策定するというのが求められている中でちょうどいま各学校を通じて子どもさんにアンケートを県内全域で投げかけをしたところである。このアンケート自体はどういった制度があったらいいかとか具体的なことを求めるのではなくて、子どもさんが感じる幸福度とかそういった理念的な設問ではあるけれども、一旦それを実施しているところである。集約した結果で子ども計画を策定していくが、策定して進捗を図るなかで継続的に子ども若者の意見を反映していくということが求められているのでその中で遊び場を含めて意見を引き出せるようにやっていきたいと思っている。そのため、今年度っていう話ではないが、今後の話になっていくかと思っている。
【会長】
ということは第2期ではなくて、むしろ第3期の計画に反映されるかもしれないということになる。
【委員】
そしたらアンケートではなく、子どもに直接聞きに行くっていうのはどうだろうか。多分アンケートだと堅苦しくなって子どもってもしかしたら低学年だと思っていることを上手に書けなかったり、うちの子どもが一人二年生なんだけど思ったように書けないかもしれないけど、直接来ていただけるとどんどん子ども同士で集まれば自由に発言ができる。なので小学校とか中学校とか行かれてはどうだろうか。提案とする。
【長崎市】
直接的に対面形式でご意見を聞く。これは今策定をしようとしている子ども計画の動きだが、実はその中で市長が地域を回り地域の皆さんのお声を聴くシンナガサキみーてぃんぐというのが実施されているが、この子ども版、若者版を8月末に実施しようということで今参加者の募集を図っているがこれが一つの対面型の形かなと。ただ地域に行ってということではなくて、本庁舎で実施をする形で参加者を募っているところだが小学生の4、5、6年生を対象にしていて、中学生、高校生、それ以上というところで実施をするような形で考えている。委員がおっしゃられた部分については、学校をめぐってということかなと思うのでなかなか実現が難しい点があろうかと思うが、そこも一つ子どもさんから意見を聞き出すためのただアンケートをするよりも直接そういった場があったほうが話しやすいとか表現しやすいとかそういうことかと思うのでどういったやり方ができるのかというのは考えさせていただきたいと思う。
【会長】
アンケートって実は結構難しくて、質問する項目が多いと大人でも答えるのが嫌になるアンケートがいっぱいあるので、取り方等々の工夫も検討していただければと思う。
あとは「(3)学校における教育環境を充実する」についてはいかがでしょうか。
全体的にこのテーマに限らず説明の中で気になったのは学びの質を向上させるとかニーズを拾うとか言葉はご説明の中であったのだが、具体的にどういうふうなニーズをつかまれているのか、どういうふうなことを質として考えておられるのか、もしあるなら多岐にわたるので今すぐに答えるのは難しいかもしれないけれども、1つでも2つでも例があれば出していただければと思うし、もしそれが難しいのであれば、今後どういう改善を図っていくか、今年どういうふうにやっていくか、更に第3期に何をやっていくかというのを具体的に出していただいて反映させていくということが必要になるのかなと感じたという言い方しかできないけれどもご検討いただければと思う。
【長崎市】
いろんなところにそういった表現が出てくるかなと思うので、それぞれそこで使っている言い回しとか、言いたいこと、役割とかもあるのでそれぞれ分析をさせていただいて、総合的に調整させていただいて今後活かせるようにしていきたいと思う。
【会長】
他に基本目標2について、何かご意見やご質問、今までの話を聞いてもっと聞きたいとかいう話が新規に出てきたりすればお願いしたいがいかがでしょうか。
それでは基本目標2については概ね長崎市の年度の評価等々、目標評価と検証については概ね長崎市の評価が妥当であると、ここに記載されているとおりでいいだろうということで委員会としてまとめていいか。ただ、先ほどいろいろとご質問が出たけれども、メモは取りきれていないが、そこについては報告書の中での意見とかでまとめていただければと思う。そういうことでよろしいか。
それでは、これを持ちまして基本目標2については終わらせていただきたいと思う。
イ 基本目標3の評価及び検証について
【長崎市】
・基本目標の目標評価シート及び検証シートについて部会長から概略を説明。
【会長】
基本目標3について、具体的な施策としては、3つあるけれども、それぞれについてご質問ご意見等あれば伺いながら次の検証シートに入っていきたいと思っている、まず「(1)地域の力でまちづくりを進める」というところについて何かご質問やご意見等はあるか。私から一つお伺いしたいのだが、例えば自治会の加入率が下がっているとか、組織率が低いとかっていう目標は到達していないというようなグラフになっていると思うが、この辺は何かその原因や理由というのは探られているのか。
【長崎市】
自治会加入率についてお答えしたいと思う。加入率は近年、自治会そのものが解散しているという事例が生じており、急激な減少傾向になっている。令和6年度も1.1ポイントほど下がっており62%程ということになっている。個々の住民の方々が脱退しているケースと組織そのものがなくなっているということが主な要因で減少している。実態はそういうことである。
【会長】
その実態はわかるが、そういうふうになってしまう理由は分析とかされているのか。
【長崎市】
市民意識調査等のアンケートっていうことになるかと思うが、自治会の存在そのものは理解していただいているのだが、活動内容とかが知られていないとかそういったこともあり、あと近年の住民の意識の変化というのもあって自治会に対しての加入する意義を感じないとか、そういった傾向があるというふうに分析している。
【会長】
ということはこのコミュニティをつくるということに関して言えば、あまりうまくいっていないという評価にも。これだけ取り上げて言うのはきついかもしれないが、そういうふうになってしまうかもしれないけどその辺はいかがでしょうか。もう少しこれを次に向けて改善していきたいとかっていうのが何かお考えはあるのか。
【長崎市】
自治会の加入率だけで見るとそういった傾向になっているけれども、今後のコミュニティのあり方っていうのは当然しっかりと検討を進めていきたいと思っているけれども、加入の促進に繋がるような取り組みとして例えば、自治会長さんが地域の住民の方に加入をお願いする際に取組みがしやすいように利用促進のマニュアルとかっていうのを共有して、実際に住民の方を回る際に活用いただくとか。あとは自治会の加入の促進、魅力を発信するために令和6年度はプロモーション事業をするようにしたいと考えているところである。そういった取り組みを地道に継続していきたいと考えている。
【会長】
今後に期待をしたい。他に何かあるか。
【委員】
今の自治会の話に併せてのご質問だが、質問の前の前提を話させてほしい。私は自治会に入っている。立山の自治会に入っている。神輿を担いだり、精霊流しも流したりとかっていうので、自治会好きなんだけど、それを前提として踏まえた上で、ちょっと意地悪な質問だが、若い人にとって自治会に入る意味と意義は何かという質問に対してどのようなお答えをいただけるのか。
【長崎市】
自治会に加入するメリットとか、そういったお話は常にご指摘をいただいているところであるけれども、まずは自助・公助・共助という中での、まずは何かあったときに自ら守るっていうことができていたと思う。次の共助っていう部分が特に地域住民の中でしっかりと大事な部分かなと思っている。若い世代の方にとっては、子育てをされている中でどれだけ共助という意識まで実際にできるかわからないが、最終的な地域住民の生命とか、防災とか、防犯活動とか、そういったのは自治会が中心としてやっているので、そういったところが地域のインフラとして自治会が存在しているというふうには認識しているところだと思っている。
【委員】
ありがとう。若い世代にとっては自治会の意味はメインでは防災と防犯みたいな認識でよろしいか。
【長崎市】
若い世代というよりも地域住民、全世代にとってということで説明をしたということでご理解いただきたいと思う。特に特定の世代に対してということではなくて、住民の全世代に対して安全をお守りするのが行政の責任だと思っている。その重要なパートナーとして自治会がまず、第一義的に共助というような行いをしていただいているというふうに考えている。
【会長】
他に何か最初の地域コミュニティのところに関して、ご質問とかあるか。続いて「(2)コンパクトで暮らしやすいまちをつくる」について、ご意見ご質問はあるか。資料の質問になり申し訳ないが、21ページを見ていただいて、これ多分具体的な施策が書かれているところの主な事業が書かれているところ。21ページの3が最初に目に入ってしまったのが良くなかったのかもしれないが、このスタジアムシティに対して補助金をだいぶ出しているような感じがするけれども、これは今ここで金額とか書いてある。これまでどれくらい出してきたとか、それから今後何か税金的な優遇みたいなのするとかしないとか、そういったようなことで何か考えているのか。
【長崎市】
総事業費約880億円のうち、補助金額というのが約43億円になる。この優良建築物の補助は今年度で補助が完了するので今年度ですべて補助は終わる予定である。
【会長】
これは総事業費880億円というのは去年1年間でということか。
【長崎市】
これは全体である。
【会長】
補助金は去年1年間で43億円入れたということか。
【長崎市】
これはトータルである。今年度まで含めての数字である。
【会長】
そんなに大きくはないってこと。今後補助はないのか。
【長崎市】
事業の完了を目的にしているのでこれで完了となる。
【長崎市】
追加で補足にはなるが、スタジアムシティのいわゆるハード面に関しての補助についてそういったものがないけれども、今年の10月が開業になるが、そこから1年間ぐらいは、例えばこれまで長崎で開催できなかったようなイベントなんか開催してくれようとするところには、一部その開催費用の補助を出したりとかソフト面での補助についてもしばらく続く形をとっている。その原資については企業版ふるさと納税なんかで納めていただいた部分を使ってやらせていただくというような形を検討している。
【会長】
このスタジアムシティに関しては先月やったビジョン会議のときにも少し話題になったけれども、まちの中心が、長崎の中心がずれだしているということが意見として出てきているし、私もなんとなくそんな気がしていて、長崎駅から昔の浜町、中通り、新大工あの辺がずっと寂れだしているような気がする。この評価とはちょっと違うのかもしれないが、全体的なまちづくりっていうのをもう1回考えていかないといけないのかなと。コンパクトシティとしてまちを中心に集めていくのはいいけど、逆に言えばこれ100万ドルの夜景がなくなるっていうことになる。みんな下に降りてきているから、そういう意味で長崎の夜景を犠牲にしている側面も出てきやしないかと。そのようなことの心配になってくるので。ちょっと違う話になってしまったかもしれないけれども、そういうことも含めて、第3期の話になるのかな、考えていただきたいと思う。
【長崎市】
まさに今の話だけれども、実はこの件はもうドストライクのところの話ではある。実際おっしゃられたように駅周辺から先ほどスタジアムシティの話があったが、開発というか投資はあちらの方に進んでいる。おっしゃられたとおり旧来の長崎のまち。本来なら新大工から浜町のところ、まちなかと呼んでいるけれども、あちらはやはり長崎市の母屋という考え方もずっと変わらないので、駅周辺に集客した人たちが、集まってきた人たちがあちらの方に流れるようなことっていうのはずっと考えていかないといけないと思っている。そんな中で、この中にも少し書いているけれども、今県庁跡地から旧長崎市役所跡地のところが、それぞれの跡地はまだ今のところは活用までには至っていないけれども、あそこを越えていただくっていう導線が必ず必要になる。だから、あそこを活性化するっていうことも必要なので、ちょっとあそこの間をほこ道っていう制度を用いて少しにぎわいのある通りにできないかとか、そういうことも考えながら、これまで通りのまちの中心部の方にも人に流れていってもらおうというのは施策の大きな考え方なのでこれからも検討してずっとやっていきたいと思っている。
【会長】
次の第3期の目標になるかもしれないけど、そういう話もちょっと今、余計なことかもしれないけど言ってしまったので許してください。
それから「(3)地域をネットワークでつなぐ」っていうところはいかがでしょうか。
【委員】
コンパクトシティの問題と地域のネットワークでっていうのがあるけれども、いわゆるコンパクトシティの範囲っていうのはどこまでがコンパクトシティと考えているのか。
【長崎市】
20ページの先ほどの主な事業の将来都市構造って書いているがネットワーク型コンパクトシティとして長崎市全体をとらえている。これは平成28年12月に都市計画マスタープランを改訂したときに定めた将来都市構造になる。要するにその頃は人口43万人が20年後には35万人に減っていくと。8万人が20年で減っていくと。そんな中でも暮らしやすいまちをいかに次の世代に繋いでいくかっていうのがテーマで、将来都市構造を定めたものである。要するには病院とかお店、様々な都市機能というのがまとまって初めて効果を発揮するということであったり居住についても、まばらに暮らすよりはお互いにある程度密度を保った中で生活した方が都市インフラの維持であったり、そういった居住であったりがしやすいということでそれぞれ集積度は都心部であったり、あるいは地域の拠点であったり、あるいはもともと合併町の中心だった生活地区であったり、集積度というのは違うけれども、それぞれの地域地区の特性に合った形でのコンパクト。ただ長崎市は明治22年から始まっているけれども約130年の中で12回合併している。ということは一極集中型のコンパクトシティではなくて、ネットワーク型っていうのを頭につけているのは繋がりを持って初めて市全体が成り立つと。要するに地域の拠点を各生活者の皆さんが使いに来てもらわないと成り立たないレベルの施設もある都心部も然りである。そういった形でネットワーク型のコンパクトシティを目指そうというのが市全体の考えということになる。
【委員】
この問題と地域をネットワークで繋ぐっていうのは関連しているということか。
【長崎市】
そうである。長崎市が持続可能であるためにはまとまりと繋がりというのは両輪で進まないといけないという考えである。
【会長】
今の話と関わるのかどうか。長崎市の方もご存じだと思うが長崎大学がトヨタ財団からICTを活用した地域の繋がり支援を通じた地域コミュニティ活性化プロジェクトとかいう。かなり長い名前のプロジェクトの予算をとっていて、そういう意味では、先ほどのコンパクトシティもそうだしそれからオンラインを通じた市役所を使いやすくするとかいったことを全部含めてそういう予算を今年から来年にかけて取っていると思うので、そういったところと連携して、1つのあり方というか個々での課題の解決と言うかそういったことにも役立てていただけるのか。役立てていただきたいというふうに思う。
他は何かあるか。そうすると検証シートの方のこれまでの4年間。そこの振り返りの方になるけれども、ここについてはいかがでしょうか。
【委員】
一番最初のところで質問があり、総合評価のところの数値目標で3ページ目になるけれども。3ページ目に住みやすいと思う市民の割合っていう数値目標と、あと自分が住んでいる地域に愛着を持っている市民の割合という数値目標が2つ出ており、愛着を持っている方は年々減少をしているっていうのが実績として出ている。住みやすいと思う市民の割合は令和5年は若干令和4年に比べると上がっているものの、令和4年に急落というか、数値がどんと下がっているという状況があるのでこの辺りが人口にも関連してくるのかなと思うところがあるので、年々減少しているもしくは令和4年に少しどんと数値が落ちた理由とかっていうのがあればお聞きしたいし、それの理由はわかっていて対策とか今考えられているのであれば、そのあたりまで踏まえてご教示いただければと思う。
【長崎市】
まず、住みやすいと思う市民の割合、まずこれがどこから来ているかっていうような説明だが、これは毎年実施をしている市民意識調査という中で実施をさせていただいている。それがどういうような方に送られているかっていうと市内で2000人抽出するけれども、各エリアの人口構成などを見ながら無作為に抽出している。そういった方にアンケートをお出しした結果、約50%の方から返事をいただいているような調査になる。そういった中で、完全に分析できているわけではないので申し訳ない。傾向として今とらえさせていただいている状況ではあるが、一つ考えられるのは、例えば、住みやすいと思う市民の割合というのが下がっているというところだけれども、おそらくエリアによっては住みやすくなっている方もいらっしゃる中で周辺部の方も同じような形で人口構成に応じて送っているので、いろんな条件状況はあるんでしょうけれども、例えば思い起こしていただきやすいのは、バスのダイヤが少し変わったりとか、そういったところからやはり少なくとも出てきているので、そういったところで、そういったところにお住まいの地区の方については住みやすさのところのポイントが下がっているんだろうなというのが想像である。そこまで詳しく分析できているわけではないが、そういったことを考えているので、そういったことに対しては、公共交通の部分を全くなくなってしまうことがないようにできるだけ効率化をしながらそこを維持するとか、そういった対策に一つずつ取り組んでいくべきだと思っている。それから、下の方につきましては私もこの傾向については気になっていて考えたがなかなか答えに行き着いていない。基準値のところ上の表を見ていただいたところで、基準値のところ令和元年度が70.5%で令和12年が実績のところでいうと79.9%、それから令和3年が77.5%というところで、ここちょっと理由がわからないんがどちらかというと令和2年度が少し異常値が出ているかなというようなところもあり、下りの傾向が顕著に見えているのかなと思う。そういった中では全数調査ではなくて、サンプル調査になるので必ず誤差というのは数%出てくるのだがその数%の枠の中から令和2年度に飛び出している状況かもしれないと思っており、もう少し長期的に見ていく必要があると思うが、これがもしかしたら実際の数字かもしれないので、長崎市に愛着を持っていただくというか長崎を愛する心を育てるというような視点で事業は続けていかなきゃいけないとは思っているところである。
【委員】
今住みやすいと思う市民の割合とか、自分が住んでいる地域に愛着を持っているかとかこれは漠然としている。だから何で愛着を持っているのかとか。やっぱりなぜ住みやすいと思っているのかとか、そこまでやっぱり落としていく必要があるんではないかと思う。それともう一つは、今、大村市にどんどん長崎市の住民が出て行っていると思うが、そういう問題も含めて、これ諫早市の方に聞いても諫早からも出て行っているという話で聞いている。この傾向っていうのはやっぱり今後もなかなか改善できないんじゃないかという思いがあるけれども、その辺のことに関しては何か情報をお持ちか。
【長崎市】
今のお話については、今人口減少対策の重点プロジェクトでアクションプランというのを作ってやっているけれども、おっしゃる通り諫早にも長崎市から出て行っているが、県内だと諫早大村の方に出ていかれている方がそれなりにいらっしゃると。そのタイミングを分析したところ、やはりご自宅を持たれたタイミングや結婚のタイミングにというところもあり、そういったタイミングで住宅を求めて出ていかれているんじゃないかと考えている。そういったところはどうしてもあることからやはり今ちょっと若い方たちが長崎市内に住みたいと思うような間取りであるとか家賃であるとか、そういったところの住宅がやはり少ないんだろうなというところもあるので、そういったところが民間の方とも協力をしながら、できるだけそういう住宅を供給していくというようなところとかにどんどん取り組んでいかないといけないんだろうなと思っている。もう一つはやはり産業の部分。大村諫早は今大きな企業でてきており職場がすぐ近くにあるというところもある。そうしたところ長崎市には残されたところではそれほど多くの企業が立地できるような土地はないけれども、そういった中でもたくさんの企業を連れてくることでお住まいになっていただく方も増えていくというか、減り方を遅くするというかそういったことについては取り組んでいかなきゃいけないなと思っている。
【会長】
今長崎市の駅の辺りの坪単価とかっていくらくらいか。要するに家を供給するとかって言われても、私が聞いたところだと駅周辺で200万円とか言われたことある。マンションあたりだったら7000万円とかっていう金額が出てくる。供給するのはいいんだけれどもそう買える人がいるのかどうか。そこまで考えていかないとただ供給するだけじゃ多分いかない。片淵あたりでも百何万円とかっていうあそこ売るとか売らんとかいう話のときに、売るっていう話が出てくるみたいだけどそういうときでもすでにそういう金額ある程度いくつか聞く。3,000万円4000万円とかだったりする。そうすると長崎の人がそれだけのものを買えるのかどうか、供給するっていうのはわかるけれども、これから資材がもっと値段が上がる可能性があるけれども、そのときに本当に買える人がいるのかどうかっていうことまで考えていかないと中国の人が今は東京のマンションをいっぱい買いまくっているって話が出てきている。何億円もするやつ。そういうようなことが安いから買わないかもしれないけど、そういうことが起きるような長崎になっては困るなということは思う。
【長崎市】
まさにおっしゃるとおりで今おっしゃられたような駅の周辺なんかは少し書かせていただいたけれども、今、供給自体を増やせるような規制緩和をさせていただいている。ただ、先ほども申し上げた通り物価高騰であるとか、平地のところに人気が集まっているという部分もあって今のところまだコストは下げ止まりというかまだ上がっているような状態なのかなと感じているけれども、そこはもう需要と供給の関係の中で、どこかの場面ではやはり落ち着くというところは必ず訪れると思っており、そういった意味で住宅が供給されるということが、まず今は作るところかなと思っている。若い人は平坦なところだけじゃなくてもいいはず。若い方たちに限って言えば少し離れたところでも、例えば賃貸でもいいと思うけれども、そういった形でいろんなニーズがあると思うので、マンションだけに限らず、いろんなニーズの方が選択できるような形で供給できるようにというのが今の大きな考え方でやっている。
【会長】
話がそれてしまって申し訳ない。強制的に元に戻すが、次が「(2)コンパクトで暮らしやすいまちをつくる」そこら辺にも関わってくるところだと思けれども、ここについては何かあるか。容積率の緩和とか先ほどの書かれていたと思う。ただ長崎市は容積率をかなり緩和した。だからまちなかでもかなり高い建物が建つようになってしまっているけれども。
【長崎市】
実は私が実際に実施した担当だったんだけど。長崎市ちょうど平成28年、将来都市構造を打ち出して平成30年に初めて立地適正化計画、どこに地域で使う都市機能を誘導するか。あるいは今日は7月23日だが、長崎大水害のときに傾斜度が15度以上の地盤というのが軒並み滑っているというのが、ちょうど文献であって、地形はつぶさにメッシュかけてチェックして傾斜度が15度以下のところを狙った居住度区域。これは長崎市だけ独自のそういった二つの誘導区域というのを作った。それでその誘導する施策として何があるかなっていうので、過去の都市計画の経過とか状況を調べると平成8年の長崎県から譲り受けた用途地域の指定基準っていうのが20年以上見直されていないなっていうのに気づき、その中で用途地域っていうのがいろんな用途地域の中でもう少し高い値を与えられるというのに気づいた。そういった中で、まさにこれから新幹線もやってくる。当時はJRの連続立体交差、東西がやっと結ばれる。これからまさに都市インフラ都心周辺部にかけての平坦地を有効活用することで、当時まち・ひと・しごと創生総合戦略の第2期がちょうど始まったところだったので。若い世代に選ばれる魅力的なまちっていうのが、まさにテーマになっているという中で少しでも住む場所、働く場所、楽しむ場所これを都市計画サイドから作りたいというので指定基準を令和2年に見直して全体的に容積緩和したのが令和3年3月。計算上は850ヘクタールぐらいの床が新たに生み出せるぐらいのインパクトを与えた。あとはちょっとコンパクト。当時ネットワーク型コンパクトシティという考え、人口が減るので縮退型っていうイメージを持つ中で、最初はとられてしまけれども、そんな中でコロナがきました。コンパクトっていうとインザケース、昔の都市作りっていうのはインザタイムちょうど間に合う。ちょうどよしというところの都市作りをずっと追い求めてきたけども。コロナのような万が一の場合でも少しでも都市が活動しやすくなる選択肢を与えるべきじゃないか。それでインザケースということで、特に長崎市は地形的な制約が強いということで市街化調整区域でも住宅団地を居住誘導区域に寄り添って作る場合についても認めていこうじゃないかということであったり、新しくインターチェンジができるようであれば、せっかくならそこに工業団地とか、物流団地を調整区域でも作っていいんじゃないかっていう新しいルールを私どものほうで作っていったっていうのが、まち・ひと・しごと創生総合戦略と照らし合わせて、そういった動きをしてきたというのがあるので少し紹介させていただいた。
【会長】
ありがとうございました。他に何かあるか、最後に「(3)地域をネットワークでつなぐ」っていうところがもう一つ残っているのでここはいかがでしょうか。
【委員】
この地域をネットワークでつなぐってところの「5.Society5.0の実現に向けた技術活用の促進」というのがあるけれども、この中で、公開型GIS(ながさきマップ)があって、第三期総合戦略の中にも公開型GIS(ながさきマップ)の導入って書いているけれども、今国土交通省がPLATEAUっていう三次元マップを出している。もう3年目になる。これに関しては今、東京都は100%の自治体が参加者している。あと、静岡県も100%である。全自治体が参加している。長崎県が佐世保市と松浦市、波佐見町。松浦市、波佐見町に関しては今季対策されているけれども、これは国が全自治体が参加するような指導をやられているというふうに思う。長崎県は組織的には各単体の自治体でそういう動きをやっているだけで、県そのものはまだほとんどやっていないと思う。これは、オープンデータとして公開される。このデータがそろえばいろんなサービスが災害用にも使えるマップになる。三次元、建物なんかも高さから間口からそういう情報まで書いている。グーグルマップの三次元マップみたいに見えているものはそういう情報は入っていない。道路でも幅やそういう情報が入っている。このマップにいろんな情報を重ね合わせられる。いろんな情報が連携できる。これに関してはやはり長崎市も早く取り組むべきだと私は思う。
【長崎市】
今のご意見はまさにそのとおりかと思う。同じような話として、データ連携基盤というものを長崎県が持っておられて、そこにいろんな情報を集めた上で、これはパーソナルデータの利用というところも含めて今そこに集めた情報をパーソナルデータと結び付けておけば必要な方にプッシュ型で情報を送ることができるようになるとかいうことであるので、ちょっと話は少しずれましたけれどもそういったデータ基盤を今のお話も含めたところで作っていこうという流れ自体はあるので、ご意見お受けしてそのような方向性で進んでいくべきものと考えている。
【会長】
ちょっと路線バスの話が出ていたけど、これもビジョン会議のときに運転手さんが減っているとかそういうこともあって、バスの使い勝手が悪くなっているんじゃないかというふうな話も出ていたけれども、それに対して今後、取り組みをされるということだが、そこら辺は今年、来年、さらには次の計画というところで取り組んでいただければと思うけど、運転手が増えないと簡単に済む話ではないと思うけれども、ぜひお願いしたいと思うが。よろしいか。
【長崎市】
今回の計画までは路線バスの運転手さんがなかなか集まらないというのがわかっていたので同じ路線の中でもなるべく運転士さんの数が少なくてサービス水準を維持できる方法っていうふうな形で私達の方がハブアンドスポーク型の運行というのをこれまでずっと推進してきて東部ではかなりの成果を上げてきているけれども、それも概ね効率化できるところっていうのがもう大分少なくなってきていて、ここから先はやはり本当に運転手さんの数を維持しないと路線の維持そのものが大変になってくるっていうふうなことは長崎市としても認識をしているので、ただ運転士さんの確保そのものの話を長崎市が何かをやって、即解決、何か一つで解決するっていうふうなことではないと思っているので各公共交通事業者さんとも相談しながらどういった形で私達の方が支えていけばいいのかっていうのは、今後とも考えながら、やれる支援を考えていきたいと考えている。
【会長】
運転手不足は長崎だけの話じゃないけどね。去年福岡でタクシーに乗って、急ぐんだったら地下鉄乗ってくれって言われちゃいましたけど、それくらいやっぱり運転士さんが不足しているということはあるのかなと思うが、ビジョン会議でもその話が出たので、ここでも共有しとこうかなと思っただけのことだ。一応全体的に昨年度それから過去の振り返りと話ましたけど、基本目標3について何かさらに言っておきたいとか言い忘れたとかいうことがあればお願いしたい。
特にないようでしたら、ここについてはやはり自治会の組織率それから住みやすいまちっていうのはどういうことか。そこら辺アンケートとか取られているけれども、さらにそれに基づいて今年度さらには次の計画に活かしてもらえればといったような話があったと思う。
基本的には、ここでの目標評価は長崎市の評価については概ねここに記載されている通りでいいのかなという。ここに参加されている方の意見の雰囲気だろうと思うけど、そういうことでよろしいか。ありがとう。
今後どう進めていくかということについてはいくつか意見が出てきたので、それを踏まえた上で文章を作っていただければというふうに思う。ということで本日予定していた2つの目標は、以上ということになるけれども、残りの2つの目標は明日の15時からまたこの場所で行われることになるので引き続きよろしくお願いしたいと思う。その他何かあるか。
【委員】
審議会の今後の進め方について皆さんに提案と相談だけれども。最初に担当の方から資料の丁寧な説明をいただきありがとうございました。事前に皆さん資料配られて読んでいらっしゃるかなと思うので、資料の説明に関しては3分から5分ぐらいに短くして、変更修正ないしは強調したいポイントのみご説明いただいて残りの時間を議論や質疑応答とかに当てるとより審議会が有意義になるかと思ったが、皆様はどうでしょうか。
【会長】
目標によって盛りだくさんのところとそうでないところがあったりするので、1時間ずつとかで切るんじゃなくて、長く時間をかけられると割と少し短目に済むところとか出てくると思うので、そういうことから考えればおっしゃられるように一応前提として読んでいることを前提にすれば、せめて忘れないでいて欲しいとか、ここだけは押さえた上で議論してほしいといったようなことを3分から5分、場合によっては10かもしれないけど、ご説明いただいた上で議論していくっていうのがあるのかなと。いかがか。
【長崎市】
明日の分についても事前に説明の時間を今日と同じようにしているけれども、今日出たご意見を各部会長にお伝えして、強調できるところとかに絞ってということでお話をしようと思うので、全部とはならないかもしれないけれども工夫はさせていただきたいと思うのでよろしくお願いいたしたい。
【会長】
あとは今回は評価だけど次期の目標の話が出てきている。検証シートとかを見てみると、2期までの問題点がこうだから第3期って出てくるとなんか三つの柱と一つの特定目標が全部前提となって次に流れてしまうような印象があるけれども、ここはどうなのか。
【長崎市】
基本的にこのままいくっていうことではなくて、今まずはその前提として2期の振り返りをさせていただいているので2期がどうだったかと。そして2期を踏まえて第3期の姿についても2期ありきではなくて、2期のことも当然踏まえつつ第3期に当然新しく盛り込まないといけない要素もあると思うので、今の4つの目標はあるけどそれ自体もどうするかというところの話もあるし、それぞれの目標で目指すべき姿というものを掲げていこうと思うので、そこはちょっと今までの振り返りもしつつ、第3期に新たな要素も盛り込んでしていくという形で今後議論させていただきたいと思う。
【会長】
わかりました。他に何かあるか。
【委員】
女性がいつも少ないなと思っていて、今回も変わられたんだけど4人しかいらっしゃらない。子育ての話とかってやはり女性がもう少しいた方が話が進みやすいかなと思うので、第3期のときはもう少し女性を増やしてほしいなというのが希望である。
【会長】
今のお話ともかかわるのか。以前のこの会議のときに委員からも出たと思うが少し分科会みたいなのを作って、それで議論をして、それで集約するなり何なりしてここに出してくると。ここで話しにくい話とかであっても、例えば子育てのところだったら、子育てのところでいろいろ議論ができるとかまちづくりはまちづくりで議論できるとかっていうのもあると思うのでその辺については、今すぐってわけにいかないかもしれないけど、かつてやったことがあるという話をちょっと聞いたこともあるので、今後の議論の進め方は、そこでご検討されるといいのかなと。女性を増やすって話とはちょっと逆行した意見になってしまって申し訳ないけれども、逆に言えば、そういったことに関心のある人はまたそこで議論ができるしということになると思うので、そういうやり方もあるのかなと思う。
【長崎市】
先ほどの分科会という形を設けていないが一応ワークショップ的な形で委員からも会長からもそういったご意見をいただいていたので、次期戦略を練るときにはちょっと少人数で人数を分けさせていただいて、ワークショップ的な形でご議論いただくという場を設けたいなというふうには考えている。
3 閉会
【会長】
それでは本日予定していた議題は終了したのでこれをもって本日の長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会を終了する。
以上
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く