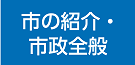ここから本文です。
令和5年度第2回 長崎市農業振興計画審議会
更新日:2024年11月12日 ページID:042938
長崎市の附属機関(会議録のページ)
担当所属名
水産農林部 農林振興課
会議名
令和5年度第2回 長崎市農業振興計画審議会
日時
令和6年3月21日(木曜日) 14時00分~
場所
長崎市役所5階 議会会議室3・4
議題
⑴ 長崎市農業振興計画の推進について
⑵ その他
審議結果
【A委員】
事務局側より第二次長崎市農業振興計画[前期計画]における取組み概要及び令和6年度の取組みにおける説明を頂いたが、委員の皆様のご意見を伺いたい。
【B委員】
取組み概要(資料2)の4ページにおいて、令和2年度~令和7年度の主な取組指標とあるが、実績はどうなっているのか。経営体系として、税金が投入されているので、しっかりとした目標をたてるのに加え、どれだけの達成がされているのか不透明なところがあるので伺いたい。
【事務局】
今回の審議会では、令和6年度の取組みについて説明をする場であり、例年、年度内の1回目の審議会で前年度の実績を発表することとしているため、令和5年度の実績については次回の審議会で説明をしたいと考えている。
【B委員】
わかりました。実績の説明については、販売額と担い手の数の2点ということで間違いないか。
【事務局】
指標については、本編の75~78ページで表記をしており、それらの項目の現状と令和7年度時点の目標、毎年度の達成状況をお見せする。
【B委員】
わかりました。
【A委員】
事務局側より重点的取組みの推進における説明を頂いたが、委員の皆様のご意見を伺いたい。
【C委員】
新規就農については、全体的にある程度増えてきた気がするが、優良農地の限界がきており、農地の確保が課題となっている。若手の多い茂木の日吉地区では、ハウスリース施設活用の要望があっているが、基盤整備話もしつつも、そういった要望に応えることができない状況である。潮見地区では農地の取得について子会社を通して、30aの農地の確保をしているが、なかなか要望に応えるのが難しいところ。前年度は国の予算がとれず、県外から来られた3名の新規就農者が就農を断念する結果となってしまった。新規就農も増加しているが、就農の減少数を補填するだけの対策が取れていないのが現状となっている。また一方で、今後、なつたより等の果樹の経営継承に力を入れていくつもりである。さきほど販売額について、総額が50億を下回ってから10年程の長い期間が経ったが、現在は48億を維持しており、施設園芸のイチゴ農家の参入による販売額の増加に頼っているところがあるが、今後も金額の維持に努めていきたい。
【B委員】
販売額については総額的にみても、少し低いように見受けられるが、農業の総括的な目標としては、担い手の増加を目指すのか販売額の増加を目指すのか、どちらを重点的に行っていくのか。
【事務局】
さきほどの本編75ページにあるとおり、これらの指標を目指すかたちで施策を進めていくつもりである。
【B委員】
現実としては、収益の見込みがないと就農者の経営も厳しくて続けられないと思われる。継続的な経営を考慮すると、販売額の増加も大事だが、個人単位での収益がどうなっているのかも把握する必要があると思われる。
【事務局】
新規就農について、国の補助を受けて半年ごとの面談を以て収支や農業の経営改善に努めており、また認定農業者においても5年おきの行政側の点検により経営改善をはかっており、全体的なところから対象を絞ったかたちでの農業経営の改善に努めているところである。
【B委員】
畜産についての記載が見受けられないが、その点どう考えているか。
【事務局】
畜産については、出島ばらいろを中心に経営を行ってもらっているが、当然販売額の実績のなかに含まれており、施策においても預託といったものがあり、7億円の予算をもって事業を行っている。
【B委員】
わかりました。
【D委員】
市内にどれだけの経営体が残っているのかを懸念しているところであり、補助金の体制があるなかで、販売額があがっていても資材価格もあがっているので、利益率を考えたときに適切なフォーローアップの体制が必要だと思われる。人口減少を踏まえると県内消費も限界があるので、県外への売上げに努めないといけないと考えている。そのため、計画についても現状に見合っているのか今一度立ち止まって考えてみる必要があると思われる。
【事務局】
物流などの各種課題については、現計画には記載がないので、次の更新の際に加味していく必要があると考えている。
【E委員】
農業推進員として、一番頭を悩ましているのが農地の問題である。茂木地区では農地の確保の課題が依然としてあり、農地だけでなくその農地までの道路も狭くて交通に苦慮しているところもある。せめてトラック一台が通れるような道路の整備をしてほしいと思っているところ。また、土地の貸し借りの話になると、昔は相対で貸し借りをしていたが、今の人たちは貸し借りを基本的にしたくないといった考えが強い。世界的な問題に目を向けると、日本は食料自給率が低いのがあり、食育推進員としても会議などに出席した際には、プランター農業でもいいから、野菜を作ろうという声掛けをしている。そのようにして色んな方面から農業に関わるような努力をしている。
【事務局】
びわ産地圃場については環境整備等で、少しでも補助がだせるようにしていきたいと考えている。農地については、茂木地区の地域計画の話し合いでもあったが、中間管理機構を介したやり方を浸透させるのが課題となると思われる。また、農地の利用については、地域単位で保全していく姿勢が大事であり、市としても積極的に支援をしていきたい。
【E委員】
農地の保全を目指すうえでの農道の確保がとても大事だと思っており、農業者に農地を勧めるうえでもそこまでの移動が困難であれば、勧めづらいところがあるので、農道の整備はなんとしても解決したいところがある。
【事務局】
対象地域について具体的な活用のビジョンがあってはじめて地元のひとたちで協力しながら、行政も介入していく話になると思うので、段階的に課題を解決していきたい。
【F委員】
琴海はいちごが盛んだが、ミニトマトの収量が落ちており、いちごに注力するのもいいが、品種を増やすのはプラスになるはずでマスカットの栽培もあったりするので低コストで作成ができる作物の導入や生産情報の把握ができれば、新規就農の増加にも繋がるのではないかと思われる。農地の集約についても、成功事例を増やすしかないと思われ、農地をまとめたことによって、どれぐらいの収益が見込めたのかがわかれば、周りのひとも活動的になるのかなと思う。
【B委員】
テレビの放映で県外の人も移住したことによって、よくなった事例が紹介されていたのがあり、そういった成功事例をPRすることで長崎の魅力も伝える方向に注力するのもいいと思われる。
【G委員】
研修生の中に3人の就農希望者がおり、そのあとにも2人の新規就農希望の方がいるが、東長崎のいちご部会で土地を調達してもらったが、5人の就農を受け入れられる土地はないと考えており、万が一土地があったとしても初期費用で負担がかかるので始めるのは難しい。県の就農センターでもいちごしか勧めておらず、今では、いちごによってしか経営が成り立つところが少ないのが現状であるように感じている。また、研修をするにしても、土地がないと話も進まないのもあり、コストパフォーマンスを懸念する人も多く、ちょっとでも日当たりが悪いとなれば、やめてしまう若者が多い。機材についても単価がとても高いので、今後も補助については継続してお願いしたい。
【事務局】
東長崎の事例ですが、農地の確保もそうですが、地元の地権者でも話の突合・調整によって基盤整備に至るまでにもかなり時間がかかるところがある。農地の確保にかかる調整については地元の人たちのあいだで話すことが重要であり、農地については、適地はどこかに必ずあるはずで、地域計画等によって密に話し合いながら推し進めていかなければいけないと感じている。また、補助についてはしっかりと支援していけるように行政側として努めていきたい。
【H委員】
生産物については、高単価で販売を目指す中で営業等に対する支援の検討ができないか。出店にかかる補助はあるが、営業を独自でやっていくなかでの支援があればと思っている。現在、ある生産者の営業の代行をしており、東京の飲食店の営業をしているが、10件ほどの商談がとれているところ。そういった中で、販路の開拓は生産者にはなかなか手が回らず難しいところかと思うので、長崎産の産品のPRのうえでもそういった支援ができないかという提案をしたい。
【事務局】
販路拡大については、根幹に対する支援はまだ希薄なところがあるがイベント等での販売に対する支援をしており、他にも一般の販売については、今度商工部との連携で農業以外の分野を組み合わせた形で検討していかなければいけないと思っている。
【事務局】
私たちとしても県へ提供する情報として、そういった営業を行える人材といった情報を必要としているので、情報提供を積極的に行ってほしい。
【H委員】
営業については、質も大事だが量的にも積極的に働きかけをしていきたい。
【事務局】
現在、物流の問題もあって、JALが飛行機を活用した物流として農産物については琴海の味彩市の商品を送るのも検討されていたり、課題解決に向けた取り組みも見受けられる。
【B委員】
今の話を踏まえて、対象の商品を絞らずに生産商品について先方が求めるものを作るのでもいいのではないか。
【事務局】
ニーズがあってニッチなものを作って、販売の活路を見出すのが一番いいかと思うので、収益が見込める方向で考えていく必要がある。また、販売については農協を介して関わっているので、個々の農家への支援として、どこまで行政が介入できるかといったところが悩ましいところである。
【E委員】
農業においては、団体で団結して話をもっていかなければならないと思う。そういった意味でも成功事例を作り、その情報発信が必要になってくると思われる。
【F委員】
県外へ販売を行うにもなにを売っているのかをよく訊かれる。琴海にしかないものを県外の方々は欲しがるので、そういった需要に対するマッチングが大事だと感じている。
直売所でもなにが売れてどれぐらいの反響があるのかがわかるのには実績がわかるのには3年かかるので、どういった商品を提供できるかといった視点で専門家の方の意見を取り入れながら先のことを考えるのも重要だと思う。広い認識にはなると思うが、そういったことも踏まえて、営業に対する支援があると経営における選択肢が増えるのでないかと思われる。
【事務局】
長崎市内にはどうしても小さな土地が多い中で、少量で多品種で販売していく方法と農協を介して大きく販売していくことと様々な農業のやり方があると思うので、その場その場に見合ったやり方を模索していく必要があるのかと思われる。
【I委員】
農業体験では、移動に30分かかっても楽しいといった声や体験に対して充実した意見が多い。需要に対するマッチングにおいては、加工者と生産者との調整をもっと密にする体制の整備が必要だと思われる。出荷数におけるトラブルがあったりするので、そういった課題のすくい上げを集会等を設けるなどしてお願いしたい。この前もマスカットの生産者から加工についての相談を受けたりしたので、PRに貢献できるように支援のやり方も検討してきたい。また、PRについては、みのりめぐみの開催にかかる課題があると感じており、人の流れについての対策がもう少し改善する必要がある。
【D委員】
あぐりの丘でイベントがあったのと、出島メッセでラーメンのイベントがあり当日の来場者が分散されたのと、会場が広かったのでどこになにがあるのかわからなかったのと、同じ場所で他のイベントと一緒に開催されたため、なにが行われているのかよくわからなかった人が多かったのではないかと思われる。
【事務局】
みのりめぐみの感謝祭については、たくさんの意見を頂いたので、それらの意見を踏まえて来年の開催時にしっかりと対策を講じたい。
【I委員】
生産について多品種あった方がいいといった意見があったが、学校給食において生産者と注文者側とで情報のマッチングが上手くいっていない旨が教育会で話題に挙がった。時期によって野菜が不足すると献立を考えるのにも苦慮するところがあるとのことで、大きくまとまった連携ができるような機会がないと今後困った状況になると思われる。
【事務局】
学校給食に関しては、以前は連絡協議会を作って、伝統野菜を取り入れるような活動も行っていたが、給食の品目における調整が非常に困難なところがあると思う。
加えて、組織作りに関してはびわ部会のような形で各地域で集まった際に機会を設けて、ネットワーク化して、行政側に働きかけを行えば、こちらも対応できるようなことがあると思われる。
【J委員】
研修においては、現在1年間といった設定があるが、状況に見合ったかたちで2年間に伸ばしたりするようなことができないか働きかけているところ。また、びわのクラウドファンディングについては、さとふる上では1500万円の寄付金を頂いた。加えて、農業振興計画においては、気象条件の変化にともなう、見直しを図っていく必要があるのかと思われる。
【A委員】
熊本県では、輸出促進協議会を立ち上げて、現在では右肩上がりで輸出量が伸びてい
るという。農地の確保においても、全体で取り組みを行っている事例がある。販路拡大を念頭に置いた、輸出に向けた取り組みに対して注力をしてほしいと感じている。
【K委員】(欠席のため文章を読み上げ)
私が住んでいる東長崎のJA長崎せいひ東長崎支店のふれあい市は多くの人で毎朝賑わっています。お客が買い求めるものは旬の野菜や魚であり、特に近隣で採れた旬の食材は飛ぶように売れております。
そのような中で、これからが旬である茹でた筍が昨年同様出品されていないので農家の方に聞いてみました。
食品衛生法の改正で、営業許可がないと出品できないのだとお聞きしました。購入するお客さんのほうでも、なんで今年も出ていないの?不作なの?との声がありました。皮付きが10個ほど出ていたが800円~1200円で商品棚に陳列されていたが、しばらく見ていたが誰も買いません、知り合いの人が声をかけてきたので自分で茹でますか?と尋ねるも殆どの人が出来ないという。
秋田名物の漬物いぶりがっこも同様で食品衛生法猶予期間の2024年5月までに製造・販売も、漬物専用の加工場を設け営業許可を取得しなければならなくなり、「改修にかかる費用をかけてまで続けられない」と多くの生産者が悩んで廃業する農家が殆どだったが、生産者の一人が「少しでも家庭の味を残していきたい」と、設備の整った加工場をシェアしようと立ち上がった例があるそうです。
地産地消、耕作放棄地対策と云いながらも鳥獣被害、食品衛生法の改正と近隣の竹林、農地へも携わる人が減少し、廃れるばかりです。
ある兼業農家の男性からも食品衛生法の法律は変えられないが秋田のいぶりがっこのような工夫がとられているのか?行政の支援やJAの対応はどうなっているのでしょうか?と会議で質問して欲しいと依頼されたところです。
この点について、わかる範囲で構いませんのでご回答をお願いいたします。
【D委員】
商品によって青果市場には置けるけど直売所には置けないものがあったりなど、国の方針がいまいちわからないところがある。出品に対しての規制において、かなりハードルが高くなっているので、個人経営の方はやめる方が多くなるのではないかと懸念している。
【C委員】
個人がどれだけの販売を行っているかを考えるとそこまでの販売を行っていない。JAについては取扱いがないので、具体的な支援は難しいところである。
【事務局】
行政の対応としても、県央振興局に問い合わせをしたところ周知はしているが具体的な支援策はとっていないとのことで確認をとっている。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く