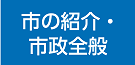ここから本文です。
令和6年度第1回 長崎市経済活性化審議会
更新日:2024年11月22日 ページID:042988
長崎市の附属機関(会議録のページ)
担当所属名
経済産業部 産業雇用政策課
会議名
令和6年度第1回 長崎市経済活性化審議会
日時
令和6年9月24日(火曜日) 15時00分~
場所
市役所5階 議会第2委員会室
課題
1 副会長の互選
2 令和5年度の取組みに係る評価と今後の取組方針
3 次期長崎市経済成長戦略の策定の方針案
4 その他
審議結果
事務局報告
※長崎市経済活性化審議会規則第5条第2項の規定により、会議の開催には委員の半数以上の出席が必要であるが、半数以上が出席しているため、審議会が成立していることを報告(出席委員は15名中10名)
※会議は公開であり、傍聴者がいることを報告
※当審議会の議事録は、要点を公開することを報告
※ 新任委員の紹介
事務局から新任委員の紹介を行った。
1 副会長の互選
委員の互選により、伊藤委員(日本銀行長崎支店 支店長)を副会長とすることと決定した。
2 令和5年度の取組みに係る評価と今後の取組方針
⑴ 事務局からの説明
事務局から資料に基づき説明を行った。
⑵ 質疑等
【委員】IT企業の集積のことで、情報関連産業2社、雇用計画455人と説明があったが、これは具体的に名前は出せるのか。
<事務局>まず、1社がリコーITソリューションズ株式会社で、製品組み込みソフト事業やそれに係るソリューション事業といった部分の研究開発をされる企業が立地しており、雇用計画としては55名を予定している。
もう一社は、トランス・コスモス株式会社で、従前、BPOで長崎市内に立地をしていたが、新しくITアウトソーシングサービスといった部分の研究開発の部門の立地が決定しており、雇用計画は400人で、合わせて2社455名になっている。
【委員】トランス・コスモスは、400人をいつまでに雇用する予定か。
<事務局>雇用計画自体は4年間で、スタジアムシティに立地することになっており、今年度以降4年間かけて400名ということで伺っている。
【委員】表現上の問題だと思うが、資料6ページの人手不足対策のところの右側の当面の課題のところで、「小学生から大学生に向けた情報発信の手法」というところがあるが、読み方によれば、小学生から大学生に向けて情報発信するような読み方にもなるので、説明が必要かと思う。どういう形で情報発信するのかは、付け加えが必要ではないかと思う。
<事務局>説明が不足していた。まず、人手不足という流れの中で、一つの大きな要素として地場企業のことを十分に知っていただくことができていないという課題があるかと思う。その中で、特に、今まで重点的に、大学生や高校生等の若者に対して情報発信してきたところではあるが、定着に繋げるためには、さらに長期のスパンで、いわゆるキャリア形成という意味合いで、現在も実施している学校もあるが、小学生や中学生に対しても、例えば、授業の時間で企業を知っていただくような取組みを強化していかなければならないと考えている。また、高校生等については、今、保護者等に向けた情報発信等を行っているが、高校生には新たに割ける時間がなく、なかなか伝えられていないということがあるので、県が学生と保護者向けに職場体験などを実施していることから、県と連携して情報発信をしていけないかと考えている。また、大学生等についても、今まで一方的な形だが、ホームページ等を使ったり、SNSを使って情報発信を行っているが、なかなか見ていただけないということがあるので、大学生の授業で大学生と企業とを繋ぐような取組みができないか、今、検討を進めている。そういった意味で、小学生から中学生等に向けては、キャリア教育的な情報発信をしていきたい。大学生等に向けては、授業等でさらにコミュニケーションを増やしながら、情報発信を強化していきたいと考えている。
【委員】今の説明を伺ったらわかった。この記載は、小、中、高、大学生とはっきり書いた方がわかりやすいかと思う。
<事務局>そのように修正したい。
【委員】インスタグラムやエックスを使っているが、このような情報を見たことがない。どのような表示にしているのか。
<事務局>「就活シェアル」というSNSの名前で、インスタグラムやエックスなどで情報発信をしている。
【委員】「就活シェアル」というと、もともと高校生と大学生を対象にしたアカウントで発信している形か。
<事務局>4、5年前までは、ホームページ等で行っていたが、データ等を見ると、やはり今の大学生の8割以上はSNSを見て情報を取っているため、そのようなインスタグラムやエックスで取組みを開始した。
【委員】これは人手不足対策なので、働く世代とすると、高校生や大学生を対象にしなくてもいいのではないかと思うが、同じような内容を他のアカウントで発信する考えはないのか。
<事務局>あくまで、中心として高校生、大学生だが、若者も含めて広く公開しているので、UIJターンにもリーチをかけられるよう、周知の強化に努めていきたいと考えている。
【委員】資料4ページの大学連携のところを、銀行の取組みとして説明させていただきたい。私ども十八親和銀行が合併した2019年10月に、長崎大学とFFGで、アントレプレナーシップセンターというものを設立させていただいた。主に、活動が2つあり、まず、アントレプレナーシップ教育人材育成で、大学生あるいは社会人向けにアントレプレナーシップ教育をやりましょうということと、もう一つ、大学発ベンチャーの創出、起業家活動支援という二つの柱がある。当初は、教育プログラムの方に比重があり、なかなかベンチャーを発掘できてなかったが、2022年4月に大学でベンチャー称号授与規程を制定され、そういった活動をされるベンチャーへ称号を授与することが始まった。現在、8社が認定をされている。この中の1社が、今日来られている北村先生のNLaboさんで、認定を受けられている。
私どもFFGの子会社で、福岡ベンチャービジネスパートナーズというベンチャーキャピタルがあるが、長崎大学には本当にたくさんのシーズがある。ただ、そのシーズは、なかなか事業として表に出てこないということをよく聞かされていた。一方で、ベンチャーで少しずつ動きも出てきており、銀行としてもこの分野は非常に力を入れていきたいと思っており、創薬分野ではがんの治療薬、すごい薬を作っている先生もいらっしゃると聞いているので、いろいろな場面で情報開示やお知らせもしていきたいと思っている。
資料5ページにグルーズ船のことが書かれており、毎日のように大きなクルーズ船が入ってきていると思うが、港の近場で、人だかりができていて、何も消費もされていないような、そういった観光客の方をたくさん見かける。取引先の中華街のお店などに行っても、表にものすごく人通りがあるが、店の中で全く食べてない。店の人に聞くと、あの人たちは食べないという状況になっているようだ。ただ、あれだけ人が来ているので、ある意味ビジネスチャンスにもなっていると思うし、ああいう方々の消費行動や、どういった市内の観光をしているのかなど、そういった調査などがあれば、どんな手を打つのか、地元にお金を落とす仕組みが作れないかなどを考えることができると思う。長崎市では、そのようなことをされているのか。先般、高知のひろめ市場という全国で有名な屋台村みたいなところに行ってきたが、もうすでに有名でたくさん人が集まっているところでさえ、営業活動を一生懸命されているという話もお聞きした。高知もクルーズ船が入るらしいが、そういった方々向けにも活動をしていると言っていたので、せっかくの交流人口なのだからそういったこともやらないといけないんじゃないかと思う。
<事務局>クルーズについては、動向調査を行っている。これは、県とも共有させていただいているが、DMOで調査をしている。コロナ前と比べると、アジア、特に中国からのクルーズが若干減って、欧米系が多かったというのが昨年度で、今年度はアジアの特に中国の方が復活しているという状況だ。
動向について、市内を含めてアンケートをとると、特に中国の方がカジュアルクルーズでも2万1000円ぐらいの買い物をされている状況はある。しかし、買い物をされている多くは、ドラックストアなどが依然として多い状況だ。飲食についても、市内のラーメン店に行かれるような状況もあるが、隈なく入っているかといえば、そうでもないようだ。クルーズ客船の受入委員会においても、このような調査を共有させていただきながら、また、DMOでもアンケート調査はホームページでも公開をしている。せっかく来ていらっしゃる乗客に、買い物やランチなどでどれだけ消費を促すかが重要だと思っている。中国のクルーズに関しては、やはりランドオペレーターの動きという部分で、なかなか市内飲食店に入っていただくことへの働きかけが十分ではないので、しっかりと検討し、働きかけも行いたいと考えている。
【委員】どこから来られたかによる部分も大きいと思うが、ある時はコンビニの周りに多くの人がいて、コンビニの物を買うということがあり、自分たちもコンビに近づけないぐらいの人だかりがあったりするので、こういう人たちを受け入れるような場所や、何を好むかにもよるのだろうが、それがわかれば、何かヒントになるのではないかなと思って質問した。
【会長】DMOや県、あるいはシンクながさきさんが観光にターゲットを絞った、より直近の、ほぼ時差がない形でデータが活用でるような仕組みを検討していると聞いているが、おそらく市では取り組まれていると思うので、そのデータに基づいて、対策をどう作っていくかということが、次期戦略の1つの重要な柱になってくると思うので、その整備をお願いしたい。
<事務局>私どもも、DMOやシンクながさきさん、県とも連携をしながらビッグデータで逐一情報を収集していくものと、先ほどご紹介した動向調査としてアンケートをとりながら、どういうところに回っているか、あるいは、どれだけ消費しているかというところもまとめてやっている。新しく観光MICE戦略の方も次期に向けて見直しの段階に入ってきているので、本戦略においても、しっかり情報やデータに基づいた打ち手は、打っていきたいと考えている。
【委員】資料13ページのデータだが、人材確保の支援という部分で、市内高校卒業者の市内就職率や事業者への新卒採用状況調査における求人数に対する平均充足率において、目標値を少し下回っている。ここから何が分かるかというと、地場企業が若者世代を雇用するのに苦戦しており、選ばれていないということだ。これについては、産業部門だけではなく、まちづくりの領域で、雇用に繋げていくような施策がいるのではないかと前回の審議会でも言われていたので、それを次期戦略にも反映させていただきたい。
また、先ほど発言があったが、小学生から大学生まできちんと課題を認識し、それを働く意欲に繋げていくということで、今回は、資料4ページの生命科学関連分野で、長崎大学のアントレプレナーシップのようなところで、きちんと大学発のシーズを次の課題解決の事業に転換していくことに繋げていく。だから、どちらかというと、それぞれの分野に施策目標を立てて、それを評価しているが、またがってきちんと読み込んで施策を作っていくという作業が、次の戦略では必要だと思うが、どうか。
<事務局>前回もご意見をいただき、雇用の場だけでなく、住宅の賃料やアミューズメントなどの暮らしやすさといった部分の長崎市全体の魅力を上げていくことが、結果的に雇用の確保に繋がることについては、もっともなご意見だと認識している。次期戦略については、これまでご指摘をいただいた、そういった分野についても、今はどういったことに取り組むことができるか答えを持ち合わせていないが、総合的にまちの魅力を高めるという視点も踏まえながら、検討をしていきたいと考えている。
【委員】課題が複雑化している分野なので、応える方も複雑化した体制でそれを届けるような枠組みが必要だと思っており、会長の言葉を借りれば、市が果たすべき役割は、プラットフォーマーとしての役目を見える形にしていくことがとても大事だと思う。いろいろな問題をもたらすところに対して、答えを打ち返していくという枠組みを見える化していく拠点や制度を整理していくのが、今後、求められていることだと思う。
私もアントレプレナーシップの1期生として学ばさせていただいた。そのときに大学生とずいぶん多くの大学発シーズをもとにしたビジネスモデルを一緒に考えてプレゼンまで行ったが、長崎大学が所有している知的財産を活用している領域など、とにかく柔らかい頭で、まだまだ掘り起こすことができると思った。小中学校でも、ふるさと教育を進めているので、教育委員会部局と市長部局が次の長崎のアントレプレナーを育成していき、しかも、それが長崎大学にあるシーズを活用でき、また北村委員のようにそれを事業化されているところがあるので、そこと意見交換などを行い、次の世代を巻き込んだ形のプラットフォーマー的な役割を果たしていただきたい。
もう一つ、資料5ページの交流分野だが、長崎市は、観光の交流による観光消費額の最大化をめざしていると思うが、旅マエ、旅ナカと、もう一つ、旅アトの物産振興において、特に食品に絡む一次事業者、二次事業者の可能性をもっと掘り起こす必要があり、まだコロナの前には交流人口が戻っていない中で、そこそこやれているという実感があると思うが、私の中でまだまだやれる領域があると思っている。高知市のひろめ市場の話も出たが、長崎の物産を食べたり、飲んだり、送ったり、それを活用したりというところは、まだ掘り起こせると思っているが、そのあたりの認識はいかがか。
<事務局>まさに旅マエ、旅ナカ、旅アトで物産振興に繋げる取組みを推進させる目的で商業振興課の組織体制を改編した。旅マエでしっかりと長崎の魚などの魅力の発信を行い、旅ナカで地元の飲食店やお土産屋さんなどで消費していただき、旅アトでふるさと納税に繋げるような一連のスキームを築き上げている。DMOとも協力し、効果的な情報発信について、今まさに検討と実施をしている段階であり、皆様のご意見をいただきながら進めたいと考えている。
3 次期長崎市経済成長戦略の策定の方針案
⑴ 事務局からの説明
事務局から資料に基づき説明を行った。
⑵ 質疑等
【委員】資料にも様々な課題があげられており、課題は十二分に認識されているかと思うし、その解決に向けてのいろいろな施策を実際にやっていることは認識している。ただ、もっと力を入れてやってほしいと思う点が、例えば、100年に一度というワードだったり、数年前からキーワードとしている交流の産業化のところだ。駅ができて、新幹線が開業して、今後もスタジアムシティもできて、ますます人がやってくるような状況になっている。せっかく人がたくさん来ているのに、お金が落ちているのかという部分に対して、この数年で長崎市にどれほど変化があったのかと思う。私は、昔から平和公園周辺に住んでいるが、クルーズ船が入った時はたくさんの人が来ているし、修学旅行シーズンもたくさんの人が来ている。ただ、お金を落とす場所がない。不思議なまちだと思ったりもする。あれだけ人が来ているのに、全く買い物するところもなければ、横に被爆者の店があったが、閉めていて、本当に消費がなされないまま、観光客がただただ通り過ぎているという状況になっている。せっかく来ているお客さんに対して、食べるところやお買い物をするところがない状況をどうやって、お金が落ちるまちに変えていくのか、それを雇用に変えていくのかということが課題であると、皆さんも認識しているはずだ。一方で、居酒屋や蒲鉾屋などお買い物や食べるところを市役所の職員の皆さんがやるわけでもない。そこに何かギャップが生まれていると思う。結局、課題が分かっていても、民間がすることだから、市役所がそこまですることじゃないというギャップが生まれていて、いつまでたってもその課題解決に結び付いていない状況ではないかと思う。それでは、市役所は何をすべきかというと、場所の提供であり、これに尽きると思う。民間の方々が場所探し、土地探しをする際に、公共が持っている土地をいかに活用するかという提案や提供、相談なりしていくことが、役所の役目ではないかと思う。例えば、長崎駅ができたが、駅周辺の一番大事な場所が未だに更地のままで、誰が持っているかというと、長崎市が持っていたりする。100年に一度と言いながら、駅が完成して、このような状況になっているにもかかわらず、何年も前からこうなるとわかっているのに、いまだに土地の活用は決まってもいない。銅座川プロムナードもそうだ。10数年前、駅が完成する暁には、ほぼ完成させる目標でやっているというような話を聞いていたが、全くできていない。浜町の再開発にしてもそうだ。いろいろな理由があるのはわかっているが、なかなか進まない。
経済に結びつくような土地の活用を考えた時に、その土地は、土木部、まちづくり部、教育委員会、理財部などが持っており、経済部局は土地を持っていない。これもネックだと思う。長崎市の中で、いろいろな土地の活用を考えてはいるだろうが、経済を第一優先に置いた土地の活用ができていないということは、検討の最初の段階から入れていない現状があるのではないかと議員の立場で見ていて思ったりもする。今後も経済部局がそこに入る余地がなければ、変わらない未来があると思う。その点は、非常に懸念するところであり、こういったことを念頭に置いて、新しい動きを今後の戦略の中でやっていただきたいと思う。
<事務局>土地については、いろんな場面で課題として認識しながら、また意見交換も行ってきた経緯もあるが、土木部など他の部局が持っている土地は、目的を持っており、例えば、企業立地用地という部分で、我々はいろいろな土地を探したりするが、そういった部分では、なかなか扱えないといった立場もある。一方で、まちづくり全体の話をしないとなかなか経済の活性化も図られないということもあり、我々にとっても土地の確保は非常に重要なテーマであるので、今後、関係部局と連携しながら、施策に反映できるように、そういった場合の土地の確保も念頭に置いて、やっていきたいと考えている。
【委員】市の土地のみならず、県の土地を考えた時も県警跡地、県庁跡地、公会堂の跡地として活用もでてきた常盤町の駐車場、松ヶ枝の再開発、大波止の港の再開発などがあり、県の土地とはいえ、長崎のへその部分であるこの辺りについても、ぜひ市と県との連携の中で、経済ということを考えたときに、どのような活用がいいのかを県の所管任せではなく、長崎市の経済をどうしていくんだという観点で、ぜひ入っていっていただきたいと思う。いろいろな壁があったり、行政の縦割りの中でいろいろな関係やしがらみがあるのは十分分かってはいるが、経済が活性化しないと人口対策もどうにもならないので、そこはぜひ突破していただきたいと思う。
<事務局>市有地以外の土地の活用という部分では、県庁跡地をはじめ重要な土地がある。県が進める長崎港元船地区整備構想の話も出ているが、そういったところは確かに長崎市の中心的な役割を担ってきた土地であり、また今後も同様だと思う。県有地と言いながらも、目的は同じであると思っており、市として関係部局と連携を取りながら、関与すべきところは十分関与していきたいと考えている。
【委員】この方針案に書ける部分も書けない部分もあるかと思うが、今の意見も念頭に入れていただいて、新しい取組みをしていただきたいと思う。
【会長】お店を出したい起業家にとって、場所の確保が難しいと聞いている。家賃がものすごく高く、間口が狭いところしか借りることができない。だから、税制の活用や民間の資金を活用しやすくするなど、いろいろな形で若手の人たちがそういう場を持ちやすくする仕組みをつくるような施策も併せて考えていただきたい。
福岡市でスタートアップがあれだけ旺盛になってきたのは、入ってくるスタートアッパーに対して、最初に敷金ゼロにしたからだ。最初のハードルをものすごく下げて呼び込んだことで、それが福岡を選んだ理由として大きかったというアンケート調査もあるので、そういったものも含めて全体的に考えていければと思っている。
【委員】今後の施策の方針としての根本的な部分で話をしたいが、これまでも、第四次、第五次戦略といろんな施策が進められてきたが、結果的に効果のあらわれているところと、そうでないところがもちろんあるわけで、現状、私が感じている一番大きな問題は、交流人口の拡大をしようといろんな施策が講じられたとしても、率直に言って長崎の市民、私ども商業者も含めて、交流人口が拡大することが本当に重要なことだという認識がまだ少ないと感じている。例えば、コロナ後にこれだけ回復してきて、いろいろなところからたくさんのお客様がお見えになっている。それをどうやって、我々の商売や居住などに繋げていくかということに対して、市民の方がそんなに交流人口の拡大が大事だと思ってない部分があるように感じている。これは、宣伝不足とかいうこともあるかもしれないが、最重要課題として人が増えること、それに対して地元の人が何をするのかという具体的な方策をとることが絶対に必要なことという、その重要性がまだまだ地元の私どもに伝わっていないというか浸透していないと感じる。それでは、どうするかということだが、皆さんに知っていただくための今後の経済成長戦略の一番柱には交流人口が拡大して、県外に行く人が増えたり、少子化、高齢化が進んでも、それによってよそから来る人で稼ぎ戻せるというようなはっきりとしたメッセージをみんなが持っておかないといけない。何やっても一緒だという諦めみたいなものが商業者の中にあったり、もう自分の代でこの商売は継げられないということがあったり、そういう空気が蔓延していくと、結果的に、まちの魅力としての1軒1軒のお店がなくなっていったり、その魅力が感じられなくなってもっと面白くないまちになっていくとか、そういう悪い連鎖みたいなものになっているのではないかと感じる。従って、これまで、施策の内容はこうあるべきだろうということは、いくらでも出てきたわけだが、これを長崎市民の方々を含めて、全ての人たちに一番大事なことだということをどう知らせていくかということに、もっと力を入れないといけない。これは、我々、地元にいる人間の責任でもあるし、それを感じて何をやるかという実行力の問題にもなっていくわけだが、そういう意味ではまだ浸透しきれていない。そう言いながら、他の施策もいろいろと出てくるので、交流人口拡大というのが二の次、三の次になって、新しいビジネスを構築しましょうということなどが優先されたり、昨今よく聞く、いわゆるオーバーツーリズムの問題が出てきたりする。これは、とんでもないマイナスであって、もちろん対応が必要だと思うが、やはりその根元に、交流人口の拡大の重要性というものがまだ伝わっていない部分があるので、これをどうやって皆さんに伝えるかということにもっと力を入れるべきじゃないか思う。それでは市としてどうするか、我々は何をすればいいのかという具体的なことで言えることはないが、現状の感覚として、今後、施策を進めるにおいては、人口拡大の重要性をしっかり伝えるということにもっと力を入れていただきたいと思う。
<事務局>ただいまのご指摘は、ごもっともだと思っている。100年に1度のまちの基盤の整備が、今度の長崎スタジアムシティの開業で、完成に近づくということもあって、多くのお客様がお見えになる。そこで、オーバーツーリズムの問題など、消費に円滑に繋がらないという問題、課題が出てくると、非常にマイナスのイメージにもなり、そのような新たな要素をしっかり念頭に置きながら、受け入れの重要性をどのようにお示ししていくのか、皆さんのご意見を伺いながら、整理をしていきたい。
【委員】私は、オーバーツーリズムのようなことが出てくるのは、致し方ないと思っている。従って、このような問題が出てきたときに、どう対処するか、あるいは全市的にどういう方法を講じながら超えていくのかをしっかり考える必要がある。
もう一つは、交流人口の拡大が最重要課題として据えられていない一つの理由として、長崎に来る人、あるいは長崎の人が活発になることが、何よりベースとして必要だという認識がまだできてないという意味で、これに対して、いろいろな施策を講じたけれど、それが本当に長崎の魅力や発信になってない。身近なところで例をあげれば、長崎市はまちぶらプロジェクトという取組みを行っているが、これは非常にいい事業だと思っており、その中でいろいろな事業がたくさん認定された。地元浜町も認定をされた。そういう意味では、まちなかを活性化しようという認識はある意味伝わっていると思うが、まちぶらプロジェクトにたくさん認定された結果として、まちなかの魅力が一つの塊になっているかが、次の課題だと思っている。そのような認定や事業を選定されることは、大変いいことだと思うが、結果的に、それをまとめてまちなかの魅力として看板を上げられるかどうか。一つ一つの事業も大事だが、それを集約して地域の魅力として仕上げられているかどうかということが、次の戦略の中に反映されるべきではないかと思っている。
【委員】説明では、次期戦略の方向性としては、基本的にはこれまでの戦略を踏襲しながら、調査等に基づいて、必要な施策を追加、修正、削除していくという話だったと思う。一点目の議題とも関連するが、これまでの取組みの評価をどう反映させていくかということが重要ではないかと思っている。ご説明いただいた4分野と人材確保について、現段階で市として、この分野はうまくいっていて、この分野はなかなかうまくいってないという評価の濃淡が、もしあればお伺いをしたい。
<事務局>成果の部分でうまくいっているところと、いっていないところだが、全体を通して、施策として全て上向きだということはないが、そういった中でも、例えば、企業誘致の分野では、重点施策に掲げて、4、5年前と比較すると、IT分野のオフィスなどの誘致が進み始めてきたということがある。また、これから、海洋ものづくり分野について、民間でも洋上風力の付帯設備への参入の兆しがあり、今年11月に海洋分野の訓練施設が新たにできるなど、一時期、造船や海洋分野が厳しくなってきたということがある中で、新たなGXの分野での可能性が広がりやそのような新たな動きが出てきている。市としても、海洋分野、原料で言えばアンモニア、水素などの部分、また、航空産業など、短期的な構造転換は難しいと思うが、そのような長崎ならではの部分について、しっかりと下支えをしながら、動き始めた部分について、中長期的に強い産業、成長産業として育てていきたいと考えている。
一方で、全国共通の課題だが、人手不足については、ここ何年かで顕著となっており、これらの構造的な問題が大きく左右してきているのではないかと考えている。というのが、これまでは企業を誘致すると、そこに雇用ができ、新たな需要が生まれるというような良い形であったが、構造的にも人がいなくなり、パイの取り合いになってきている。これは、長崎だけでなく、全国的なトレンドになっている。大学生の皆さんに聞くと、内定を早めに3つか4つぐらいとって、その中から一番いい条件のところに行くという状況がある。なかなか人手不足への対応は、うまくいっていないというところだが、そういった中でも、長崎の企業の魅力を発信するとともに、若者に選ばれるような魅力ある企業になるための支援として、新しい働き方の伴走型の取組みや、女性活躍のための補助金の支援を行っている。また、バングラデシュのⅠT関連人材を確保しようということで、今年度から県、長崎大学と連携して外国人の活躍のための取組みも始めており、こうした人材確保に向けた施策にもしっかり取り組んでいきたいと考えている。
【委員】行政に期待する役割や取組みの一つは、カーボンニュートラル関係もそうであるが、めざすべきビジョンが社会へのスムーズな移行・実現に向けて、その契機となる先導的役割を果たしていただくことや、それがうまく回るような仕組みや交流などのプラットフォームを提供いただくことが重要だと思っている。それが社会に定着し経済合理性を含め民間で活性化するようになれば民間主導でやってもらえればよいと思うので、このような点を踏まえて、ご検討いただければと思っている。
【委員】私は、市の認識もそのとおりだと思っている。この第五次戦略の間に起きてきたことは、やはり人手不足に尽きると思っている。経済界として、いろいろとヒアリングをしているが、例えば製造業、大島造船さんがきていただいて、一応、稼動は本格的に始まった。第1船は引渡しまで終わっている。大島造船さんは、西海市でも埋め立てが完了し、また工場を広げられる予定だが、今、一番困っているのは、人手だ。香焼でバルクキャリアを造っておられるが、今の人数だと年間4隻しかできない。ところが、今は造船業界も様変わりで、受注残をおそらく3、4年分持っていらっしゃる。船価も非常に上がってきている。船主さんにしてみれば、早く引き渡してもらったら絶対助かる。非常に恵まれた環境だが、人がいないから、造れない。かつては、三菱重工さんもやっていらっしゃったことを考えると、おそらく、人を倍かければ、キャパシティーからして、8隻ぐらいは十分できるはず。だから、その人たちも、相当努力されているけれど、なかなか難しい。ある意味3Kの職場だから、こういう気候の中では、大変な仕事になっていると思う。
また、交流人口の話だが、交流人口を増やすために、ナイトタイムエコノミーなど宿泊させて消費を増やそうという施策でやっていると思う。新たにホテルも増えるが、人手がいないから部屋はあるけど稼働できない状況だ。長崎もまた数百室増えるから、おそらく人手の取り合いになる。この問題をどうするかの答えは難しく、毎年、人口が5千人減っているのだから、その中での取り合いになってしまう。これは、やはり最重点課題だと思う。どう解決するかは、本当に知恵を出さなければならないと思うが、どの分野を伸ばそうとしても、最終的にはそれにぶつかる。伸ばしたい気持ちはあっても、伸ばせないというのが現状ではないか。
【会長】労働者不足というのが、成長戦略を考えていく上での非常に大きな制約条件としてかかってしまうのではないか。その打開というものを次期戦略の中でどう盛り込んでいくのか。少なくとも、どのような芽を作っていくのかということを書き込んでいくことが、一つの重要な次期戦略への課題ではないかというご意見だったと理解した。その点も踏まえて、次期戦略に活かしていただければと思う。
4 その他
【委員】資料を配らせていただいた。この日本の都市特性評価は、森記念財団が毎年発表されているもので、今回は7月25日ごろに発表された。2023年と2024年での比較を見ていただこうと思い、概要版をお配りした。県民所得は、各県で比較ができるが、市を比較した数字はあまりなく、市民所得というのはあまりない。この森記念財団のものは、公的なデータに基づいて、よく調べてあると思うから、一つの資料としては、見ておくべきだろうと思っている。合計スコアでは、長崎市は去年は27位、今年はなんと52位になってしまっている。以前、長崎市の人口は40万人あり、一昨年の7月に割ったと思うが、8月に長崎市が宮崎市より下になってしまったことがショックだった。長崎市の人口が40万人を割るのは、推計されていたので、時間の問題だと思っていたが、どうして宮崎市が長崎市より上に行くのかというので、宮崎市を注目しているが、これでも宮崎は逆に上がっている。2023年は宮崎市が29位で、長崎市より下。2024年は宮崎市が23位で、長崎より上。そして、もう一つ加えると、隣の佐賀市がどうなっているかということに興味があったが、2023年は42位、2024年は41位で、ステイだ。この結果として、九州7県の県庁所在地で、残念ながら長崎市が最下位だ。
これは、6分野での分析があり、経済分野でいくと、長崎市は80位以下で、2023年も2024年も変わっていない。6分野の中で、経済分野が一番悪くて136都市中、120位。これには、詳細の項目が87項目くらいあるので、それを見ていけば分析は可能だ。SWOT分析ではないが、そういうことをやれば、何が長崎市の弱みなのかが出てくると思う。それくらい分析する価値があると思っている。
企業誘致がいろいろな施策の中にあり、今まで、割と順調にきていると思う。一番気になるのは、各企業が長崎へ行くかどうか決めるために、他の都市と全部を比較するわけだが、その時にこれが間違いなく使われる。ランクだけがすべてではないと思うが、座して待つよりは、ランクを上げる努力もするべきだ。弱いところを見るべきだ。経済分野はトータルで120位だが、経済分野で21項目あって、100位以下の項目は10項目くらいある。ここは特に弱い。この中で一番気にしているのは、可処分所得で、長崎の経済の中で一番大事だと考えている。可処分所得を増やすことが、最終的な目標と言ってもいいぐらいだと思うが、可処分所得は経済分野の中に入っていない。生活、居住という分野の中に入っている。可処分所得は、なんと長崎市は3位だ。これは、総務省の家計調査で、5年に一回しかやってないから、2019年のデータだ。3位なので、それを総務省に問い合わせ。それでわかったのは、確かに3位だが、2019年だけ特別収入が13万円くらいある。この中身は、総務省も教えてくれない。それで、ランクを押し上げている。だから、2019年は、この13万円を入れて53万8000円だ。ところが、その5年前のデータでは、34万4000円。今年は、5年ぶりの調査があっているはずだが、おそらく元へ戻るか、ひょっとしたら、下がるかもしれない。それは、ランクを下げる要素になってしまうので、次期戦略を作る中で、こういうものも参考にされて、経済だけではないかもしれないが、どの分野をどうすべきかという議論の一つの資料にされたらいかがかと思って持ってきた。
【会長】都市のランキングにおいて、どういった項目が効いているかについて、ある研究者によれば、それは、産業の大きさと、文化交流の分野だ。経済と文化交流の部分が、その都市の人口を引き付ける要因として、ものすごく効いている。福岡は何が強いかというと、やはり経済・ビジネスと交流文化の数字が高く、それらが都市の魅力度を上げる非常に大きな要因として効いている。そして、若者が非常に敏感に反応することが結果として出ている分析もあるので、どこまで信じていいかは疑問もあるが、市としても統計部署でこのデータを分析してみるということも、委員の問題提起からすると、あっていいと思う。
【委員】補足すると、長崎市は、文化交流がトータル9位だ。ここだけ一桁の9位。中身を少しだけ申し上げると、文化交流の中で一番高いのは、景観まちづくりへの積極度で、これが2位。それから、文化、歴史、伝統への接触の機会が7位。イベントホールの座席数は8位。決して少なくはない。あと観光地の数、評価、これも8位。これらが、一桁台となっている。
【会長】紹介していただいたデータからわかることは、おそらく、そういう器はできているが、長崎は福岡に比べると、そこに入ってくるコンテンツが相当足りないだろうということだ思う。だから、そういうことを含めて、今後、次期戦略を考えていく上では、いろんなご意見を加えながら、考えていきたい。
【副会長】いろいろ活発なご議論をいただき、今年度の評価についても、具体的な実績として上がっている事案、それから企業誘致のケースなどを挙げていただいた。一方で、ご説明いただいた中には、まだまだ抽象的なところでとどまっているものもあるんだろうと感じた。来年度は、次の戦略を作っていくということであり、ベースにしようと思っている現行の戦略では、重点分野として四つ提示をしているが、この四つの分野の中で、どれをどういう形で市民に対して打ち出していくのかというメッセージの打ち出し方は非常に重要なのだろうと感じた。四つの分野に絞られているが、具体的な施策に落とし込んでいくと、どうしてもいろいろな方の顔が見えてきて、全員の顔を思い浮かべながらやっていくと、焦点がぼけてしまうということもあるのではないかなと思う。長崎市として、どの方向に進んでいくべきなのかが打ち出せるような次の戦略づくりに関与させていただければと思う。
〔閉会〕
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く