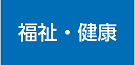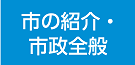ここから本文です。
事業所へ通所して受けるサービス
更新日:2024年11月13日 ページID:009539
事業所へ通所して受けるサービス
介護保険対象者(65歳以上。特定疾病に該当する場合は40歳以上)のかたで、介護保険サービスを受けることができる場合は、原則として、介護保険サービスの利用となります。
「者」は18歳以上の方に対するサービス、「児」は18歳未満の方に対するサービスです。
【児】児童発達支援
主に未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。
対象者
障害児(主に未就学児)
申請方法
障害児通所支援の申請方法をご覧ください。
【児】放課後等デイサービス
就学児(小学生~高校生)に、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進を行います。
対象者
障害児(就学児)
申請方法
障害児通所支援の申請方法をご覧ください。
【児】保育所等訪問支援
保育所などの集団生活を営む施設に通う障害児に、保育士等が訪問し、障害児に対する訓練やスタッフに対する専門的な支援を行います。
対象者
障害児
申請方法
障害児通所支援の申請方法をご覧ください。
【者・児】短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行うかたが病気などの場合に、施設に短期間入所して生活上の介護などを行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上の方
児童の場合はこれに相当する心身の状態のかた
申請方法
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
【者】生活介護
常に介護が必要なかたに、日中に施設に通って創作的活動等をしたり、食事や排泄等の介護を行います。
対象者
障害支援区分が区分3(50歳以上は区分2)以上のかた
申請方法
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
【者】自立訓練
身体機能や日常生活能力の維持向上のため、日中に施設に通って、一定期間の支援計画に基づいて訓練を行います。
機能訓練と生活訓練の2種類があり、生活訓練には宿泊型自立訓練もあります。
対象者
機能訓練は、地域生活を営む上で、身体機能・生活機能の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者のかた
生活訓練は、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者のかた
機能訓練は1年6か月間、生活訓練は2年間が、標準利用期間となります。
申請方法
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
【者】就労移行支援
就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間(原則2年間)の支援計画に基づいて行います。
対象者
就労を希望する者であり、単独で就労することが困難であるため、知識、技術の習得や就労先の紹介等の支援が必要な障害者のかた
申請方法
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
【者】就労継続支援
障害により一般就労が困難なかたに、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。A型(雇用型)とB型(非雇用型)の2種類があります。
対象者
A型(雇用型)企業等に就労することが困難なかたであって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な障害者のかた
B型(非雇用型)次のいずれかにあてはまる障害者のかた
- 就労経験があり、年齢体力面で一般就労が困難
- 就労移行支援事業を利用後、B型利用が適当と判断された
- 50歳以上
- 障害基礎年金1級を受給している
申請方法
障害福祉サービスの申請方法をご覧ください。
日中一時支援 地域生活支援事業
日中に施設などに通って受ける支援で、3種類あります。
1.日帰り短期入所型【者・児】
介護者が病気などの場合に、日中に施設で預かりを行います。
「対象者」療育手帳をお持ちのかた
2.デイサービス型【者・児】
創作的活動等や集団生活への適応訓練、食事や排泄等の介護を行います。
「対象者」身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかた
3.タイムケア型
放課後や長期休暇中に見守りや社会適応訓練を行い、活動場所を確保します。
「対象者」小学生から高校生までの、障害者手帳をお持ちのかた
申請方法
地域生活支援事業の申請方法をご覧ください。
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く