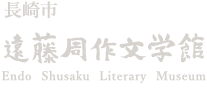本文
第12回文学講座(H22.10.09)
題目 『侍』を読む――日本人像を中心に
講師 海老井英次氏(九州大学名誉教授)
平成22年10月9日、海老井英次先生をお迎えし遠藤文学の第二の円環を閉じたといわれる『侍』についてお話をしていただきました。
『侍』の主人公・長谷倉は、命を受けた長い旅の中で時代や政策の変化によって自らが行った行為のすべてが作品が進むにつれことごとく無意味化していきます。それはつまり、政の世界の論理や、作中で語られる功利主義を本質とする日本人の論理では、長谷倉の旅(行為)が禁教令が布かれた時点で全て無に帰すということです。ですが、こうした論理に翻弄された長谷倉は、その中で自分の行為に意味を見出します。この「意味を見出す」ことこそが信仰の世界の問題であり、『侍』にみられる遠藤文学の核となる「私のイエスの発見」「寄り添うイエス」が導かれているとのお話でした。
また先生は、「人間がいかに生きるべきか」を考える小説として、夏目漱石→芥川龍之介→遠藤、もしくは漱石→太宰治→遠藤という近代文学の流れがあり、先生ご自身この流れの中で常に遠藤作品を捉えておられ、これは「近代文学研究の黄金ライン」とも言えると評されました。