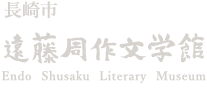本文
第33回文学講座(H29.3.4)
題目 遠藤周作『沈黙』の世界―長崎の歴史の視点で読む―
講師 本馬貞夫氏(長崎県長崎学アドバイザー)
平成29年3月4日(土曜日)、映画公開記念特別展の関連イベントとして、長崎県長崎学アドバイザーの本馬貞夫氏をお招きし、文学講座を開催しました。
本講座では、日本近世・近代史を専門とし、スコセッシ監督の映画『沈黙―サイレンス―』の時代考証をされた本馬氏に、映画制作時のエピソードや、小説・映画の題材となった長崎の歴史について、貴重な絵図や資料写真を見ながらお話しいただきました。
史実の視点から本馬氏は『沈黙』について次のように分析されました。小説の中で長崎奉行として描かれている井上筑後守について、遠藤はこの井上筑後守に江戸から明治までのキリスト教政策を集約させて描いたのではと指摘。例えば、井上とモキチのやり取りは浦上一番崩れの際の資料に、井上の「余は切支丹を邪教とは、つゆ、考えたことはない」という態度は、最後の長崎奉行・河津伊豆守が浦上四番崩れで浦上村の信徒である高木仙右衛門を説得した際の資料に類似していると解説されました。
また、映画の時代考証については、長崎の歴史はもとより、江戸時代の外海や五島の景観、当時栽培されていた野菜や植物、生物、建物についての細かい質問を製作チームからいくつも受けたそうです。時代考証のやり取りからも、スコセッシ監督が原作に忠実に描こうとしていた姿勢が窺えました。資料提供後は制作側の判断に委ねたため、映画でどのように描かれたのか首を長くして完成を待っていましたが「あれだけ調べたのに、家の中の再現とか食べ物とか、暗くてよくわからなかった」と笑いながら話され、本馬氏のユーモラスな話しぶりに会場は笑い声が絶えませんでした。
参加者は70名で市内にお住まいの方が多く、普段住んでいる土地の歴史に皆さま興味津々のご様子でした。アンケートには「もう一度注意深く映画を観たい」という感想が多く寄せられ、映像作品における時代考証の重要性と面白さを感じる時間となりました。