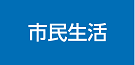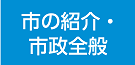ここから本文です。
個人市・県民税
更新日:2024年3月28日 ページID:009476
個人市・県民税の概要
個人市・県民税とは
税額の計算
- 計算方法
- 所得割と均等割
- 収入と所得
- 分離課税(土地建物の譲渡所得、株式の譲渡・配当所得)
- 所得控除(医療費控除など)
※令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例が設けられました。詳しくはこちらをご確認ください。 - 税額控除(ふるさと納税、住宅ローン控除など )
- 令和6年度における個人市・県民税の定額減税について
市・県民税申告等の手続き(個人)
特別徴収に関する手続き(事業主)
制度
関係先リンク
お問い合わせ先
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く