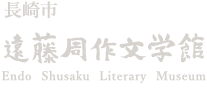本文
第27回文学講座(H26.8.30)
題目 遠藤周作と原民喜――かなしみの詩学
講師 若松英輔氏(「三田文学」編集長)
青来有一氏(作家)

青来氏(左)、若松氏(右)
平成26年8月30日(土曜日)、若松英輔氏(「三田文学」編集長)と青来有一氏(作家)を講師にお招きして、文学講座を開催しました。今回は当館と「三田文学」の共催でトークイベントとして対談形式で行いました。
遠藤周作宛ての原民喜の遺書を含む書簡数点の公開(同年5月より)にあわせ、遠藤と民喜の交流を軸にこれからの時代に文学が担う役割について、作家と批評家の立場から語られました。
長崎に生まれ、長崎に住み、原爆、切支丹の殉教の歴史という長崎の「土地の記憶」を作品に書いてきた青来氏。自分が書こうとする意志とは別のところで、「これを書かなければ」、と土地が呼びかけてくるものがあると話されました。それに対して若松氏は「自分の小説の人物たちがそこへ行くよう求めるから自分は旅をする」という遠藤の言葉があるが、民喜の場合も被爆直後の現状を死者のために「書かなければ」という意志は、大きなテーマを生んだと話された。「自分が求めるものではないところから書く動機はとても大切」と、創作について書き手であるお二人の見解が述べられました。
さらに、若松氏は遠藤のエッセイ集『走馬燈―その人たちの人生』から次の言葉を引用され、遠藤と民喜に共通する創作態度と死者への向きあい方について指摘されました。
「折にふれてその生きた場所を訪ね歩いてきた私には、彼等はもう死者ではない。小説家がいつかその人物のことを書こうとしてノートにその名前をしるした瞬間から、彼等はふたたび生きはじめるものだ」
死者は眠っているのではなく生者とともに何かをする存在。民喜から遠藤が太く摂取したのはその部分――死者の存在だと、小説家・遠藤周作の原点にある民喜の影響を語られた。
対談では、お二人の今日の文学に対する疑問と展望について聞く貴重な機会にもなりました。作品は活字になり読まれることで初めて文学になる、読み手は書き手と同じように文学を作り出している担い手。作家が変貌できる機会を潰さないよう、未熟なものを大切にし、育む土壌が必要だと、書き手である青来氏と、編集者と批評家である若松氏による、これからの文学への希望が語られました。