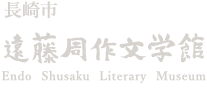本文
第35回文学講座(H30.3.3)
題目 「書き分ける作家」としての遠藤周作
講師 小嶋洋輔氏(名桜大学上級准教授)
平成30年3月3日(土曜日)、名桜大学上級准教授の小嶋洋輔氏をお招きして、文学講座を開催しました。
日本人にはあまりなじみのない“キリスト教”をテーマにした遠藤周作が、なぜ人気作家となったのか、高度経済成長期に拡大していった中間小説誌やテレビなどのメディアへの対応に注目し、純文学と純文学以外の作品とを書き分けていた遠藤のねらいについてお話しいただきました。
前半では、遠藤の純文学以外の仕事への姿勢と作品の特徴についてご説明いただきました。同時代の作家たちと比べると積極的にメディアを利用していたと言える遠藤。小嶋氏は、遠藤が描く純文学以外の作品には、実際に起きた事件や芸能人の名前、ひいては遠藤自身までが小説内で描かれていることを紹介し、メディアの拡大によって増えた読者に自分のテーマを伝えるため、読者に近づく手法で中間小説を描いていたのでは、と遠藤の戦略を述べます。
後半は、純文学と純文学以外とをどのように書き分けていたのか、具体的に作品を見ながら解説していただきました。例えば、1959年に書かれた純文学小説『火山』と中間小説『おバカさん』を取り上げ、純文学では書きえなかった〈救い〉を同時期の中間小説で描いていると指摘。他にも『ヘチマくん』『わたしが・棄てた・女』などを挙げ、純文学以外で現代日本人の〈救い〉を繰り返し描くことで、〈同伴者〉の概念の強度を高めていったと解説されました。そして、『深い河』は最後の純文学長編というだけでなく、現代日本人の問題がテーマとなり、中間小説で描かれ続けた〈同伴者〉の概念が結実していることからも、遠藤文学の集大成であると話されました。
遠藤の著作は膨大な量ですが、戦後文学史の背景、作品が発表された時期や媒体、作品の系譜に注目して読むことで、遠藤文学のテーマの深まりを理解することができるという、新たな視点が見えた講座でした。