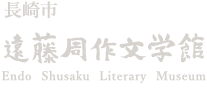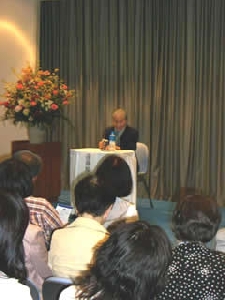本文
遠藤周作を偲ぶ一日(H21.5.16)
遠藤周作を偲ぶ一日(H21.5.16)
夫・遠藤周作からの宿題
平成21年5月16日(土曜日)、「遠藤周作を偲ぶ一日」のイベントとして、遠藤周作夫人の遠藤順子氏をお迎えし、「夫・遠藤周作からの宿題」と題して、40年に亘る結婚生活を通して、肌で感じられた夫・遠藤周作との日々について、ご講演いただきました。
昭和30年、慶応義塾大学仏文科の先輩と後輩という仲からご結婚され共に歩まれた中には、「10回入院・8回手術」、「結核でもう死ぬかもしれない」という時期が三回あったそうです。そうした時期を抱えながらも生涯執筆を続けた遠藤先生を、夫人は傍で懸命に支えてこられたわけですが、本講演でも「主人を一日でも長く生かしてあげたい、それしかなかったですね。」と明言しておられました。
講演の内容
「一生懸命勉強してきたけれども、切支丹のことは書かないで死ぬんだな。それは、すごく残念だな」
戦後初のカトリック留学生として渡仏した遠藤先生は、結核を患い、志し半ばの昭和28年2月に帰国しますが、その結核が再発し、昭和35年、東大伝染病研究所病院に入院します。手術を念頭におくようになってからというもの、内科の伝研病院から慶応病院への転院を決心されたそうですが、昭和37年、慶応病院で検査されたときには、「夫婦協力しなければ、あと一年持たない」という状況だったそうです。そのような中、3回目の手術が成功し、昭和37年に退院されますが、「切支丹のことを書かないで死ぬのは嫌だ」と口にされていた遠藤先生は、退院してすぐ「長崎へ」と願われたそうです。しかしながら、体力的な問題ですぐには叶わず、昭和38年になってようやく実現したそうです。随行された夫人曰く「この時点で既に『沈黙』の構想は出来ていたのではないでしょうか」とのことでした。
「捨石になる気はない。踏石になりたい」
死をも覚悟した時期を経験した遠藤先生は、「自分は何時死ぬかわからない。だから、どんなに非難をあびても、自分がこれが正しいと思ったことを書かずに死ぬことはできない」と仰っておいでだったそうです。特に『沈黙』上梓後は、教会の権威筋をはじめ非難されることも多く、ときには、夫人に「ご主人にあんなものを書かれちゃ困る」と、直接難色を示された方もおられたそうです。そんな時、遠藤先生は「言わせとけよ。今のカトリシズムの信者には理解してもらえなくても、いつか、自分の言ってることをわかってくれる人が出てくる。自分は、そうした時のための踏石になりたい」と仰っておられたそうです。
「21世紀の日本を3日でいいから主人に見てもらいたかった」
現在、夫人のもとには、遠藤先生について、外国からの問い合わせが屡々くるそうです。そうした問い合わせを考えてみると、「文学者」としてというよりはむしろ「宗教家」として遠藤先生を求めておられる方々が多いようであり、事実、出版社の方々からも同様のご意見を頂戴するとのことでした。夫人は、遠藤先生に「今の日本の状況を3日でいいから見てもらい」と思うそうです。遠藤先生が亡くなって約10年が過ぎましたが、「踏石になりたい」と願われた先生の思いと同じ方向へ向かって国内の状況も変化してきていると感じておられるとのことで、それは、『沈黙』上梓後しばらくは、教会方面においては四面楚歌という状況であったことを思えば、著しい変化です。遠藤先生から「日本人に合うキリスト教とは何か」という宿題を受け取った夫人ならではの思いの顕れであると感じます。