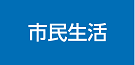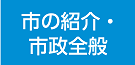ここから本文です。
市内で住所が変わったら(転居届)
更新日:2025年1月1日 ページID:000430
お引っ越し時の住民異動届の作成を支援します
来庁前に携帯電話やパソコンから「事前申請システム」を利用して住民異動届(転居届)を作成することができます。併せて事前に必要なものがわかるようになります。(詳しくはこちら)
(外部サイトへ移ります)長崎市事前申請システム(※中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)

また、中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の6ヵ所の地域センターでは、職員が来庁者の氏名・住所等の情報を聞き取りながら入力し、住民異動届(転居届)の作成を支援します。(従来より記入が少なくなります)
市内で住所が変わった時の手続き(転居届)
届出期間
転居の届出はお引越しした日から14日以内に手続きが必要です。
(補足)実際に転居した日以降にお届けください。
届出先
お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所に届け出てください。(各地域センター等の場所はこちらをご覧ください。)
受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで
土・日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。
持ってくるもの
- 本人確認書類
(補足)代理のかたが届出される場合は委任状が必要です。(詳しくは窓口での本人確認書類の提示と委任状についてをご覧ください。) 委任状(PDF形式 68キロバイト)
委任状(PDF形式 68キロバイト)
- 住民異動届(様式)ダウンロード
 住民異動届(PDF形式 209キロバイト)
住民異動届(PDF形式 209キロバイト)
転居届記入例ダウンロード 住民異動届 記載例 (転居届)(PDF形式 238キロバイト)
住民異動届 記載例 (転居届)(PDF形式 238キロバイト)
この用紙は地域センターなどに設置しています。届出には署名が必要です。
このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。一部を除いて、お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所で手続きができます。
市内間でお引っ越しされた時(転居)の手続き一覧について 転居手続き一覧(PDF形式 268キロバイト)
転居手続き一覧(PDF形式 268キロバイト)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人は
- 国民健康保険に加入している人は
- 介護保険に加入している人は
- 国民年金・厚生年金を受給している人は
- 小中学校の転校手続きは
- 被爆者健康手帳の交付を受けている人は
- 第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証の交付を受けている人は
- 後期高齢者医療保険に加入している人は
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は
- 児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている人は
- ひとり親家庭及び寡婦福祉医療費の助成を受けている人は
- 外国籍住民のかたは
- 水道、下水道の使用開始、廃止については
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人は
転居者全員分のマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
※住民基本台帳カードの住所変更は各地区事務所では手続きできません。
国民健康保険に加入している人は
国民健康保険被保険者証もしくは資格確認書をお持ちください。
詳しくは長崎市 国民健康保険をご覧ください。
介護保険に加入している人は
介護保険被保険者証をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
詳しくは介護保険制度をご覧ください。
国民年金・厚生年金を受給している人は
住民票以外の住所を送付先として設定中の年金受給者は、年金手帳をお持ちください。
小中学校の転校手続きは
転居届を出すときに交付される「転入学届」を通学中の学校へ提示して、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の交付を受け、指定された学校へ提出してください。
詳しくは入学・転校の手続きをご覧ください。
被爆者健康手帳の交付を受けている人は
被爆者健康手帳、各種手当証書をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
詳しくは被爆者健康手帳をご覧ください。
第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証の交付を受けている人は
第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
後期高齢者医療保険に加入している人は
後期高齢者医療被保険者証もしくは資格確認書をお持ちください。
詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は
手帳をお持ちください。
詳しくは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をご覧ください。
児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている人は
証書(児童扶養手当、特別児童扶養手当)をお持ちください。
ひとり親家庭及び寡婦福祉医療費の助成を受けている人は
福祉医療費受給者証をお持ちください。
詳しくはひとり親家庭福祉医療をご覧ください。
外国籍住民のかたは
転居者全員分の在留カード・特別永住者証明書をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
水道、下水道の使用開始、廃止については
詳しくは水道、下水道の使用の届出をご覧ください。
お問い合わせ先
長崎市 中央地域センター 住民記録係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(1階)
電話番号 095-822-8888(内線3373)
ページのトップへ
ダウンロード
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く