本文
長崎市各地の歴史概況と景観概況(2ページ)
2.長崎東南部地区
(1)歴史概況

長崎東南部地区には、今から6000年くらい前の縄文時代から弥生時代、古墳時代にかけて狩りや漁による人々の生活が行われていました。田上名・本郷名からは縄文時代の遺物、王台寺境内・千々名からは弥生時代の遺物が出土していて、文化面では古くから中国や朝鮮の影響を受けていたとされています。
今から800年くらい前までは、深堀を中心として、戸町より以南野母まで散在する島々含めて「戸八ヶ浦」と呼ばれていました。鎌倉時代末より、関東上総之国深堀氏がこの地に下向し、地名を深堀と改め、16世紀後半まで代々統治しました。江戸時代は佐賀鍋島深堀支藩となり、現在、当時の面影を残す武家屋敷跡を見ることができます。長崎街道が通る地域で、関門番所があり、今でもその名残をとどめる番所橋などが残っています。また、茂木街道の起終点である茂木は天草を結ぶ重要な港として発展し、現在でもまちなみ等に当時の面影を残しているところがあります。
(2)景観概況
1.長崎街道と宿場、日見峠の景観
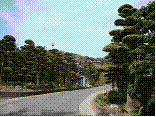
小倉から長崎までのルートの中で、宿場、峠越えの一連の街道景観が展開されています。八郎川に沿って矢上宿、矢上神社、本陣跡、役屋敷跡が往時の名残りを留め、日見峠には急坂のつづれ折れの峠道が残ります。
2.古賀植木の里・船石の農業集落景観

古賀・松原の植木の里には、400年の植木技術の歴史に育まれた庭園が見られます。樹齢600年を誇るラカンマキの枯山水庭園、迎仙閣の屋敷庭園、高級盆栽など秀逸なものがあります。
3.網場・戸石漁業集落と牧島の島しょ景観

橘湾の奥部に位置し、網場漁港、戸石漁港、牧島からなり、入り江の養殖いかだが象徴的です。普賢岳が地域のランドマークとなり、牧島の岩場、沖合島、網場のルイ14世岩などの自然海岸や、戸石漁港の石組み堤防が特徴的です。
4.茂木のまちなみ景観
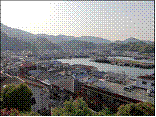
かつて旅館街で栄えた茂木街道沿いや若菜橋の本通り筋は、大きく変わることなく、町家・屋敷・鎧戸のある蔵が建ち並び、素朴で魅力的なまちなみを形成していて、風光明美な港、河口が印象的です。
5.断層海岸に展開する茂木ビワ産地の景観

茂木ビワは長崎半島の東向きの急斜面の段畑に植えられ、春先には、果実の袋をかぶる風景が、天草灘の広がりの中で、白や黄色の花が咲いたように展開します。
6.深堀武家屋敷のまちなみ景観

佐賀藩深堀領の鍋島家城下町跡として、中世・近世の地割り、掘割り、藩港が残っています。武家屋敷のまちなみが見られ、町割りは、佐賀藩との繋がりを示すものとして重要です。



