ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
長崎市各地の歴史概況と景観概況(10ページ)
10.高島地区
(1)歴史概況

1185年(文治元年)に平家の落武者が住みついたのが始まりといわれ、その後、1695年(元禄8年)に五平太という人物が石炭を発見しました。深堀氏の力を借りて1710年(宝永7年)頃から事業化して、高島での炭鉱時代の幕が開かれました。
高島炭坑が本格的に稼働を始めたのは、1868年(慶応4年)に、トーマス・グラバー氏が、佐賀藩との合弁により開発をはじめたころからです。グラバーは、深さ43メ-トルの竪坑を掘り、蒸気機関を用いて石炭を採掘しましたが、この竪坑は「北渓井坑(ほっけいせいこう)」と呼ばれ、日本で最初の洋式竪坑でした。
その後、高島炭坑は、1881年(明治14年)に三菱社の岩崎彌太郎氏に譲渡され、三菱の経営による操業が始まりました。これ以降、三菱は高島で採掘された石炭で得た利益をもとに、事業を拡大し、隆盛したといわれています。そのため、高島は、三菱発祥の地の1つといわれています。
(2)景観概況
1.石炭発見から近代炭鉱産業までを伝える産業遺構の景観

高島は、江戸時代に五平太が石炭を発見した地です。また佐賀藩とグラバー商会との間の合弁事業が進められ、わが国最初の蒸気機関による立坑が開坑した地です。
2.軍艦島の近代化産業遺産の景観
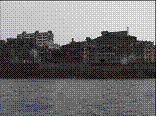
軍艦島の異名をもつ端島は、大正、昭和、高度成長期にかけて、わが国が石炭産業の近代化を成し遂げ発展してゆく姿をよく体現しています。工場部分とともに、住居部分の遺構が残り、都市的レベルまで高度に構築特化された特徴が見られます。



