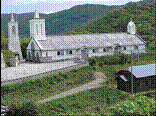本文
長崎市各地の歴史概況と景観概況(5ページ)
5.外海地区
(1)歴史概況

外海地区は、出津遺跡や宮田古墳群などの古代の遺跡をはじめ、中世の神浦氏関係史跡、近世の大村藩関係史跡、近代の社会福祉と宗教関係史跡など、さまざまな文化財が数多くあり、出津・黒崎を中心にキリスト教の文化が色濃く残る一方、神浦には、江戸時代初期に創建された寺や古い歴史を持つ神社など古来の文化が集積しています。
特に、明治時代のフランス人宣教師ド・ロ神父の活躍とあわせて、キリスト教の歴史は外海地区の文化的特質の一つです。また、大中尾の棚田、牧野の石造家屋、丸尾の石塀など、当時の生活の様子が偲ばれる資源も残されています。
昭和27年に松島炭鉱株式会社が池島で炭鉱開発に着手、同34年に営業出炭を開始し、それまでの半農半漁の村から石炭産業を基幹産業とする町へと発展しました。しかし、平成13年11月に、九州最後の炭鉱であった池島炭鉱が閉山しました。
出津教会
石積集落
(2)景観概況
1.角力灘の水平線と大角力・小角力・母子島の島しょ景観

角力灘の海洋と海食崖の間に、立岩や小島が群形をなして、あたかも石庭園の石の如く、海水面上にバランスよく点在しています。
2.石積み家屋のある集落景観

教会を中心に形成された小さなまとまりのある集落景観が見られます。痩せた土地、過酷な自然条件の中で、暴風を防ぐ温じゃく石を使った石積みの家屋や道路・墓地などが残されていることが特徴的です。
3.ド・ロ神父ゆかりの教会関連施設のある景観
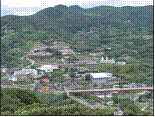
幕末以降の集落景観で、ド・ロ神父の功績を顕著にあらわす景観資源があります。聖堂・授産場等の教会関連施設の建設、ソーメン、マカロニ等の産業の育成、西洋の近代技術の導入、共同体組織による活動などが特徴的です。
4.神浦城址と河口港のまちなみ景観

渓谷の深い神浦川水系の河口にあり、山城・河口港を中心とした帆船時代のまちなみの構造を残していて、船着き場、伝統的な町家建築が現在も残っています。
5.大中尾棚田の景観
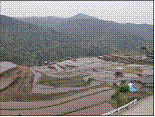
渓谷の緩斜面域に、江戸中期の大村藩により開拓された面積8ha、約450枚の棚田が連なります。対面にはケスタ地形による山岳、遠方には角力灘の島々が望め、雄大な自然景観を形づくっています。
6.池島の炭鉱跡の景観

閉山した炭鉱で、貯炭場、選炭工場、高台にある高層住宅群など、かつての産業施設の廃墟の景観が見られます。