ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
長崎市各地の歴史概況と景観概況(4ページ)
4.琴海地区
(1)歴史概況

琴海地区は、波静かな形上湾と村松湾に面する景勝地にあって、古代遺跡や中世末期の山城が残されています。戦国時代の末期より明治時代に至るまで300年間は、キリシタン大名であった大村氏の藩領に属し、廃藩置県後長崎県に属しました。
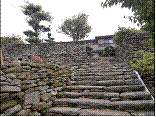
大村湾への大口瀬戸につながる形上湾に面する戸根から長浦の地先には、千々石ミゲルの従兄弟マリナが庵を結んだ自証寺、塩釜神社や三社神社、長浦墓地五輪塔などの歴史的な史跡が残っています。また、付近には、温じゃく石を使った石積のり面や石積塀の石積群が点在していて、当時の生活文化が感じられる斜面住宅が見られます。
長浦西瓜、真珠養殖、石材業といった生業が栄えてきました、昭和40年代後半からは、長崎市中心市街地のベットタウンとして宅地開発が進み、良好な自然環境に恵まれた定住拠点として発展してきました。また、これに併せて人口も増加してきました。
(2)景観概況
1.形上湾・大村湾の沿岸景観
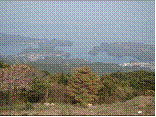
山並みの途中や尾戸半島から見る大村湾の遠景、海岸線沿いの丘のいたるところから俯瞰できる形上湾、海岸道路からの対岸の光景など、風光明美で変化に富みます。
2.自証寺と石積み集落の景観
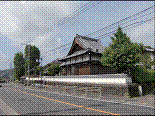
歴史的な史跡が集まり、千々石ミゲルの従兄弟マリナが庵を結んだ自証寺、塩釜神社や三社神社、長浦墓地五輪塔が見られます。温じゃく石を使った石積のり面や石積塀のある集落が見られます。
3.長浦~尾戸の農・漁業集落景観
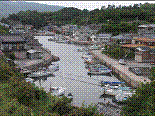
少ない平地や緩斜面を生かしたハウス栽培が多く見られます。尾戸のリアス式半島部は、温じゃく石積みの石垣による段々畑が発達し、真珠養殖の漁村集落や海際の水田景観が見られます。



