ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
長崎市各地の歴史概況と景観概況 (8ページ)
8.香焼地区
(1)歴史概況

香焼という地名は、弘法大師の香焼伝説に由来しているといわれています。もともとは、香焼島、蔭ノ尾島の二つの島からなり、徳川時代は佐賀藩・鍋島の支藩・深堀の所領でした。
明治以後、石炭と造船産業の衰退とともに歩み、最盛期(戦時中)の人口は2万人を超えるほどの盛況でした。

しかし、戦後の社会経済情勢の変化の中で、造船 (昭和30年)、石炭(昭和39年)がともに消滅し、沈滞化しましたが、長崎県が昭和41年から46年に香焼深堀間の臨海工業用埋め立てを行い、昭和42年に 旧造船所施設を三菱重工業株式会社が取得し、昭和47年には、最新鋭工場の完成に伴う本格的な操業を開始したことにより、再生を果たしました。
(2)景観概況
1. 歴史豊かなまちなみ景観と近代産業景観

香焼は長崎港口の島で、行き交う船の航海安全祈願をする高台の寺院・神社があります。深堀との瀬戸を埋め立てて出来た三菱造船所は、長崎港口のランドマークになっています。
2. 炭鉱跡集落の景観
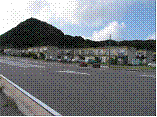
恵里は、香焼の石炭発祥の地で、炭鉱住宅群、炭坑口等の遺構が各所に残っています。また集落正面の美しい海には、採掘のため水没した横島が波間に見え、炭鉱の栄枯盛衰の一面を見せています。
3. 大中瀬戸の自然景観

岩石浜の岬から間近に往来船を見ることができ、香焼の島々とその奥の長崎港、外海や高島、野母崎へのパノラマが楽しめる場所です。



